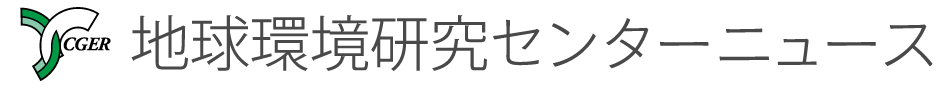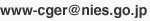2012年10月号 [Vol.23 No.7] 通巻第263号 201210_263003
地球環境モニタリングステーション—波照間20周年 1 波照間ステーション設立の経緯
国立環境研究所では、1992年に沖縄県八重山郡竹富町波照間島に波照間ステーションを設置し、二酸化炭素、メタン等の温室効果ガスやその関連物質等のモニタリングを長期間継続的に実施しています。このたび、波照間ステーションの竣工から20年を迎えることとなり、地球環境研究センターニュースでは、ステーション設立の経緯やこれまでの観測成果等を紹介していきます。シリーズ第1回は、設立当時の担当であった井上元さんに当時のことを振り返って原稿をいただきました。
環境庁(現環境省)は1988年に地球温暖化・二酸化炭素問題をはじめとする地球環境問題に全面的に取り組むことを決めた。その一環として地球環境モニタリング・研究支援(スーパーコンピュータ)経費と地球環境研究総合推進費を予算化した。地球環境モニタリングは、1990年に国立公害研究所を国立環境研究所に改組するにあたり、新たに設立された地球環境研究センターが、所内外の研究者の協力を得て担当することになった。
温室効果ガスのモニタリングとして、地上での定点観測と航空機による観測が2本の柱として予算化された。温室効果ガスの濃度変化は長期蓄積的であるから、長期継続的モニタリングが前提であるが、それと同時に最先端の研究的観測を行うという点に、研究所が実施する意義があると考えた。また予算はつくが職員はほとんど増やせないという制約もあり、無人化・自動化がもう一つの前提となった。大蔵省(当時)の主査からは「こんなに少人数の組織(4人)で、こんなに大きな予算(2.2億円)が使えるのか? 大学や民間の協力を得てやるというが、それなら組織はいらないということか」という指摘があった。私は後ろに控えていたのだが、思わず「研究者は研究費がなければ自分で旋盤を廻してでも装置を作り、研究する。予算があれば外注するなどして効率的に進めることができる。要はやる必要がある観測かどうかだ」と査定の観点を批判するような不規則発言をしてしまったことを覚えている。
国際的に認められる高精度の二酸化炭素の濃度測定は直接の人為影響の少ない場所で行う必要がある。しかし、そうした場所に人を派遣するには時間と経費がかかるので、頻度を下げざるを得ない。機械化による自動測定はリスクの大きな試みであったが、結果的には、人がいない方が再現性が良く精度が高まるという面もあった。
実をいうと当初環境庁は、地方自治体に委託して各地で観測するという発想をもっていた。その方針は企画調整局長が私的に諮問した研究者の意見により修正され、2〜3カ所での観測ということになった。国内で行う観測ではあるが地球規模の炭素循環解明に貢献するためには、南北に大きく離れた場所で観測するのが妥当である。そのため、ターゲットを沖縄と北海道とに決めた。当時の沖縄はリゾート開発ブーム下でもあったことから、開発の恐れの少ない場所という点も考慮して、国立公園であり環境庁の事務所もある西表島が候補として浮かんだが、密な植生の影響は避けられないと断念した。次に植生の少ない周辺のサンゴ礁の小島に目を移し、波照間島が候補として挙がった。
波照間島は人口が少なく、主たる産物はサトウキビである。二酸化炭素の発生源は島の中央にあるディーゼル発電所と北岸の精糖工場である。飛行場が東部にあるが燃料補給はなく、小型飛行機の定期便が1日1便あるだけである。島民は土地を島外の人に売らないため、開発が進んでしまう可能性も低い。こうした状況がわかり「これほど条件のよい場所はほかにない」と確信した。
現地の区長、竹富町役場(なんと町内ではなく石垣市にある)、沖縄県庁、林野庁などを訪問して協力を要請し、島の東部の国有地を候補地とし、用地を確保した。日本で人が住む最南端の地の、観光で訪れただけでは想像もできないような実態を図らずも垣間見ることにもなった。
次に建物をどのように建設するかであるが、台風や塩害などを考慮して経験豊かな建設省(当時)の沖縄営繕に依頼することにした。担当の方々は大変な意気込みでいろいろ工夫してくれた。たとえば、八重山の人家がサンゴ礁の垣根で囲まれているのは、風通と断熱性があり、窪みに溜まった雨水が蒸発して建物を冷却するなど、沖縄の自然に適した省エネ効果があるからである。そこでステーションの基礎工事で出てくるサンゴ岩を海側の壁面と屋根に積もうということになった。耐荷重を計算してみるとサンゴ岩は意外と軽いらしい。実際台風で直径30㎝もあるサンゴ石がステーションに飛んできたほどである。大気の採取はできるだけ高い鉄塔から採取したいが、予算の制限もあって、高さを40mとし、塩水で錆びないようブリキ塗装を3回繰り返し(これは沖縄仕様らしい)、さらに、ペンキを塗るというものにした。それに、いろいろな観測の試みがなされることを予想して、機器を持って安全に登れるように20mまでは内階段とした。台風時の停電などはあるが、予想していたほど電力事情が悪くなかったのは幸いである。

ステーションの壁面と屋根に積まれたサンゴ岩
こう書いていくと、経験のある人が見識をもって決めていって成功したように聞こえるが、実際には私も、一緒に立ち上げを行った内山・泉の二人も、事務方の荒木らも、温室効果ガスの観測研究の経験は皆無であった。もちろん東北大学の中澤高清氏らの助言やケープグリム(豪)訪問による知識など、先人に多くを学んだが「理詰めで正しくやれば間違いない」という若さからくる自信で走り抜けたと言ってよい。しかも、同時にシベリアでの航空機観測も始めていたのだから、今考えると無鉄砲だったと言った方が正しいかもしれない。
観測を開始するとき「研究者は一般に長く観測を続ける体質をもたない。少なくとも10年は続けると約束せよ」と詰めよられたことを覚えているが、その倍の20年を経ていること、さらに今でも内容的に発展していることを、創始者の一人としてうれしく思っている。