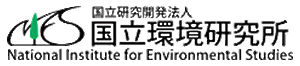より精緻な科学的知見を提供 −IPCC第1作業部会第6次評価報告書概要−
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、気候変動の自然科学的根拠を担当する第1作業部会(WG1)の第6次評価報告書(AR6)(以下、AR6/WG1)を2021年8月9日に公表しました。執筆に携わった一人として、AR6/WG1の概要を紹介します。
なお、AR6/WG1の政策決定者向け要約(SPM)の気象庁による暫定訳はhttps://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar6/IPCC_AR6_WG1_SPM_JP_20210901.pdfをご覧ください。
また、動画による解説は、【速報版】IPCC執筆者が独自解説!「気候変動 国連最新レポート」(国立環境研究所YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/watch?v=dLgGSI0G2SA)をご覧ください。
AR6/WG1のヘッドライン・ステートメント(概要)は次の4つのカテゴリーに分類され、合計14項目あります。
A 気候の現状(4)
B 将来ありうる気候(5)
C リスク評価と地域適応のための気候情報(3)
D 気候変動の抑制(2)
本稿では14のステートメントすべてについて内容を紹介し、解説を加えていきたいと思います。
A. 気候の現状
A.1 人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。大気、海洋、雪氷圏及び生物圏において、広範囲かつ急速な変化が現れている。
IPCCの報告書では、「20世紀後半以降の温暖化の主な原因は人間活動である可能性が…」という表現が2001年に公表された第3次評価報告書から出てきました。そのときは可能性が「高い、66%以上」でしたが、第4次評価報告書では「非常に高い、90%以上」となり、前回の第5次評価報告書(AR5)では「極めて高い、95%以上」と書かれてきました。AR6/WG1では、「人間の影響が気候システムを温暖化させてきたのは疑う余地がない」となり、初めて不確実性の表現が外れました。

1850年から2020年までの世界平均気温変化のグラフとコンピュータシミュレーションモデルで再現計算した気温変化を比較すると、観測データと合っているのは人為要因(人間活動による温室効果ガスの増加など)+自然要因(太陽活動の変動や火山の噴火)のシミュレーション結果です。このようなグラフは第3次評価報告書から出ていますが、AR5からAR6の間に、気温データやシミュレーションモデルの精度が上がり、気候メカニズムの理解も進みました。定量的には、2019年までに観測された気温上昇が産業革命前と比べて1.06℃、そのうちの人間活動の寄与は1.07℃と評価されていますので、これは疑う余地がないという結論になりました。
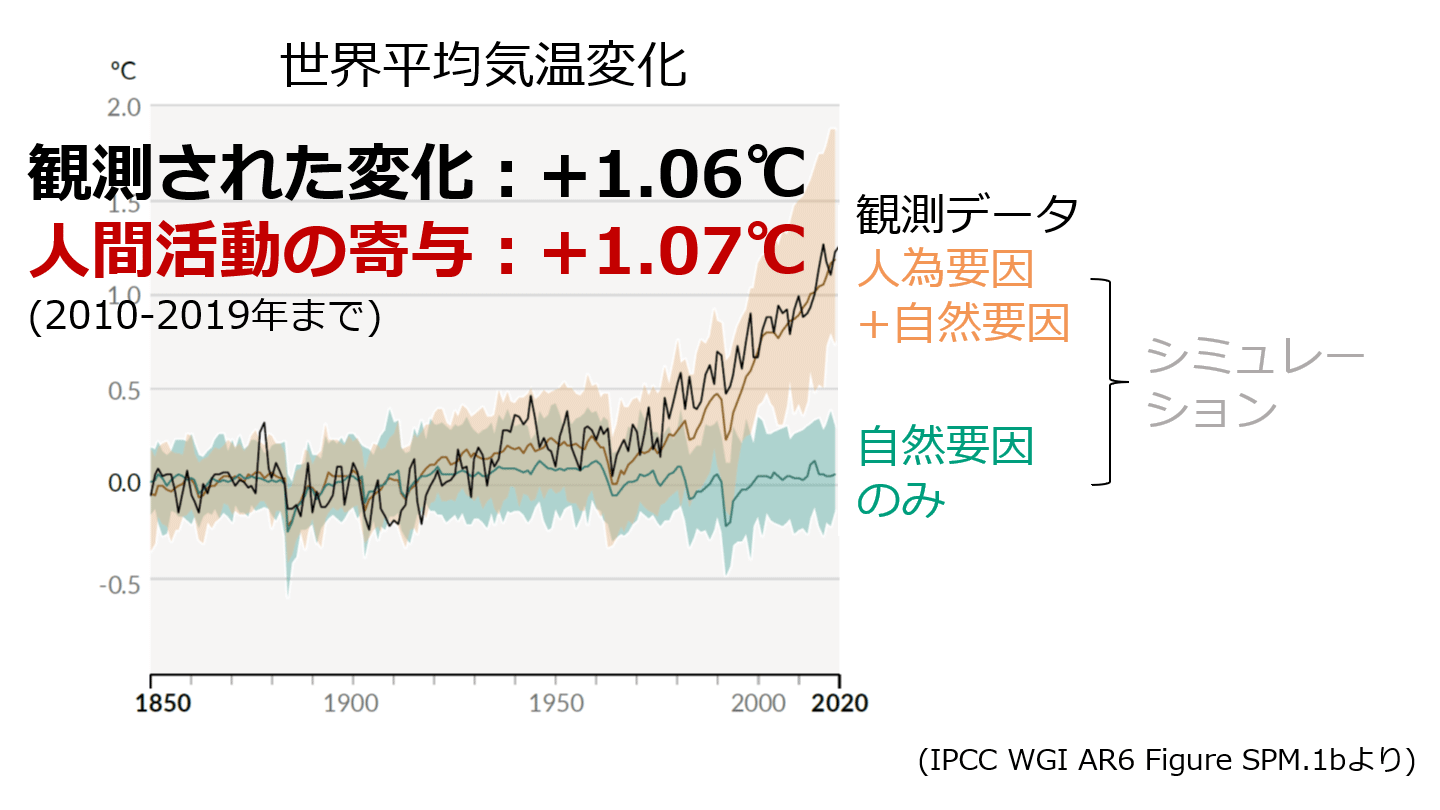
A.2 気候システム全般にわたる最近の変化の規模と、気候システムの多くの側面の現在の状態は、何世紀も何千年もの間、前例のなかったものである。
西暦1年から2020年までの世界平均気温変化から、最近の温度上昇が特別なのははっきりしていますし、約1万年前から始まった現在の間氷期が始まってからを見ても前例がないと考えられます。
A.3 人為起源の気候変動は、世界中の全ての地域で、多くの気象及び気候の極端現象に既に影響を及ぼしている。熱波、大雨、干ばつ、熱帯低気圧のような極端現象について観測された変化に関する証拠、及び、特にそれら変化を人間の影響によるとする原因特定に関する証拠は、AR5以降、強化されている。
人間活動の影響により異常気象が増えています。一例を挙げますと、産業革命前には50年に一度しか起きないレベルの暑さが、産業革命前と比べて1℃温暖化した現在では4.8倍、つまり50年に5回くらい起きています。産業革命前と比較して1.5℃温暖化すると8.6倍になり、2℃温暖化すると13.9倍になります。現在と比較しても、1.5℃上がったら倍くらい、2℃温暖化すると3倍くらい、極端に暑い日の頻度が増えるということが、AR6/WG1に書かれました。
A.4 気候プロセス、古気候的証拠及び放射強制力の増加に対する気候システムの応答に関する知識の向上により、AR5よりも狭い範囲で、3℃という平衡気候感度の最良推定値が導き出された。
平衡気候感度とは、「大気中の二酸化炭素(CO2)濃度を倍にして十分時間が経ったときの世界平均気温上昇」です。40年前の推定では1.5℃から4.5℃の間である可能性が高いといわれました。その後IPCCの報告書で毎回評価されているのですが、研究が進んでも新しい不確実要素が見つかったりして、この幅が狭まらなかったのです。しかし、さらに新しい研究がなされ、AR6/WG1では2.5℃から4℃の可能性が高いとなり、今まで3℃あった幅が1.5℃に狭まりました。そして、3℃がbest estimate(最良推定値)となりました。
気候感度が低い(地球の温度は上がりにくい)かもしれないという推定は、地球温暖化のための対策をあまりしなくてよいという考えにつながります。しかし、今回の結果により「気候感度が低いかも」はもう通用しなくなりました。これは政策的に非常に重要なことだと思います。
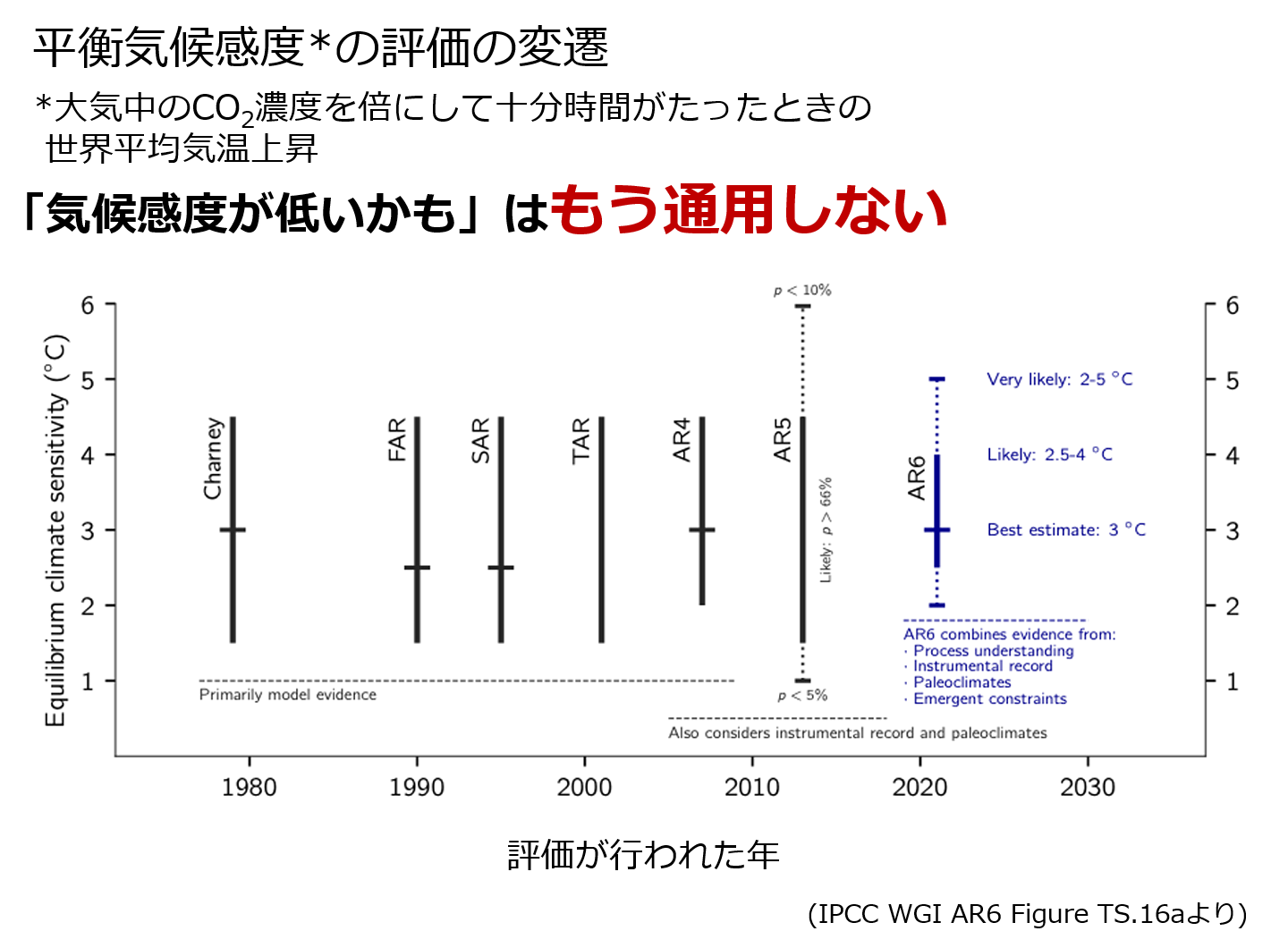
B. 将来ありうる気候
B.1 世界平均気温は、本報告書で考慮した全ての排出シナリオにおいて、少なくとも今世紀半ばまでは上昇を続ける。向こう数十年の間に二酸化炭素及びその他の温室効果ガスの排出が大幅に減少しない限り、21世紀中に、地球温暖化は1.5℃及び2℃を超える。
AR6/WG1では、共通社会経済経路(Shared Socioeconomic Pathways: SSP)*1をベースにした 5つのCO2排出シナリオ(不確実な将来に対して複数の可能性を設定したもの)で検討しました。「非常に高い(化石燃料を使い続ける最悪ケース)」、「高い(温暖化対策が後退する)」、「中間(現状レベルの温暖化対策)」、「低い(パリ協定の2℃を目指す)」、「非常に低い(パリ協定の1.5℃を目指す)」の5つです。
この5つのシナリオについて世界平均気温の変化の見通しを見ると、脱炭素化しなかった場合である上位の3つでは2100年までに2℃よりも上昇します。排出が低いシナリオだと2℃より十分低く、非常に低いシナリオだと、1.5℃を少し超えますが下がってきます。
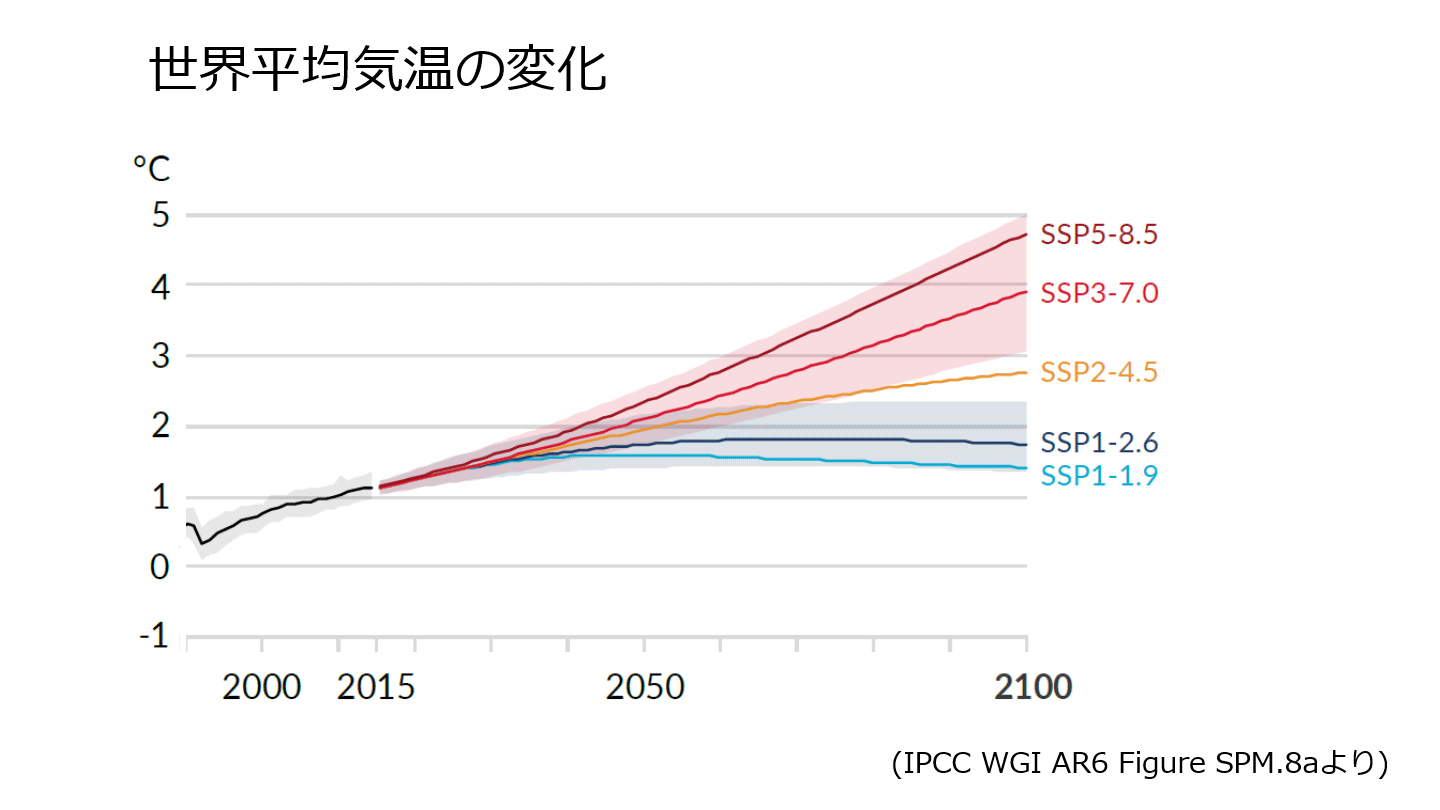
B.2 気候システムの多くの変化は、地球温暖化の進行に直接関係して拡大する。この気候システムの変化には、極端な高温、海洋熱波、大雨、いくつかの地域における農業及び生態学的干ばつの頻度と強度、強い熱帯低気圧の割合、並びに北極域の海氷、積雪及び永久凍土の縮小を含む。
熱帯低気圧や台風、ハリケーンの数自体は減るという研究が多いのですが、強いものの割合が増えます。日本にとって重要なのは、台風は今後、より緯度が高いところで最大の強さになります。つまり台風は発達しながら日本に近づいて来るケースがこれから増える傾向にあると書かれています。
B.3 継続する地球温暖化は、世界全体の水循環を、その変動性、世界的なモンスーンに伴う降水量、降水及び乾燥現象の厳しさを含め、更に強めると予測される。
世界全体でこれまでより多く雨が降り、多く蒸発します。つまり水循環が強くなります。しかも変動性も強まります。雨が降りやすいところではより大雨が降り、乾燥しやすいところではさらに乾燥します。
B.4 二酸化炭素(CO2)排出が増加するシナリオにおいては、海洋と陸域の炭素吸収源が大気中のCO2蓄積を減速させる効果は小さくなると予測される。
現在、人間活動によって排出されたCO2の半分強は海洋や陸域の生態系が吸収しています。しかしCO2の排出量が増えて温暖化が進むほど、吸収できる割合が減っていき、より多くのCO2が大気中に残るようになると予測されています。
B.5 過去及び将来の温室効果ガスの排出に起因する多くの変化、特に海洋、氷床及び世界海面水位における変化は、百年から千年の時間スケールで不可逆的である。
世界平均海面水位は1900年から現在までにすでに20cmくらい上がっています。今世紀末までの予測としては、非常に排出が低い1.5℃のシナリオの場合50cmくらい、非常に高いシナリオの場合、最悪1m上昇します。さらに、南極の氷床が不安定化して崩壊が始まったら、1.5m以上海面上昇することもあり得ます。
海面上昇は2100年以降も続きます。2300年には、2℃を目指した低いシナリオで0.5mから3m、非常に高いシナリオだと2mから7mも上昇し、南極氷床の不安定化が起きた場合には15mまで上昇するかもしれません。つまり、2100年には海面上昇は始まったばかりで、人間活動によってさらに数百年続くという認識が必要です。
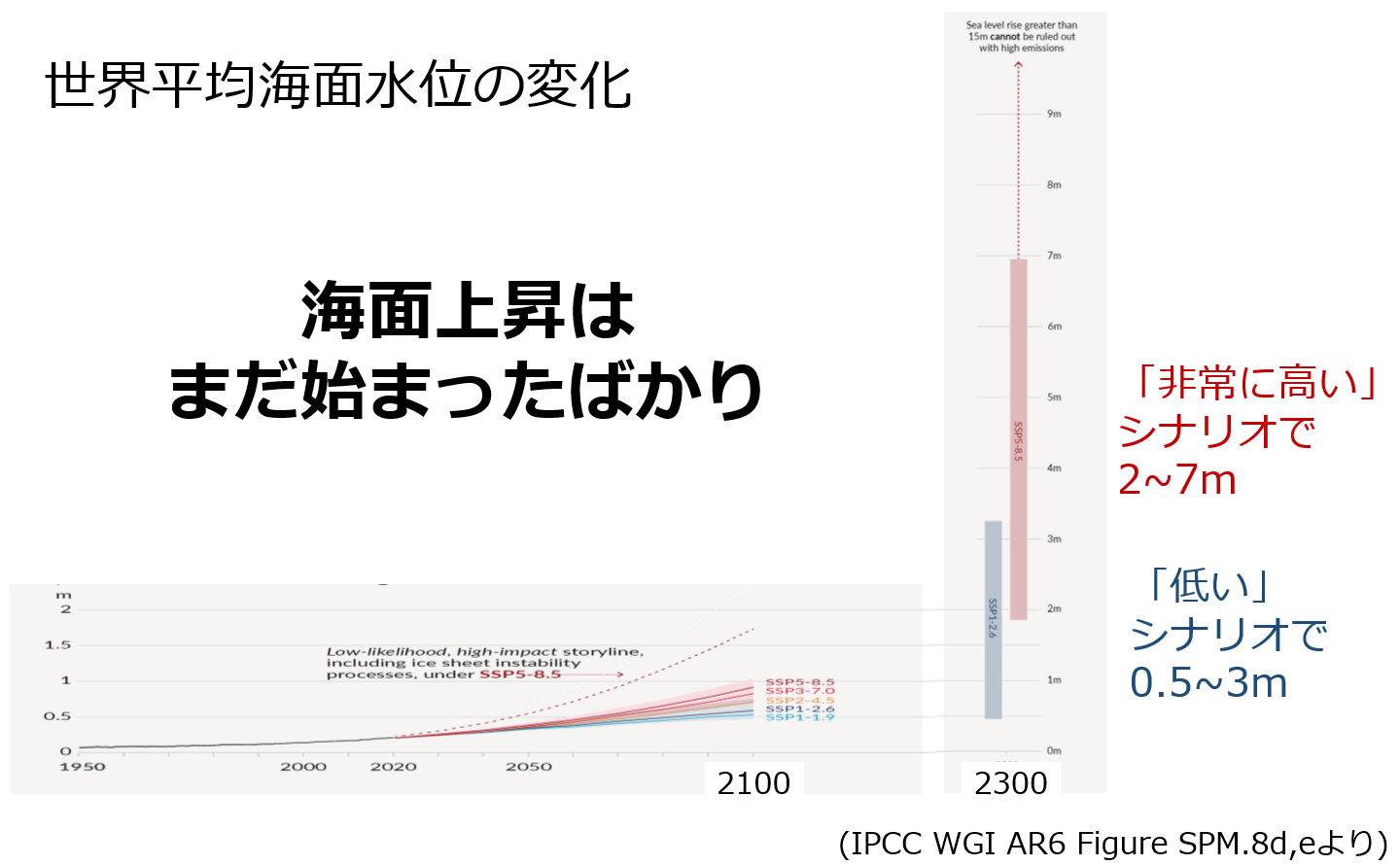
C. リスク評価と地域適応のための気候情報
C.1 自然起源の駆動要因と内部変動は、特に地域規模で短期的には人為的な変化を変調するが、百年単位の地球温暖化にはほとんど影響しない。起こりうる変化全てに対して計画を立てる際には、これらの変調も考慮することが重要である。
自然起源の駆動要因というのは、太陽活動の変動や火山の噴火など、人間のせいではない外部的な要因です。内部変動は、エルニーニョなど気候システムの内部で起こる変動です。
温暖化の将来予測には自然の変動を考慮しなければなりません。変動が重なるので、来年の方が今年より温度が下がることはもちろんあります。それも考慮して適応策を考えなければいけないということです。
C.2 より一層の地球温暖化に伴い、全ての地域において、気候的な影響駆動要因(CIDs)の同時多発的な変化が益々経験されるようになると予測される。1.5℃の地球温暖化と比べて2℃の場合には、いくつかのCIDsの変化が更に広範囲に及ぶが、この変化は、温暖化の程度が大きくなると益々広範囲に及び、かつ/又は顕著になるだろう。
気候的な影響駆動要因(Climatic Impact Driver: CID)は、ほぼ「ハザード」の意味です。ハザードは、一般的にいうと危険の原因となるもののことで、悪いことに対して使いますが、CIDはいいことも含みます。たとえば寒いところで気温が上がったらいい影響もありますから、ハザードをいいことも含めて拡張したことばにしたのがCIDです。
大雨はハザードですが、人がいないところに大雨が降っても災害にはなりません。しかし、多数の居住者が災害の危険にさらされている(ハザードに曝露している)状態で、さらにその人たちが脆弱(備えができていない、対応力がない)だと被害が大きくなります。気候的な要因とともに、曝露や脆弱性といった社会的な要因があり、影響が評価できます。曝露から影響までは2022年2月公表予定のWG2(影響・適応・脆弱性)の守備範囲なので、AR6/WG1ではCIDを地域ごと、項目ごとに詳しく調べて、WG2に渡す準備ができました。
CIDが複合的に起きる、複合災害についても書かれています。たとえば高温と乾燥に強風が加わると、森林火災が起きやすくなります。そして世界平均気温の上昇が1.5℃、2℃になるとどうなるかということが地域ごとに評価されています。
C.3 氷床の崩壊、急激な海洋循環の変化、いくつかの複合的な極端現象、将来の温暖化として可能性が非常に高いと評価された範囲を大幅に超えるような温暖化など、「可能性の低い結果」も、排除することはできず、リスク評価の一部である。
可能性は低いが、起きてしまうと大変なことになる現象があります。たとえば、海面上昇のところで述べた氷床の崩壊のほかに、急激な海洋循環の変化などが起きてしまうと大きなインパクトがあるといわれます。可能性が低い、あるいは可能性がまだ科学的に評価できないことでも、起こってしまうと大変なことになるものについては、リスクとして考えていかなければなりません。
D. 気候変動の抑制
D.1 自然科学的見地から、人為的な地球温暖化を特定のレベルに制限するには、二酸化炭素(CO2)の累積排出量を制限し、少なくともCO2正味ゼロ排出を達成し、他の温室効果ガスも大幅に削減する必要がある。メタン排出の大幅な、迅速かつ持続的な削減は、エーロゾルによる汚染の減少に伴う温暖化効果を抑制し、大気質も改善するだろう。
人間活動ではCO2だけではなく大気汚染物質も排出しています。大気汚染物質のなかには、大気中で微細な粒子(エアロゾル)になって日射を遮り地球を冷やす物質もあります。大気汚染対策や温暖化対策によって大気汚染が改善されると、地球を冷やす物質も減ってしまうので、かえって温度上昇の要因になります。
これに対処するにはメタン排出の大幅削減が効果的です。メタンは温室効果ガスですが、寿命が短いので、排出削減すると、比較的早く大気中で減少します。しかもメタン自体が大気汚染の原因になっていますから、メタンを急激に削減し、同時に他の大気汚染物質も減らしていくと、温暖化対策としても大気汚染対策としても非常に有効です。
CO2累積排出量は年々のCO2排出量を足したもので、AR5から強調されていることですが、気温上昇量はCO2の累積排出量にほぼ比例します。ここからカーボンバジェットという考え方が出てきました。気温上昇量の上限を決めると残りの累積排出量が決まってきます。
一例を紹介します。不確実性に幅があるので確率的な表現になるのですが、50%の確率で1.5℃にとどまるためには、2050年までの累積排出量を500GtCO2に抑えなければならないということがAR6/WG1に書かれています。
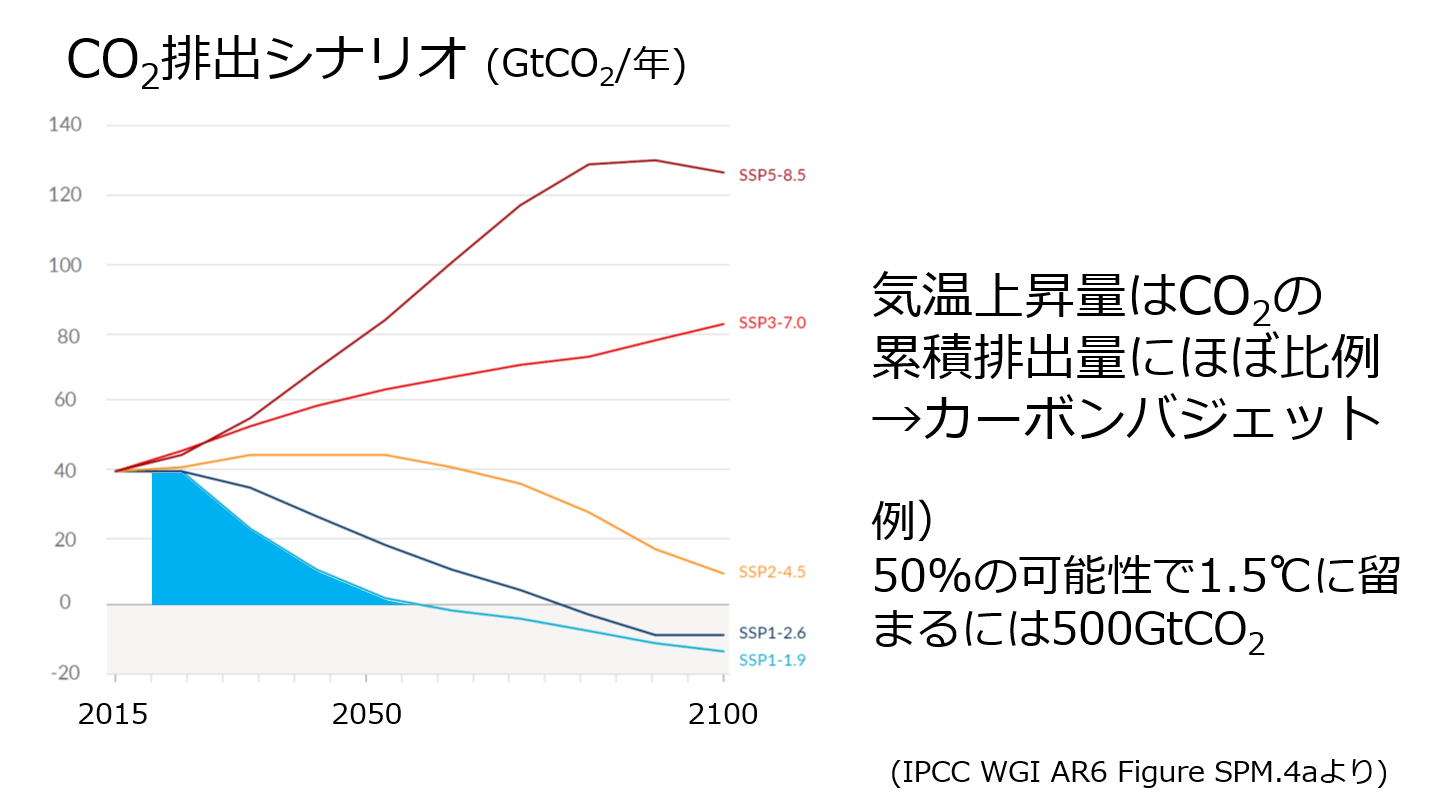
D.2 温室効果ガス排出量が少ない又は非常に少ないシナリオは、温室効果ガス排出量が多い又は非常に多いシナリオと比べて、温室効果ガスとエーロゾルの濃度及び大気質に、数年以内に識別可能な効果をもたらす。これらの対照的なシナリオ間の識別可能な差異は、世界平均気温の変化傾向については約20年以内に、その他の多くのCIDsについてはより長い期間の後に、自然変動の幅を超え始めるだろう(確信度が高い)。
識別可能な効果とは、対策を進めたときに、対策の効果が目に見えてわかることです。大気中のCO2濃度は数年で対策の効果が表れてくるでしょう。しかし気温に関しては年々の自然変動があり、それを考えると対策の効果がわかるのに20年くらいかかります。
AR6/WG1では、2021年から2040年の近未来で平均した気温上昇が5つのどのシナリオでも五分五分以上の可能性で1.5℃を超える。言いかえれば2030年前後で1.5℃を超えそうだとされています。これが、2018年10月に公表された「1.5℃特別報告書」*2における「現在の度合いで温暖化が進行すれば、2030~2052年の間に1.5°Cに達する可能性が高い」より、時期が早くなっているのではないかと話題になっています。
IPCCは、評価の仕方を変えたため直接比較ができないので、10年程度早まったと単純に解釈しないでほしいとしています。AR6/WG1の結論では、今後20年経って振り返ると、1.5℃を超えていたということは避けるのは難しそうだという感じです。非常に低いシナリオに到達すれば、1.5℃を超えないくらいで進んでいくことができます。当然これを目指すことが重要ですが、1.5℃を超えても超えたとたんに世界が終わる訳ではありませんので、脱炭素を確実に続けていくことには変わらないだろうと思います。
まとめ
全体として、AR6/WG1においては、科学がより精緻なものになりました。とはいえ、AR6/WG1の結果を受けて、11月に開催されるCOP26に向けてパリ協定の目標の解釈が大きく変わることはないでしょう。科学の精緻化はより説得力をもつことにつながりますから、脱炭素をさらに強い決意で進めていくことが重要ではないかと個人的には思っています。
今後、2022年2月にWG2(影響・適応・脆弱性)の報告書、3月にはWG3(緩和策)報告書、9月に統合報告書が公表されます。これらが出揃ったところで、AR6の意味をあらためて検討することになると思います。
IPCC報告書はなぜ信用できるのか
- 66か国からの200人以上の専門家が集まって執筆
- 14,000本の論文を引用
- 3回にわたる査読(レビュー)で専門家からコメントが提出
- 78,000件のレビューコメントにすべて対応
- コメントと対応もすべて公開
作成過程における包括性と厳密性、及び透明性がIPCCの報告書を信頼のおけるものにしている。