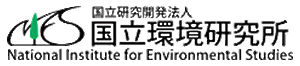最近の研究成果 大アンサンブル実験で見えてきた海面水温の南極渦やオゾン層への影響
冬季の極域は一日中太陽光が当たらない極夜となっているため、極域成層圏の気温が低下して、極周辺に強い西風で特徴付けられる極渦という低気圧が現れます。この極渦の中で毎年春季に大規模なオゾン層破壊が起こりオゾンホールの出現につながりますが、稀に成層圏突然昇温(SSW)*1が発生し南極渦が弱まってオゾン層破壊にも影響を及ぼすことがあります。そのような年の海面水温を与えた実験を行い、気候値的な海面水温を与えた実験と比較しました。
図1は南極渦強度の指標となる南緯60度、10 hPa高度(上空約30 km)の東西風の時間変化を示しています。通常、南半球冬季の終わりから春季にかけて、季節進行とともに徐々に極渦強度が低下していきますが、稀に大きく極渦強度が低下する年(細線で示した1988年、2002年、2019年)があり、そのような年にはSSWが発生していました。
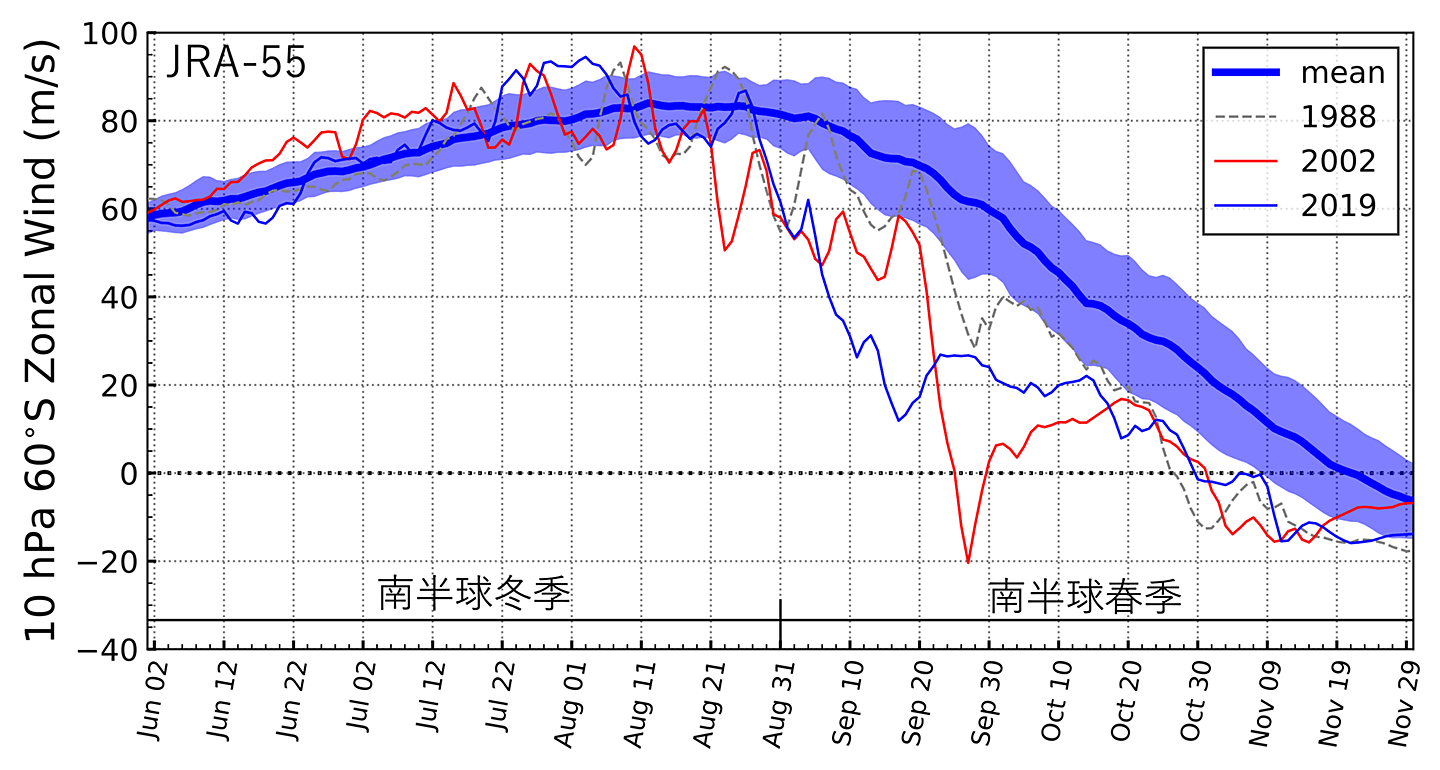
こうしたSSWの発生した年の海面水温を与えた実験を行うことで、海洋の南極渦やオゾン層への影響を調べようと考えました。オゾン層への影響を調べるためには、大気の運動や放射などを表現する気候モデルの計算に加えて、オゾンに関連した大気微量成分の化学反応や輸送などの計算が必須となるため、国立環境研究所で開発されてきた化学気候モデル(MIROC3.2-CCM)を用いることにしました。
南極渦は安定していて、そもそもSSWのような大きな変動は起こりにくいのですが、過去の観測事実が示す通り、ごく稀に大きな変動が起こる可能性があります。そのような稀な変動を検出するためには非常に多くのシミュレーション(アンサンブルメンバと呼んでいます)が必要となります。
化学気候モデルによるシミュレーションには計算時間を要するため、1000メンバの大アンサンブル実験で海面水温が南極渦やオゾン層へ及ぼす影響を調べることができたのはこの研究が世界初となりました。スーパーコンピュータを利用しても、1つの大アンサンブル実験を行うのに実時間として通常2ヶ月程度かかっています。
すべての年を調べるには膨大な計算時間が必要なため、極渦強度の低下が特に大きかった2002年と2019年に絞って、それぞれの年の海面水温を与えた実験を行いました。標準実験として海面水温を1991~2020年の30年間の平均値に設定した実験を行いました。海洋条件以外は全て同じなので、標準実験からの差が海洋の影響によるものと考えることができます。なお、大気微量成分の濃度は2000年の値に設定されています。
シミュレーションの結果、2002年、2019年の海面水温を与えた実験(赤)では、気候値的な海面水温を与えた実験(黒)よりも対流圏から成層圏への惑星スケールの波伝播*2が活発になるため、南極渦強度が低下していました(図2)。また、南極域のオゾン全量を調べると、南極渦強度の低下と整合的に増加していました。
2002年と2019年のアンサンブルメンバの分布を見ると、下方側に箱やひげの下端、外れ値が大きく拡がっています。このように、大アンサンブル実験を行うことで、2002年、2019年の海面水温によって成層圏の南極渦やオゾン層に、稀ではあるが大きな変動が起こり得ることを示すことができました。
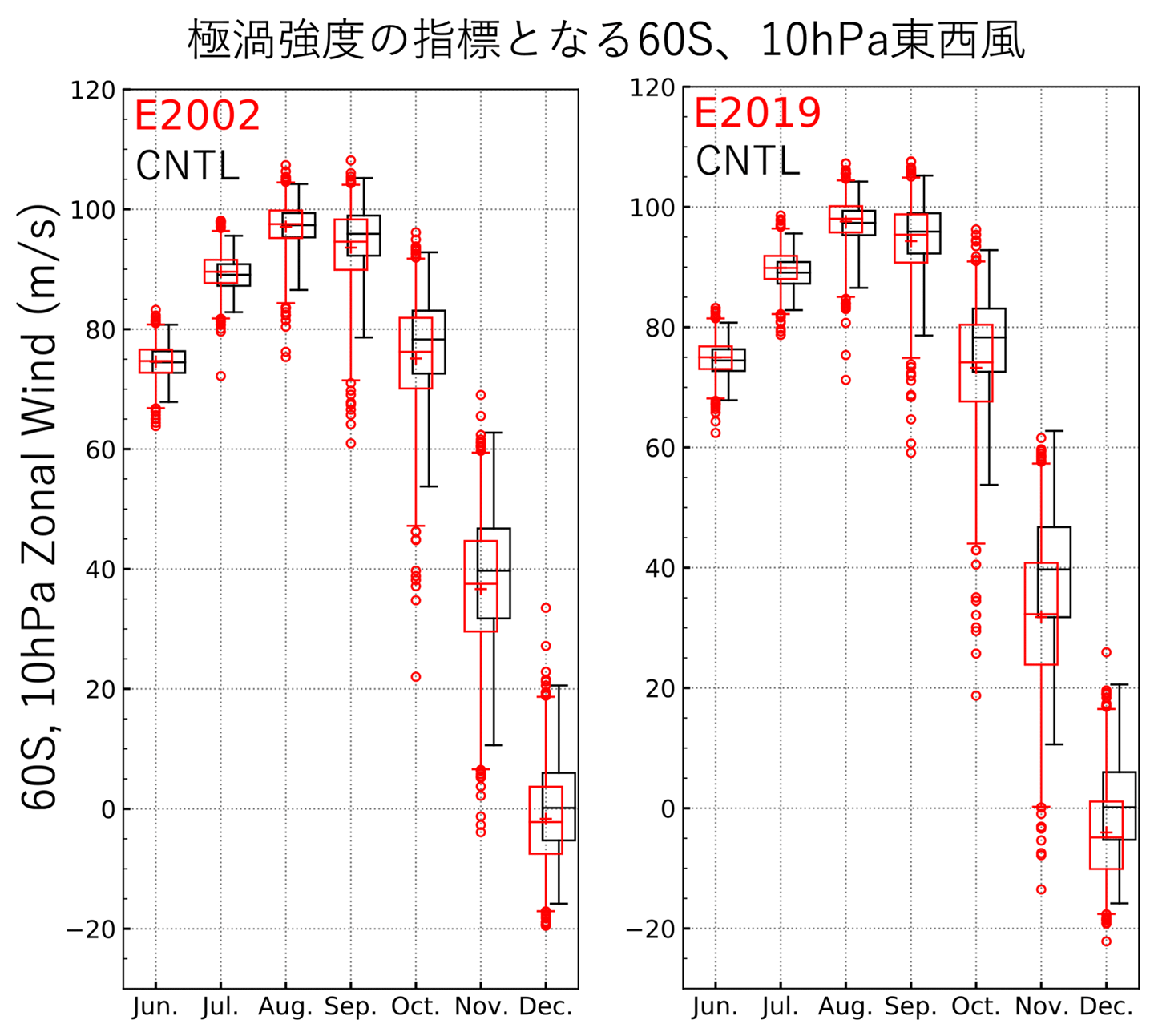
SSWには極渦が成層圏中緯度の高気圧に取って代わられる変化をする偏移型、極渦が東西波数2に分裂する分裂型の2種類があり、それぞれ惑星スケールの東西波数1、波数2の波*3が対流圏から成層圏に伝播してくることで生じます。2002年の海面水温を与えた実験では、成層圏に伝播する東西波数2の波が、2019年実験では波数1の波が標準実験よりも顕著に増大しており、2002年のSSWが波数2型であり、2019年のSSWが波数1型であったことと整合的でした。
なお、これら大アンサンブル実験のデータのうち論文の作成に用いたものは、DOIを付与して地球環境データベース(GED)から公開しています。
https://doi.org/10.17595/20221215.001