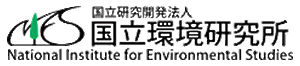計算で挑む環境研究-シミュレーションが広げる可能性【第10回】 気候モデルから化学気候モデルへ:スーパーコンピュータが可能とするオゾン層年々変動の解析
現在、コンピュータシミュレーションは環境研究を支える重要な研究方法となっています。天気予報や災害の予測など、私たちの日常生活と深く関係していることもあります。
シミュレーション研究の内容は多岐にわたり、日々進歩しています。このシリーズでは、環境研究におけるシミュレーション研究の多様性や重要性を紹介いたします。
私は、大気微量成分の化学反応や輸送などを扱うことのできる数値モデルでシミュレーションを行い、オゾン層や大気汚染、排出量推定などの研究を行ってきました。こうした大気微量成分のシミュレーションでは、大気の運動や放射などを表現する気候モデルの計算に大気微量成分の反応や輸送などの計算が加わるため、元の気候モデルの何倍もの計算コストがかかり、大規模なメモリも必要となります。本記事では、大気微量成分のシミュレーション研究のうち、この連載でまだ取り上げられたことのないオゾン層のシミュレーションを中心に関連する研究を紹介します。
1. オゾン層のシミュレーションについて
成層圏の高度約15~30 kmで大気中にオゾン(O3)が多く含まれる場所がオゾン層と呼ばれています。オゾン層は太陽からの紫外線を吸収し地球上の生命を保護する役割を果たしていますが、1980年代以降、南極域でオゾン層が薄くなって上空(宇宙)から見ると穴が開いたように見える領域(オゾンホール)が現れるようになり、人体への健康影響が懸念されるようになりました。成層圏オゾンは太陽紫外線による化学反応(光化学反応)によって酸素から生成されるため、太陽光が強い赤道域で主に生成され、成層圏で赤道域から極域に向かう大気の循環によって中高緯度域に運ばれます(図1)。
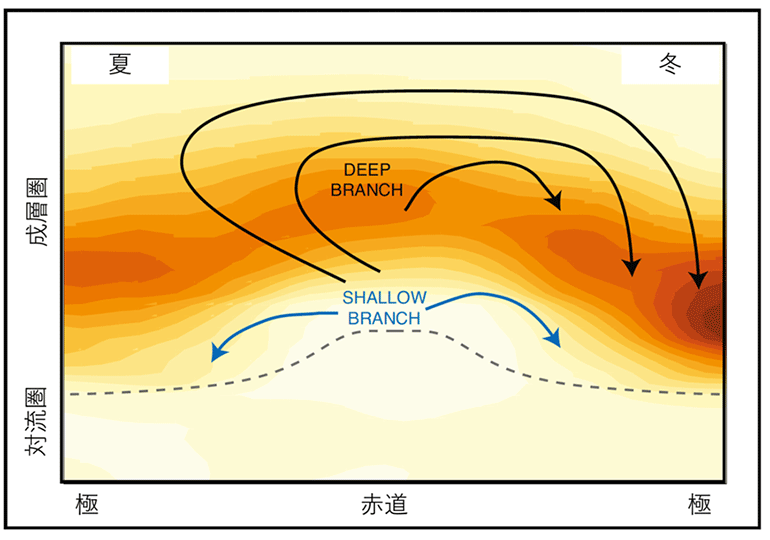
冬季の極域は一日中太陽光が当たらない極夜のため、気温が低下して極域の周辺を回る極渦という大きな低気圧が現れます。極渦を境に内外の物質の移動が抑制されるため、極渦の中でオゾン層を破壊する物質が生成されると、極渦というフラスコの中に閉じ込められたような状態になって、冬季の間に蓄積されていくことになります
冬季に極域の気温がマイナス80℃くらいまで低下すると、ガス状の水蒸気、硫酸、硝酸などが粒子化して極成層圏雲(Polar Stratospheric Cloud: PSC)と呼ばれる雲が形成されます(写真1)。このPSCは養殖真珠の母貝となるアコヤガイの内側のように虹色に輝き、見た目は綺麗な雲ですが、PSCの表面ではリザーバーと呼ばれる比較的安定な塩素・臭素化合物がオゾン層を破壊する活性な物質に変換され極渦の中に蓄積されていきます。

春になって極域に太陽光が当たるようになると、冬の間に極渦の中に蓄積された活性な物質による光化学反応が起こって極渦内のオゾン破壊反応が進み、オゾンホールの発生につながります。
このようなオゾン層のシミュレーションを行うには、ここまでの解説でご想像のようにオゾンなどの大気微量成分の反応や輸送を扱う必要があり、大気の運動や放射などを扱う従来の数値気候モデルでは不十分でした。オゾンホールの問題を受けて、こうした大気微量成分の化学反応や輸送計算が加わった化学気候モデル(chemistry climate model: CCM)の開発が各国で進みました。我が国では、気象庁気象研究所や国立環境研究所などのグループがCCMの開発を行っており、オゾン層の変動要因の解明や将来のオゾン層予測を行うための国際的なCCM相互比較プロジェクトの取り組みも行われてきました。*1
2. 春先の北極オゾン大規模破壊は事前に予測できるのか?
ここで北極域に目を向けてみます。北極域では成層圏の平均気温が南極域より高く、PSCが発生するほど低温となる期間は南極域より短いため、北極域では大規模オゾン破壊は通常起きません。しかし、北半球では南半球よりも大気中の大規模な波(東西方向に1万km以上のスケールを持った惑星波)の活動が活発で、冬季に対流圏から成層圏に伝播してきて極渦を不安定にすることがよくあります。
この波活動は、2年に一度くらいの割合で冬に活発化して、極域成層圏の気温が数日の間に数10度も上がる突然昇温現象を引き起こすことがあり、それによって極渦が壊れ、極域が低気圧ではなく高気圧になってしまいます。こうした波活動は年によって大きく異なり、活発な年には突然昇温が複数回起こり、不活発な年には極域成層圏でPSCが発生するほどの低温が継続するといったように、活発な年と不活発な年で冬季を通じた極渦の時間変化が大きく異なります。
近年では、モントリオール議定書に始まる国際的なオゾン破壊物質の生産・排出規制が成功し、オゾン層は長期的には回復の兆しが見えています。しかし、波活動が不活発になり北極域でPSCが発生するほどの低温が継続した2010〜2011年や2019〜2020年の冬季には、春先に南極のオゾン破壊量に匹敵するような大規模オゾン破壊が起きました(図2)。
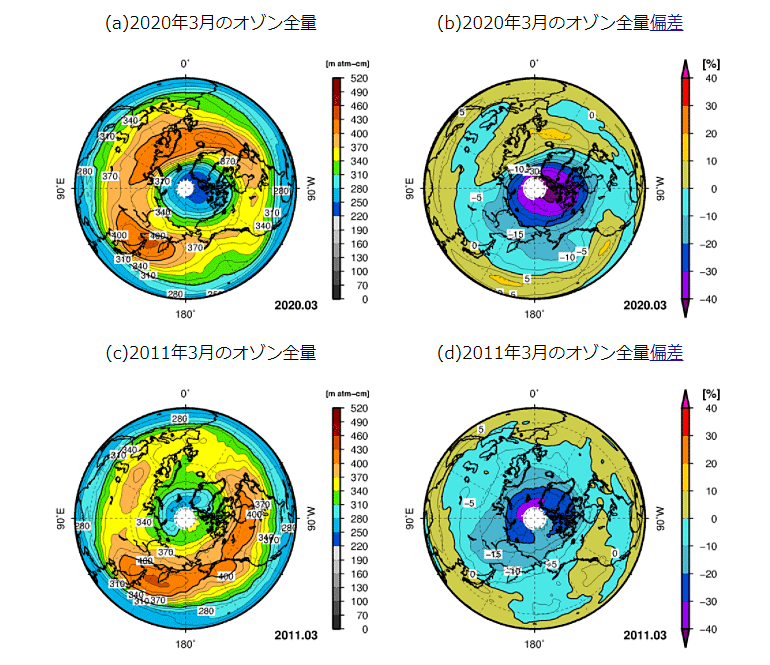
(出典:気象庁HP、https://www.data.jma.go.jp/gmd/env/ozonehp/diag_o3np.html)
オゾン全量は、地上から大気上端までのオゾンを全て地上付近に集めた場合にどれくらいの高さになるかを表す。高さはドブソン単位(DU)で、1 mmが100 DUと定義されている。ここでは、DUではなくm atm-cmと表記されている。
なお、オゾン破壊量は南極に匹敵するものの、北極のオゾン量はもともと南極より多いため、南極ほどの低オゾン域にはなりません。しかしながら、このようにオゾン層が回復していく中で、北極域では春先のオゾン層が脆弱になる年があるため、大規模オゾン破壊の要因を明らかにすることは、高緯度にも居住者がいる北半球での健康影響を軽減する上で重要な課題と考えられます。そこでオゾン層のシミュレーションに用いられてきたCCMを用いた研究に取り組みました。*2
このように、成層圏の極渦は対流圏から成層圏に伝播してくる波活動の影響を受けています。さらに、こうした波活動や平均的な極渦のひと冬の変化傾向は、それよりもゆっくりとした太陽活動の11年周期や、準2年周期振動(quasi-biennial oscillation: QBO)*3の影響を受けていることが知られています。そこで、このようなひと冬の変化よりもゆっくりとした現象を指標とすれば、春先の大規模オゾン破壊を冬に入る前に予想できるのではないかと考えました。
赤道成層圏で西風の場合を西風相、東風の場合を東風相と呼び、太陽活動を極小期と極大期に分け、これらQBOと太陽活動の指標を用いて4種類の年に分類し、春先の大規模オゾン破壊の要因を調べました。例えば先にあげた2010~2011年や2019~2020年の冬季は、QBOが西風相、太陽活動が極小期の場合に該当します。衛星観測のオゾンデータが存在している1979年から現在までを毎年調べていくと、同様にQBOが西風相、太陽活動が極小期となる年には、必ず大規模オゾン破壊が発生するというほど明確ではないものの、ひと冬を通して極渦が強く春先のオゾン量が少ない傾向にあることがわかりました(図3)。
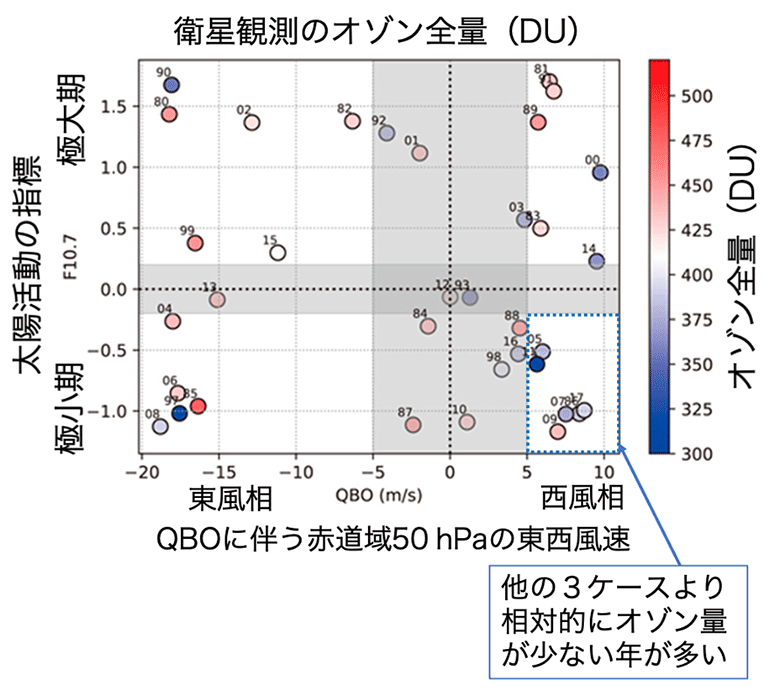
このように春先のオゾン量が少なくなった要因をどのように調べたらよいでしょうか。オゾンの反応と輸送を計算できるCCMを用いると、オゾンが大気中の風によってどのように輸送されるのかをコンピュータの中の地球で再現することができます。さらに、大気中で化学反応を起こさないオゾンが存在するという仮想的な条件の下でもオゾンの輸送を計算することが可能で、化学反応が計算されているオゾンと比較することで、化学反応と輸送によるオゾン量の変化を区別できます。
その結果、輸送による変化が化学反応による変化を大きく上回り、春先の3月における化学反応による変化は全体の1~2割程度であることが明らかになりました。これらの事例のうち、先にあげた大規模オゾン破壊が起こった2010~2011年を詳しく調べると、冬季を通じて極渦が安定し極域の気温が低下していたため、化学反応による変化が全体の2~3割程度と大きな割合を占めていたことがわかりました。このように、数値モデルの中の地球では、実際の地球では行うことのできない実験を行うことができ、観測などでは得られなかった知見を得ることができるというのがシミュレーションの強みです。
3. まとめと今後の展望
本記事では、オゾン層のシミュレーションを行うモデルを用いた研究について紹介しました。QBOや太陽11年周期のようなひと冬の変化よりもゆっくりとした現象を指標として冬季~春季のオゾン変化を調べると、QBOが西風相、太陽活動が極小期の際に、主に大気中の輸送により春先のオゾン量が少ない傾向にありました。数値モデルを用いることで、春先のオゾン量が少なくなる要因を化学反応と輸送に分離することができ、輸送による変化が化学反応による変化を大きく上回ることがわかりました。将来的に多くの事例計算を行うことができれば、モデルで再現されたオゾン変動や関連する気象場をより統計的に有意に解析できるようになりメカニズム解明につながると期待されます。
本記事で紹介してきたCCMでは、大気の運動を扱うための予報変数に大気微量成分の予報変数も加わるため、大規模なメモリが必要となります。また、これら大気微量成分の反応や輸送などの計算が元の数値気候モデルの計算に加わるため、計算コストは数倍になってきます。このため大容量のメモリや計算性能の高いCPUが搭載されたスーパーコンピュータ(スパコン)の利用は必須ですが、それでも元の気候モデルよりは空間分解能を粗くせざるを得ません。
CCM相互比較プロジェクトに参加したモデルは、気候予測のモデル間相互比較CMIPに用いている気候モデルよりも水平分解能を半分程度、鉛直格子点も半分程度に少なくしています。CCM相互比較プロジェクトでは20世紀後半から21世紀までのシミュレーションを行いましたが、10年以上前のスパコン(SX-8)では半年近くかかっていた計算が、1世代前のスパコン(SX-ACE)では13日間、現在のスパコン(SX-Aurora)では9日間と飛躍的に性能が向上してきました。今後も計算機性能が向上していけば、CCMを高分解能にしていくことや初期値を変えた複数の実験(アンサンブル実験)を行うこと、より複雑で実際の地球に近いモデル(地球システムモデル)での実験なども可能になっていくものと思います。
*計算で挑む環境研究-シミュレーションが広げる可能性は地球環境研究センターウェブサイト(https://www.cger.nies.go.jp/cgernews/simulation/)にまとめて掲載しています。