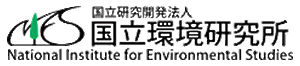成層圏からの気候・環境研究 −オゾン層変動研究プロジェクトの成果−
国立環境研究所(以下、国環研)の第3期中期計画の初年度(2011年度)に地球環境研究センター内プロジェクトとして「オゾン層変動研究プロジェクト」が立ち上げられ、その後第3期および第4期の計10年間(2011年度~2020年度)にわたり、オゾン層の変動と気候への影響に関する研究が行われた。その概要と成果について報告する。
1. 国環研におけるオゾン層研究とその背景
オゾンホールの発見後(Chubachi, 1984*1; Farman et al., 1985*2)、オゾンホール発生メカニズムの解明とあいまって世界的にオゾン層の研究が盛んになり、国環研でもオゾン層に関する研究が開始された。図1に、国環研におけるオゾン層関係の研究課題の経緯を示す。また、UNEP/WMO Scientific Assessment of Ozone Depletionのレポートの発行年も示す。このレポートは、世界のオゾン層関連研究者がオゾン層の現状やそれまでに行われたオゾン層関連研究のレビューと評価、将来展望などについてとりまとめたものである。
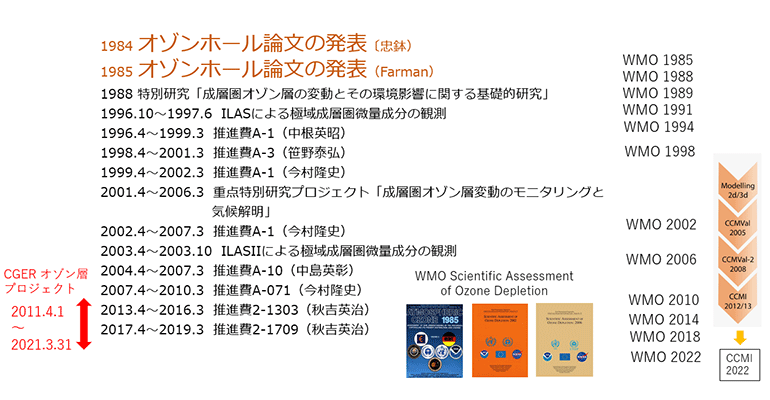
国環研におけるオゾン層研究は、ライダー(レーザーレーダ)による観測、ミリ波分光計による観測、FTIR(フーリエ変換赤外分光法)による観測、ILAS(改良型大気周縁赤外分光計)およびILAS-IIによる衛星搭載型センサーによる観測、オゾンに関わる化学反応の研究、化学気候モデルによるオゾン層変動の過去再現と将来予測等、多岐にわたった。
筆者は主に数値モデルを用いたオゾン層の長期変動の研究に携わったが、この研究においてはオゾン層に関わる化学反応を3次元モデルに導入した化学気候モデルが2000年頃から世界的に盛んに用いられるようになった。これにはオゾン層破壊問題、地球温暖化問題と計算機能力の向上が関係している。
この頃からWMO(世界気象機関)の傘下で化学気候モデルを用いた成層圏大気やオゾン層の長期変動を研究する国際プロジェクト(CCMVal, CCMVal2, CCMI, 図1を参照;Chemistry Climate Model ValidationおよびChemistry Climate Model Initiativeの略)が始まった。国環研もこのプロジェクトに参加し多くの研究成果に貢献した。
2. オゾン層変動研究プロジェクトの目的と経緯
オゾン層変動研究プロジェクトは、オゾン層問題が気候変化との関連において議論されるようになってきた中、地球環境研究センター内研究プロジェクトとして国環研の第3期中期計画の初年度(2011年)に始まった(プロジェクトの詳細は、秋吉英治「成層圏からの気候・環境研究 —オゾン層変動研究プロジェクトの紹介—」地球環境研究センターニュース2013年11月号を参照されたい)。当初のメンバーは、野沢徹さんを代表とし、筆者、中島英彰さん、杉田考史さんの4人でスタートした。翌年度の野沢さんの岡山大学への転出をきっかけに筆者が代表者となり、本プロジェクトは第4期中長期計画が終了する2021年3月まで続けられた。
プロジェクトの目的は、オゾン層破壊および地球温暖化が進む中で引き起こされる様々なオゾン層変動を、観測とモデルとの協同によって解析し明らかにすることである。当初「化学気候モデルによるオゾン層変動と対流圏気候変化の相互影響解明」と「オゾン破壊と極成層圏雲の関係の解明」の2つのサブテーマが設けられたが、これらはそのまま10年間継続された。
本プロジェクトが行われた期間は、オゾン層を保護するための国際環境条約のひとつであるモントリオール議定書(1989年発効)による世界的なフロン規制が進む中で、大気中のフロン濃度が緩やかに減少している時期にあたる(例えば、環境省令和2年度オゾン層等の監視結果に関する年次報告書の口絵図IVを参照 http://www.env.go.jp/earth/report/ozon/mat001.pdf)。一方でこの期間中、温室効果ガスである二酸化炭素は増加し続けている。フロンガス濃度が1990年台後半からゆるやかに減少し始めたことを反映して、熱帯を除く地域でオゾン全量はそれまでの減少トレンドから、全球的にわずかに増加またはトレンドがほとんどない状況に変化した(例えばWMO 2018*3, Figure3-12)。
3. 関連の研究プロジェクト
本プロジェクトは、図1に示した研究プロジェクト以外にも多くのプロジェクトと関わりながら研究が進められた。図2にそのプロジェクト名、代表者名、実施期間を示す。
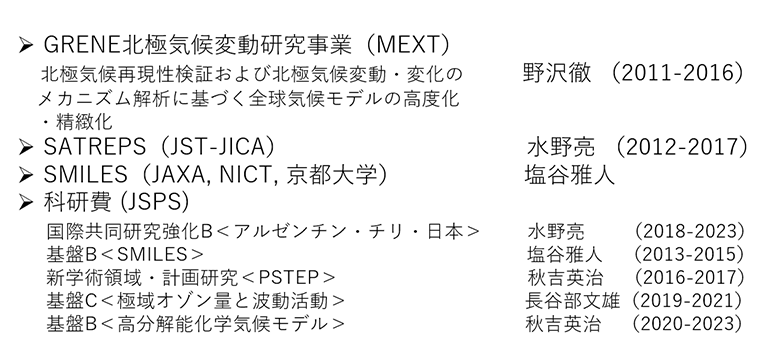
4. 成果
10年間の本プロジェクトに関連した原著論文は62編であった。以下に代表的な成果を4つほど紹介する。
(1)Dhomse et al. (2018)*4
国際プロジェクトCCMIにおける世界の20の化学気候モデルによるオゾン層の将来予測実験の解析結果である。オゾン層破壊物質(ODS)濃度が1995年頃を境に増加から減少に転じたことに応じてオゾン全量は減少傾向から増加傾向へ転じ、温室効果ガス(GHG)濃度の増加に伴って熱帯と南極以外はオゾン全量が増加する。南極域はGHG濃度への感度がほとんど見られず、熱帯はGHG濃度の増加によってオゾン全量が減少していく様子が見られる(論文のFigure 3)。
これらのシミュレーションでは、地表の境界条件としてODSやGHGのエミッション量の時空間分布を与えず、時間変化する全球一様のODSとGHG濃度を与えた。それにも関わらず計算されたオゾン全量は、そのODSやGHGへの依存性が緯度帯ごとに異なる様相を示し、過去に観測されたオゾン全量の変化や緯度帯ごとの違いをよく再現できている。オゾン量の約90%は成層圏に存在するので、成層圏大気の緯度ごとの特性がオゾン全量によく反映された結果と考えられる。
(2)Sugita et al. (2017)*5, Akiyoshi et al. (2018)*6
この2編の論文に関する研究は、SATREPSプロジェクト(地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム、図2参照)との関わりにおいて進められたものである。9月から10月のオゾンホール最盛期とオゾンホールの衰退が始まる11月頃の南米のオゾン分布の解析とシミュレーション結果である。Sugita et al. (2017) によって、国環研の化学気候モデルの南米南端付近のオゾン分布の検証を行った。この期間のモデルのオゾン全量と変動はよく再現されていたが鉛直分布に多少の正負のバイアスの入り交じった差を生じた(論文のFigure 10)。
Akiyoshi et al. (2018) では、南米南端付近で2009年11月のオゾン全量が異常に低かった原因を人工衛星搭載のオゾン監視装置(OMI)によるオゾン全量分布とERA-Interimの気象場の解析、およびこの気象場を同化した化学気候モデルによるシミュレーションから考察した。南米の西の海域の対流圏にこの時期に発生した高気圧のブロッキング現象が原因である可能性を示した。
(3)Nakajima et al. (2020)*7
2007年と2011年に中島英彰さんとJAMSTECの木名瀬健さんが南極昭和基地において行ったFTIRによるオゾン観測の結果である。昭和基地で観測された冬季~春季にかけてのオゾン濃度の変化は、ほぼ定説となりつつある極域オゾン層破壊のメカニズムと矛盾なく説明できることが示される。冬季極渦の中心領域で塩化水素(HCl)が継続して減少する原因がこれまで不明であったが、極渦周辺域から高緯度への硝酸塩素(ClONO2)と水酸化塩素(HOCl)の継続的な輸送によって引き起こされていることが初めて明らかとなった。
また、この時期にオゾンホールの場となる南極渦が変位して昭和基地の上空に位置したり外れたりすることによるオゾン量の急激な変化がみられることも化学気候モデルによるシミュレーションと合わせて明らかにした。
(4)北極オゾン量のODS・GHG濃度依存性
北極域のオゾン量はオゾンの中緯度からの輸送の影響を受けて年々変動が激しく、その激しい年々変動がこの領域のオゾンのODSやGHG濃度依存性をわかりにくくしている。この点を克服するため、24ケースのODS濃度とGHG濃度を過去あるいは将来に起こり得る値に固定し500アンサンブル実験を行い、北極域オゾン量のODS濃度およびGHG濃度依存性を調べた。
1990年代以降、北極では約10年に一度の割合で春季に大規模なオゾン破壊が起こっている(1997年、2011年、2020年)。そこで10年に一度に相当するように、500アンサンブルのうちオゾン量の多い50アンサンブルメンバーとオゾン量の少ない50アンサンブルメンバーを選んで、その特徴を解析した。
オゾン量の多い50アンサンブルメンバーを選ぶとオゾン全量のODS・GHG依存性はほとんど見られず、かつ極渦が弱く、成層圏の気温は高かった。ODS濃度の増加によってオゾン全量が220DU以下になることはなかった。
一方、オゾン量の少ない50アンサンブルメンバーを選ぶと、ODS濃度依存性が大きく、極渦が強く、気温が低かった。このメンバーではODS濃度の増加によってオゾン全量が220DU以下(オゾンホールの定義、赤実線の右側の緑色から青色の部分)が発生した(図3)。図で、横軸はODS濃度そのものではなく、ODSが分解して生じた高度50hPaにおける塩素や臭素の濃度(EESC、等価実効成層圏塩素)で表される。
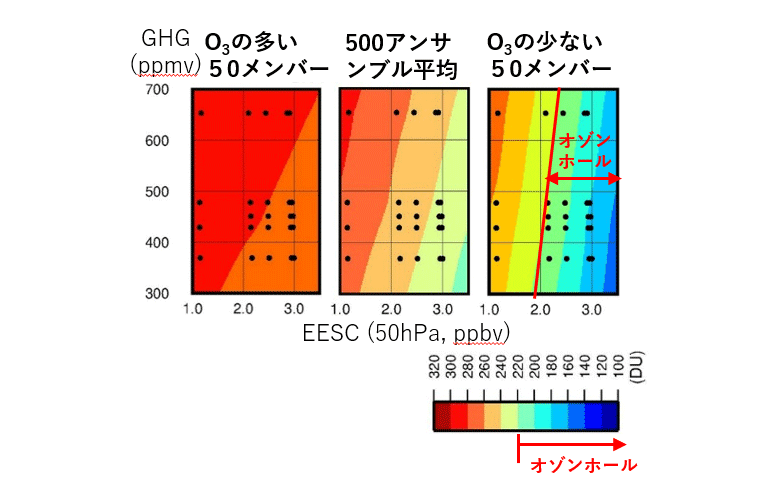
北半球中高緯度では温室効果ガスが増加すると赤道から極への成層圏の大規模な大気の流れが強まり、オゾン量が増加すると言われているが、北極大気の大きな年々変動の中で北極渦が安定した年は、ODS濃度が高ければGHG濃度に拘わらずオゾンホールに匹敵するオゾン減少が生じることをこの実験結果は示しており、南極のみならず北半球中高緯度のオゾンに対してもODS対策の重要性を示唆している。
5. オゾン層の今後
大気中のオゾン量を今後左右する因子に関しては、フロン規制によりフロン・代替フロン・ハロンの影響は相対的に減ってくるものの、これらは今後20~30年くらいの間は最重要因子であり続けるであろう。その後になると二酸化炭素の他、成層圏の水蒸気(H2O)、メタン(CH4)、亜酸化窒素(N2O)などの濃度変化の影響を受けると考えられる。モントリオール議定書キガリ改正で規制対象となったハイドロフルオロカーボン(HFC)は、化学反応によるオゾン層破壊は起こさないが、温室効果を起こしてオゾンの輸送を変える可能性があり、その排出量次第ではオゾン量に何らかの影響を及ぼすかもしれない(WMO 2018)。
また、成層圏の水蒸気や硝酸(HNO3)は、極成層圏雲(PSC)の材料となりこれらが増加すると極域下部成層圏でのオゾン層破壊を加速する。ただし、この影響は大気中の塩素濃度や臭素濃度が現在のようにオゾンホール出現以前より高い場合にのみ顕著である。
また、化学肥料の施肥などにより大気中のN2O濃度が今後増加すると、上で述べたHNO3の増加によるPSCの増加を引き起こすとともに成層圏の窒素酸化物(NOx:NOおよびNO2)の量を増加させ、NOxによるオゾン層破壊の拡大につながる可能性がある。ただし、NOxによるオゾン層破壊が効率的に進むのはオゾンがいちばん多い高度(15~25km)より少し上の高度(30km付近)なので(例えば、Brasseur and Solomon, 2005*8, Figure 6.1)、オゾン全量に対する影響はある程度限られたものになるかもしれない。
CH4の増加は水素酸化物(HOx:H、OH、HO2 )を増加させ、HOxによるオゾン層破壊を加速する一方で、CH4とClとの反応によって、あるいはNOxとHOxとの反応によって、オゾン層破壊に関わる塩素酸化物(ClOx:ClおよびClO)ならびにNOxの濃度を落とす効果もある。さらには、対流圏と同様に下部成層圏でもNOxを触媒とした光化学的なオゾン生成が進む可能性があり、大気全体としてはオゾン全量を増加させる方向に繋がると考えられる。
今後、温室効果ガス濃度が増加し気候へ影響を及ぼしていく中で、これらの微量成分濃度の変化とオゾン層の変化との関係、および気候変化とオゾン層の変化との関係を注意深く監視していく必要がある。例えば、温室効果ガスの増加とフロン対策による大気中の塩素濃度の減少とによって、将来のオゾン全量がオゾンホール出現以前のレベルよりも大幅に増加することが考えられる。その場合、紫外線量の減少や大気微量成分の濃度変化、さらには気候への影響も懸念される。