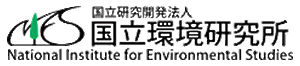最近の研究成果 地球温暖化で永久凍土の融解はどこまで進むか?
1. 永久凍土と気候変動予測
温度が二年以上連続して0°C以下になる地面のことを「永久凍土」といいます。永久凍土が存在する領域は北半球陸域の25%程度を占め、大量の有機物が凍土の中に貯蔵されています。地球温暖化によって永久凍土が融解すると、それまで凍結していた有機物が分解されて、大気中にメタンや二酸化炭素などの温室効果ガスとして放出されることが懸念されています。しかし永久凍土の融解に関わる過程についての理解が十分進んでいないことから、将来の気候変動を予測するための数値モデルでは永久凍土の取り扱いが簡略化され、大きな不確実性の要因のひとつとなっています。
2. 全球気候モデルにおける計算方法の改良
そこで私たちはまず、将来の気候変動を予測するための全球気候モデルにおいて、永久凍土融解の計算方法の改良を行いました(論文1)。高緯度域で永久凍土が存在する場所では、写真1のように、表層がコケ類やスゲ類などの植生で覆われています(横畠徳太ほか「永久凍土は地球温暖化で解けているのか?アラスカ調査レポート(現地観測編)」地球環境研究センターニュース2018年11月号参照)。つまり、永久凍土帯の地表面は、スポンジのようなコケや植物遺体の堆積によって、非常に空隙率が高く水分を多く含むことのできる厚い有機物層でカヴァーされています。
これまでの全球気候モデルでは、永久凍土域に特徴的な有機物層や、冬季に凍結する土壌水分の相変化による熱伝導率増加が考慮されていませんでした。そこで私たちは、これらの過程を計算する改良を行いました。その結果、改良された気候モデルが計算した永久凍土分布は、従来のモデルと比べてより現実的であることが分かりました。
具体的には、従来のモデルでは永久凍土域における有機物層や凍結土壌水分の熱伝導率が考慮されていなかったため、永久凍土分布の南限付近で、現実よりも地温が高くなり永久凍土が存在できない結果となっていました。新たなモデルではこの問題点が改良され、モデルで計算された永久凍土分布の南限が、より観測値に近くなりました。

3. 改良されたモデルによる将来予測
改良されたモデルを利用して将来予測を行ったところ、現在のペースで温室効果ガス排出が続くシナリオ(RCP8.5)では、2100年には永久凍土が20~50%程度(複数の予測モデル結果を用いたばらつきの幅)減少する結果となりました(図1)。将来の地球温暖化によって永久凍土面積が著しく減少する様子の動画をウェブ上で公開しています(https://ads.nipr.ac.jp/node/dagik/?type=MIROC5/PERMAFROST_SEP)。
前述のように、永久凍土の融解によって温室効果ガスが放出されることが予想されますが、将来の気候変動を予測するモデルの多くにはこの過程がまだ組み込まれていません。そこで私たちは、永久凍土の融解による温室効果ガスの放出を評価するモデルを開発し、将来予測の数値実験を行いました(論文2)。
このモデルでは、非常に氷含有量の大きい永久凍土層である「エドマ層」の融解過程も考慮しています。ツンドラ地帯で火災が起こった場所では、表層の有機物層などが失われ、永久凍土融解が急速に進むことが観測されています(横畠徳太ほか「永久凍土は地球温暖化で解けているのか?アラスカ調査レポート」地球環境研究センターニュース2017年10月号 参照)。火災跡地における、永久凍土融解にともなう地盤沈降速度の観測データなどを利用することにより、地形変化を伴うエドマ層の融解をモデルで計算しました。
一般に、有機物の分解によって、湿地などの酸素の少ない嫌気的な土壌環境ではメタンが放出され、酸素が十分にある好気的な環境では二酸化炭素が主として放出されます。こうした温室効果ガス放出過程もモデル化されています。モデル計算によると、将来にわたって温室効果ガスの排出量増加が続く RCP8.5 シナリオでは、21世紀末での二酸化炭素とメタンの放出量はそれぞれ 1130~2310億トン、12.61~28.21億トン(パラメータを変化させて計算した結果の68%幅)で、全球平均気温を0.05~0.11℃程度上昇させるものでした(図2)。
また、全球平均気温変化を産業革命前から2℃上昇程度に安定化させるRCP2.6シナリオでは、二酸化炭素とメタンの放出量と気温寄与はそれぞれ510~1020億トン、6.18~13.41億トン、0.03~0.07℃程度でした。また、RCP8.5とRCP8.5のシナリオともに、エドマ層融解の寄与は、面積割合が小さいために1%程度でした。
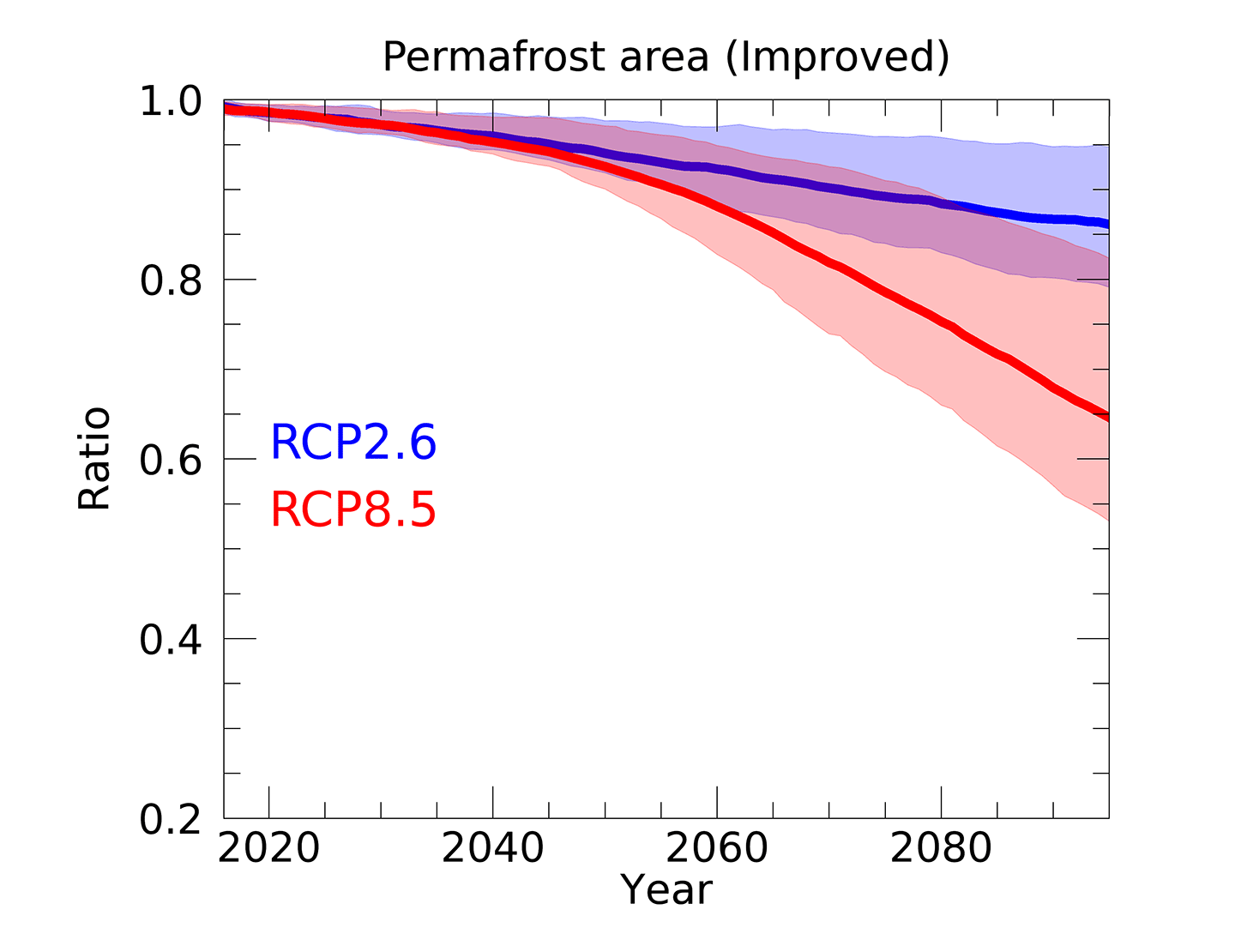
4. 長期的に影響を与えうる永久凍土の融解
私たちの計算結果によると、どのようなシナリオでも21世紀末においても永久凍土は完全には融解せずに残ることが分かりました。このため、永久凍土融解による温室効果ガス放出は、21世紀末以降も気候変化に影響を与えると考えられます。本研究のモデルの推定に基づき、永久凍土の融解による温室効果ガス放出寄与が大きいと見込まれる地域を特定することができます(図2)。
今回の研究では対策の効果などは評価していませんが、特に温室効果ガス放出の大きい地域において土地開発を抑制するなどの対策を行い、永久凍土融解による温室効果ガスの放出をできるだけ減らすことにより、地球温暖化対策への貢献ができるかもしれません。
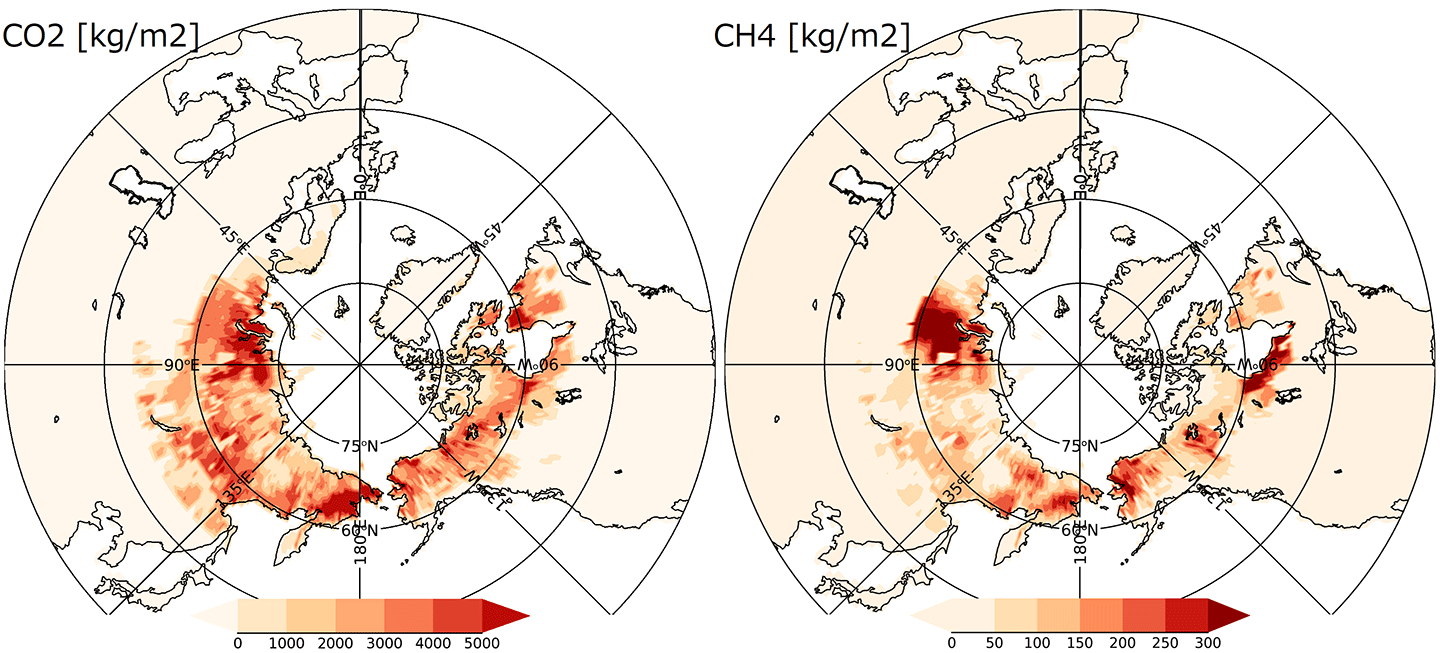
※国立環境研究所の動画チャンネルから観測の様子(【永久凍土地帯を歩く】アラスカ・バローにて)をご覧いただけます。