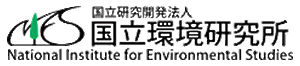自然の理に従い地球温暖化大実験を止めよう
1. 止め方も知らずに始めた人類の地球大実験
大昔に見た「ファンタジア」というアニメで、ミッキーマウスが演じた交響詩「魔法使いの弟子」の話。仕事に忙しい魔法使いに水汲みを命じられた弟子が、身代わりに箒に魔法をかけて水汲みをやらせていたが、止める呪文を知らなかったので、部屋中が水浸しになりはじめ、途方に暮れる。間一髪、魔法使いが現れ呪文で止めて、弟子は大目玉を食らう話。
もう一つは、1957年地球観測年プロジェクトのリーダーだった、スクリプス海洋研究所のロジャー・ルベル教授が温暖化について語った、「人類は地球を対象にこれまでなかった、そして二度とできない実験を始めた」という話。
どうもわれわれ人間は、「止める呪文」も知らないで、自分の唯一の住処である地球を実験材料にして「二酸化炭素を大気中に放出したら、本当に地球は温まるだろうか?」という科学的大実験をこの150年近く続けてきたようだ。確かに地球の温度は上がったし、なぜそうなるのかもわかってきたから、この実験はもう「大成功」である。
しかしこの実験を止めないままだと、地球は熱くなりすぎて生態系全体がなくなり、ロジャーが言ったように、大実験を再現したくともそれをする人類すらもいなくなる。30年かけてようやく科学が危機を宣言した今になって、止める方のまじないを学んでなかったことに気が付いて、悪戦苦闘しながら魔法使いのお帰りを待っている弟子と同じ状況になってしまった。
2. 手遅れ感のある地球危機管理
気候は生態系の生存基盤であり、気候変動問題は地球環境問題の先鋒である。これを防げなかったら生物世界もSDGs(持続可能な開発目標)も日本経済も成り立たない。1980年代から、世界はこの危機を予見し防ぐための世界システムを暗中模索でつくってきた。科学による観測・研究・評価・警告の前半工程から、UNFCCC(国連気候変動枠組条約)による国際合意、そして各国政府が明確な削減方針のもと国内アクターの行動を引っ張っていって解決する(はずの)後半工程がいま始まりつつある。地球環境研究センター(CGER)もその一員として主として科学の部分を担ってきている。この玉突きプロセスに時間がかかったことだけでなく、後半工程の準備不足が今の「気候危機」をもたらしている。
CGER発足時の1990年に発表されたIPCC第一次評価報告書では、気候変動の原因とその帰結に関する科学的根幹がすでにまとめられていて、その基本は、現在に至るまでそう大きな違いはない。しかし例えば、炭素サイクルと収支の定量化など更なる知見の取得とその科学的評価(個別知見の正しさとそれらを総合して出てくる政策に資する知見の評価)に四半世紀(1990–2015年)もかかってしまった。並行して進められた国際交渉も排出削減に歯止めがかけられず、この間に二酸化炭素排出は60%増加し、温度は約0.4°C近く(WMO:5年平均)上昇している。
これから後は誰がどうやって止めるかである。研究の方向を人間社会に振り向けなければならない。前半部分の遅れに加えて、後半工程の準備不足が足を引っ張る。ここは各国政府の出番であるが、今世紀後半の早期に2°C上昇以下に、出来たら1.5°C以下に抑え込もうというパリでの約束からもう5年たったにもかかわらず、各国提出の削減目標を足し合わせてもとても期限までにゼロ排出には到達できそうもない。原因は、200年かけて築き上げた化石エネルギー依存工業化社会の慣性を引きずって、人類生存の危機に目をつぶって進められている自国経済ファーストにある。
地球は我々なしでも生きることができるが、我々は地球の自然なしには生きることができない。「危機」は自然の理に基づき確実な温度上昇を続ける地球と、人間社会の自然に対する謙虚さに欠けたふるまいの挟間で起きている。
3. 科学が示す危機脱出の基本
遅れを取り戻すために後半工程を加速しなければならない。そのためには自然の声の代弁者たる科学の警告を真摯に受け止め、その意味をもう一度よく吟味する事から始めよう。IPCC発足から30年以上かかってしまったけれども、今、科学は確信をもって、気候変動の本質と安定化に向けて取るべき対応の基本を示している。
すなわち、①人類がGHG(温室効果ガス)を大気に排出している限り温度は上昇し続ける、果てには人間では止められなくなり灼熱地球状態に至り、生態系自体が全滅する可能性もあること。これは安定な気候あっての人類社会であること、中西宏明経団連会長がいうところの「もたない地球の上でやっている経済活動って何なのよ」(朝日新聞:6月30日朝刊、SDGsインタビュー記事)という事。
今の危機的状況をもたらした「経済と環境の両立」や、3E + S(経済・エネルギー・環境と安全のバランス)ではなく、「生存・安全・安心あっての経済」という考え方である。さらには人間社会の化石エネルギー依存経済活動による温暖化で人間自身の生存基盤を揺るがしてきたのなら、古い基盤の上でしか成り立たない従来の経済行動規範ではこの世界大転換には対応できないことは明白であり、そこに切り込まないとGHG削減はできないし、気候も変動し続けることになる。
②「人為的炭素排出をゼロにする」のが唯一の気候安定化の手段である。なぜならGHGを排出している限りその半分が大気に残り温度を上げ続ける。温暖化を止める魔法使いの呪文、科学の託宣は「炭素排出なしの社会にしなさい」の一言に尽きる。変化する気候への適応策を無限に続けるわけにはゆかない。ゼロ排出にすることはもうそうするしかない「必然」なのである。だから当面30年は、「炭素ゼロ」に脇目も振らずに邁進しよう。SDGsの17色のバッジはこれを応援する壮大な味方であるが、まず気候が安定しなければとても達成できない。
③世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2°Cあるいは1.5°C上昇以下に止めるには、今後一世代30–50年の間に炭素排出量ゼロに転換せねばならないこと。これは事の緊急性を示す。振り返ってこの30年間何ができたかを見ればその難しさが実感できよう。いつまでもまとまらない他国様子見の国際協議や目先経済第一の政府の仕切りや大口排出産業の怠慢に足を引っ張られてはたまらない。「気候危機」を憂える志あるものたちが、かまわずRE100(企業が自らの事業の使用電力を100%再エネで賄うことを目指す国際的なイニシアティブ)のように排出減が可能なことを示してゆけば、そのうち政府も国際交渉もついてくるだろう。
④ゼロエミッション転換の道筋はいくつもあり、技術的に可能であり着手が早いほどやりやすいと科学は告げる。まず政府が明確な道筋を示すのが望ましいが、いつまでも待ってはいられない。どうせいつかはやらなければならない投資であるから、そちらに確実なビジネスチャンスがある。早い者勝ちである。
①から④のように科学的知見の含意が明解なのに、なぜ脱炭素社会転換のロードマップを示すのに逡巡しているのだろうか。
京都議定書の基準年1990年から第一期最終年2012年の間、EU15カ国は12%の削減をすませており、政府の明確な長期戦略のもとで、市民もゼロ排出は当然として自分たちのやることは何かを政府と話し合っている。それに引き換え日本は、その間バブルとその後始末の大盤振る舞いでGHG排出を全く減らせなかったし、自然エネルギー技術の開発や普及にも後れを取った。この時点で20年の時間的ロス、技術開発機会のロス、経済的ロスは正直痛い。この間当然並行してやっておくべき、排出のバルブを握っている当事者に危機を早めにわかりやすく伝え、本気で削減に向かわせる働きかけが日本では不足していたのでは、との反省大である。

①温度はそれまで排出してきた総量に比例して上がる = 出している限りは上がり続ける ⇨ 人類生存の危機 = 回避するしかない。
② ⇨ 温度上昇を止めるには一切出さないことしかない。⇨ いつ止める? ⇨ 2°C上昇までに止めよう(パリ合意)。
③今から2°C上昇までどれだけ排出できる? ⇨ 1,120 Gt = 現在年間排出40 Gtの28年分しかない = 大急ぎ削減の要あり。早く削減するほど被害は少なく、止めるまでの時間稼ぎができる。
④技術的に可能なゼロ排出の道筋はいくつかある。あと延ばしするほど使える炭素が減ってしまい後での削減が困難になる。⇨ 早めの削減がやりやすい。
4. 脱炭素社会に向けて注目される有志の動き
世界的な気候変異に直面して、今では脱炭素への動きが大きなうねりになってきている。日本も後れを取り戻すべく、NGOからの様々な提案が出そろい、再生可能エネルギーの拡大を経済同友会が提唱し、資源エネルギー庁が再エネ型経済社会の検討に入った。地方自治体もRace to Zero*1で競っている。
しかし、いずれはすべての人や国がやらなくてはならない、早くやった方か楽にできるし、進む方向も分かっているのに、前世紀の慣性が強すぎて転換が進まない。もちろん全てのステークホルダーが脱炭素転換に向かって今すぐ方向を変えられるわけではない。だからといって今方向を変えないと将来世代に禍根を残す。
腰の重い政府や責任押し付け合いの国際交渉がその隘路になっているのなら、そんな危機管理システムの先に飛び出し、志を持つものが、そして力を持った産業主体や地方自治体、あるいはどうせやらねばならなくなる次世代の若者や途上国が、ボランタリーに燎原の火のように削減行動を展開し、炭素ゼロの実績を見せつけ、脱炭素社会に積み上げていってはどうか。
そういう観点から筆者が注目し、あるいは片足を突っ込んでいる、これから30年の転換を引っ張るだろういくつかの事例がある。
グリーンリカバリー:COVID-19後の経済回復が従来への回帰になれば、二酸化炭素バラマキの旧体制に戻る。その対案としての環境投資による経済復興—グリーンリカバリー—にはすでに多くの提案がある。従来の経済運営の流れに入り込み、いずれは必ずやらねばならない脱炭素化投資をここで主流化するというのは誰が考えても妥当な政策である。産業構造変化で起こる雇用摩擦の解消や格差是正も含めた「公正でスムーズな移行(Just Transition)」に向けた具体的な転換計画策定が待たれる。
2050ゼロエミッション目標:IPCC1.5°C報告(肱岡靖明「1.5°C特別報告書のポイントと報告内容が示唆するもの 気候変動の猛威に対し、国・自治体の “適応能力” 強化を」地球環境研究センターニュース2019年1月号参照)をうけて、欧州諸国はより安全な対応として、削減目標を2050年ゼロエミッションに強化した。英国気候変動委員会は、これまでのLearning by Doing(体験学習)で技術コストが下がり、2°C目標とほぼ同じ費用でこれが可能としている。1990年からすぐに削減に向かった先発組の強みである。日本にとって京都議定書期間20年のロスは大きいが、2050年ゼロエミッションに向けて挑戦する力はまだまだ持ちあわせている。
生活者の知恵とやる気を直接政治に届ける:代表制民主主義のもとで最近は、議会が利益団体代表や選挙区ファーストのポピュリズム政治家で占められ、気候危機のような長期的重要課題は論議に上りにくい。仏英は2019年、生活者が直接議会に提案できる道を開いた。
トップダウンでの炭素課税が、実行段階になって黄色いベスト運動で行き詰まったことを反省し、仏マクロン大統領は被害と削減両面からの当事者である一般市民・生活者の積極的参加の場を設営した。くじ引きでフランスの諸側面(地域、職業、年齢……)を代表するように選ばれた150人の「生活の専門家」である一般市民からなる「市民気候会合」が6週末エリゼ宮で対話合宿し、移動する、消費する、住まう、働く、食べる、制度という生活目線での149の提案を法案文案に仕立てて議会・行政に提出した。
これらの提案は3件を除きすべて、議会での論議にかけられたり、すぐできることは行政へおろされたり、重要事項は国民投票にかけられることを大統領は約束している。
ほぼ同時期に英国議会も選ばれた市民110人が連続6週末集まっての「市民気候議会」を開催し、提案を得ている。
日本も形ばかりのパブコメでの市民参加にかえて、このような熟議討論型市民参加を国やゼロカーボン宣言都市での政策決定プロセスに制度化できないだろうか。
当事者たる次世代に任せる:自分たちは逃げ切れると、見て見ぬふり本気にならない現世代は本件の諸決定からさっさと引退してもらい、後30年間確実に進行する温暖化に何とか適応しつつゼロエミッション社会転換を否応なしにやることになる当事者である次世代に実権をゆだねるのが一番有効な手ではないか。国連は来年9月Pre-COPで「Youth4Climate」を開催する。市民気候議会に倣って「若者気候議会」があっても良い。既に彼らは立ち上がっている。これまで危機管理の一翼を担ってきたと自称する筆者が、今さらこんなことをいう資格があるのかの疑問もなくはないが。
途上国との共同作業:若者と同じ境遇におかれているのは、これから発展しようとしている若い途上国である。先達もいない炭素なしの発展を自分で切り開き作ってゆかなければならない。
UNFCCCで炭素中立発展すると宣言した唯一の国である人口たった75万人のブータンは、経済成長は手段であっても目的ではないとして、国民総幸福指標からのボトムアップ視点で、水力と森林国土の自然資源に立脚する新たな炭素中立発展の道筋を模索している。いわば新たな時代のフロントランナーである。地方の文化・伝統をはぐくみ自然資源を守りつつ地域を自立させる方策は、日本の地域循環共生圏のコンセプトに近い。

途上国の脱炭素発展なしには世界は破滅する。我々は一つのボートに乗っている。援助というより共同作業・学習である。むしろ教えを乞うのは化石エネルギー文明のたたみ方に苦戦している先進国かもしれない。
立ち上がる研究者たち:そうした積極的なアクターの行動に地球環境研究者はどう協力してゆけるか。地球環境研究者の仕事は人間社会に入り込んでますます広がる。
ドイツのポツダム気候影響研究所等が科学者に呼びかけて作ろうとしている、持続可能性を意欲的に追究する科学者たちの自発的連盟Earth Leagueがある。持続可能性の視点に立って危機の本質を示し、政策担当者に政策オプションを届け、積極的な企業、自治体、広範なアクターにそれぞれにできるバルブの閉め方を提示し行動に導き、排出をゼロにするまで見届ける科学者たちの動きである。
5. 持続可能な人間社会の構築:これから10年の科学
今は経済成長牽引型ではなく、生存・生活視点から社会経済構築を考える時である。環境科学者の役目はすでに国立環境研究所憲章*2に書かれている。「今も未来も人びとが健やかに暮らせる環境を守り育むこと」を最終目標としなければならない。
また、研究と行動は自然と人間との関係の理解に基づいたものでなくてはならない。人間側からいうと、持続可能性—自然の中で生存を持続するにはどうすればよいかの追求である。
気候安定化のためには今すぐ脱炭素社会に変わらねばならないという明確な答えを科学は既に示している。この脱炭素社会転換には様々なサブシステムの組み替えが必要となり、そのためのステークホルダー間の対話を活発化する必要がある。地球環境研究者の責任は、人類生存を維持するための研究に邁進し、成果の社会的意味を抽出し、社会との接点に飛び込んで行動者にその知見をストレートに届けることである。
省エネと自然エネルギーを骨格とするゼロエミッション社会への道筋も既に明らかだ。30年前CGER市川惇信初代センター長(国立環境研究所副所長)は、地球環境時代の世界は、「自立分散ネットワーク型」になるから、それに合わせた研究スタイルにするべきとの方針を出されたが、今まさに脱炭素社会もそのようなビジョンで構築されようとしている。
しかしこのところ、日米欧ブラジルの新型コロナ対応での、科学と政治、持続可能性と経済のせめぎ合いを見るに、脱炭素社会への転換も一筋縄では行けないし、まだまだ大きな壁がありそうだ。地球環境研究者の使命は、もちろん科学的知見を深め広めるのが第一であるが、それだけに終わらず、安心安全の持続社会を実現することにある。科学と政策の間については、憲章にあるような、揺るぎない視点をもって対応してほしい。特にこれからの10年は、科学の道理をしっかり踏まえ、現場にも入り、すべての人が充足して生きられる社会を構築してほしい。
40年前に碩学近藤次郎国立公害研究所所長が目指した、まずは環境研究所へかわり、そのあとは国民の充足を探求する福禄寿研究所へ、の時代に入ってきたようである。地球温暖化大実験の店じまいがその第一歩である。