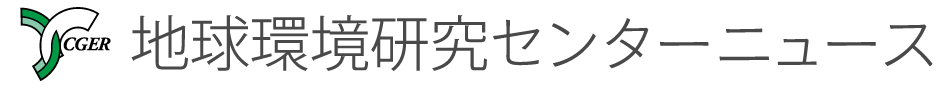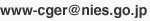2014年3月号 [Vol.24 No.12] 通巻第280号 201403_280005
第6回温暖化リスクメディアフォーラム 研究者と科学コミュニケータによるパネルディスカッション(一聴講者による報告)
1. 背景と経緯
2014年1月28日午後、コクヨ多目的ホールにおいて、第6回温暖化リスクメディアフォーラムが開催された。本フォーラムは、地球温暖化にかかわる研究者とそれを報道するメディア関係者などが集まり、2009年から年1回行われてきた。2011年度までは環境省環境研究総合推進費S-5の一環として開催されていたが、2012年度からは文部科学省気候変動リスク情報創生プログラムの一環として開催されている。今回は「温暖化予測と影響評価の一体的理解へ向けて」と題し、IPCC第5次評価報告書(以下、IPCC AR5)が公表されつつある中、地球温暖化の影響評価と気候予測に携わる研究者の連携、それを伝えるメディアや科学コミュニケータの役割について、報告及び議論がなされた。参加者は研究者とメディア関係者、科学コミュニケータなど70名程度であった。
ここでは一聴講者である筆者からみたフォーラムの様子を報告することにより、このイベントの臨場感をお伝えしたい。
2. 講演の概要
冒頭、海洋研究開発機構の河宮未知生プロジェクトマネージャーによる趣旨説明に引き続き、茨城大学の三村信男教授は、温暖化によるアジア・オセアニア域の水没域分布の予測結果などを説明し、日本における適応策は地域の課題であるため、科学者と地域コミュニティ(地方自治体など)との双方向アプローチが必要と強調した。京都大学の田中賢治准教授は、水資源統合モデルによる影響評価において、将来の水資源量と水ストレスの変化は必ずしも一致しないことを指摘し、適応策をとる際の注意を促した。名古屋大学の坪木和久教授は、台風強度とその長期変動について、特に台風の最大強度を高精度で推定する研究を進めていること、モデル実験によれば温暖化した環境では台風の最大強度が増すことが示唆されていると報告した。

会場の様子(写真提供:海洋研究開発機構)
3. パネルディスカッション
講演の後に、河宮未知生プロジェクトマネージャーをモデレータ、3名の講演者に加えて筑波大学の鬼頭昭雄主幹研究員、日本科学未来館の松岡均科学コミュニケータがパネリストとなり、ディスカッションが行われた。
(1) 台風の強度・頻度は?
冒頭、鬼頭主幹研究員は、IPCC AR5のWG1報告書によれば、台風の最大強度とそれがもたらす雨の量はともに増大することを報告した。これを受けて会場のメディア関係者から手が上がり、IPCCでは強い台風の将来の増加を『どちらかと言えば』と表現している箇所があるが、これは世界的に研究が不足しているからで、日本では台風の研究が特に進んでいて、よりはっきりしたことがいえるのではないか、との質問が投げかけられた。
鬼頭主幹研究員は、IPCCは一つの研究(例えば日本の研究)だけでは信頼度が低いと判断するが、日本の研究プログラム(文科省で2011年度まで行われた「革新プログラム」)の成果として発表するのであれば、その内容には自信があるとした。
さらに、会場から2013年のフィリピンのスーパー台風ハイエンは、たまたま起きた現象なのか、海面水温上昇などの状況により起こるべくして起きたのか、日本まで来る可能性があるのかという質問があった。
これに対して、坪木教授は、個々の現象を温暖化と一対一で関連付けて判断するのは難しいと前置きした上で、今回は海面水温が平年に比べて特に高くはなかったが、海の深層部ではかつてより高くなっており、これは温暖化の影響と考えられるとした。ただし、日本のような高緯度地域にはその海面水温とあわせても、近い将来にスーパー台風がやってくるとは考えにくいが、海面水温が今より2–3°C上昇すればその可能性は出てくるとした。
さらに、スーパー台風について、将来の発生頻度、日本への上陸の可能性が今後高まるのかと質問に対しては、将来の台風の最大強度は増大し、勢力を保ったまま上陸する可能性があるとした。
(2) 情報提供:科学者・メディアの役割は?
松岡科学コミュニケータは、アンケートによれば、信頼できる情報源として「研究者」を多くの方があげていることを紹介した。地球温暖化の影響等について科学館の現場で一般の人の声を直接聞いている担当者からは、コミュニケーションの観点から、研究者にはその情報の不確実性を示した上で説明してほしいし、メディアにはその情報にわからないことがどの程度含まれているのかを示した上で伝えてほしいとのコメントがあった。
また、日本科学未来館の中で行われた15人の非専門家と科学コミュニケータとのミニトークの中で明らかになったこととして、例えば、「温暖化を疑う人は誰の発言も信じない」傾向があることが紹介された。河宮マネージャーから、そのような人は懐疑論主張者の言うことも信じないのかとの質問があり、どっちを信じて良いかわからないから信じないようだとの回答があった。そして、個人の判断には価値観が含まれるので、コミュニケータは研究者からの情報をバイアスなしに伝えて、判断はその人に任せるべきとした。
三村教授は、現実に起きている異常気象が、自然現象なのか温暖化のせいなのかはっきりさせてくれと迫られる傾向があるが、自然の複雑な変動に人間が起こした温暖化が上乗せされているような状況については、人が生きている短いタイムスケールでははっきりとした結論が出にくいと説明しているとした。そのうえで、個々の現象について温暖化の寄与がどれくらいあるかは言えなくても、そういう現象が起きる総体(例えば個々の台風ではなく、台風一般)について、温暖化の寄与がどれくらい含まれているかぐらいは言えるように科学はチャレンジすべきとも語った。
会場の研究者から、最近、創生プログラムの中では特定の異常気象について、どのくらい温暖化の影響があるかを説明可能な研究成果が出てきているが、不確実性が高い問題であるため、数値が独り歩きしないように前提条件や背景などを含めて伝える注意が必要であるとの説明があった。
鬼頭主幹研究員は、IPCCのAR5で評価したモデルのすべてが個々の積乱雲を評価できていないなど、シミュレーションは完全ではないし、信頼度には限界があるが、それでも言えることはあると述べた。
会場の参加者(研究者)から、マスメディアに対しては例えば10秒でコメントをしなければならない場合があるので、シミュレーションの信頼度などの情報をそこに含めることは不可能であり、ネット上や書籍などで階層的に詳しい情報を用意するなどの工夫が必要であるとの意見があった。
(3) 洪水の可能性・影響は?
会場からの「2011年のタイのような洪水は日本でも起こり得るのか?」との問いに対して、三村教授は、日本とタイとでは地形が異なり、タイと同じような洪水は日本では起こらないとしたうえで、2011年に紀伊半島で起きた4日間で2,000ミリもの降雨による土砂崩れのようなことは、昔はなかったと思われるが、今後も起きる可能性があると述べた。
田中准教授は、2013年、京都市嵐山で洪水が起こったが、状況次第では宇治市一帯が浸水する可能性もあったとコメントした。
これに関連して、会場から、災害への対処方法がわからないと拒否反応が起こりやすいので、受け止め方も合わせて伝えてもらえるとよいとの意見があった。
閉会の挨拶として、国立環境研究所の住理事長が、通常の会話でも情報は正確には伝わらないことが多く、説明者はそれを認識する必要がある。昔は情報の絶対量が少なく、情報を吟味する時間もあったが、現在はあまたの情報があふれ、考える時間も不足している。ツイッターのような短い情報くらいしか、伝達されないのかもしれない。サイエンスには、それを検証できる透明性が必要である。再現に必要な情報が膨大であってもWEBを情報源とすれば不可能ではない。一方、人間は不確実な状況でも判断しなければならないときがある。しかし、1,000年に一度起きるとわかっていても、それにどこまで備えるべきか結論は出にくいと締めくくった。
4. 最後に
筆者は前世期、中央省庁の職員(官僚)であった。このフォーラムを聴いていて、感じたことを少し述べさせていただきたい。前世期までは、マスメディアで解説をする者は、その問題を管轄する省庁の官僚が多かったように思う。官僚は、担当業務について予算獲得・利害調整・ルール作りなど、他者に説明して理解を得る仕事が多いので、解説は得意なはずであるが、立場上慎重な物言いをするのでわかりにくいこともある。昨今、一部の官僚の不祥事から生じた不信感からか、マスメディアは解説者を官僚から専門家(研究者)にシフトさせている。その結果、研究者の解説・コミュニケーション能力に注目が集まってきた。しかし、研究者(専門家)が使う日本語だけでは、非専門家を理解させられないことも多い。その典型が、先の福島第一原子力発電所事故の解説である。あの事故が起きた時、科学者たちがマスメディアに登場して慣れない解説を試みたが、短時間でわかりやすく解説できた科学者はほとんどいなかった。これは、原子力に関する教育が、物理や化学の教科書の末尾におかれ、教育水準が高い日本人にさえも十分浸透していなかったせいもあると思われる。ちょうど世界・日本の近現代史の授業が日本の中学・高校では後回しになり、被教育者の理解が十分でないことと似ている。
これからの科学コミュニケーションで説明者が理解すべきは、「共有可能な言葉・多くの人が理解できるたとえ話」ではないかと思われる。コミュニケータが学校教科書に精通していたら、何を共通の知識として語るべきかがわかるはずである。現在「環境」という科目は日本にないが、「理科」「数学」「社会」「物理」「化学」「生物」「地学」など現存する科目と結びつけて説明することが重要ではないかと感じた。例えば、植物の光合成は現在でも小学校高学年時に勉強している(年配の方でも炭酸同化作用といえば通じる)が、地球温暖化と光合成が深くかかわることを知っている人は少ないし、二酸化炭素の年間濃度が光合成により大きく変動することを知る人はもっと少ない。しかし、適切な言葉で説明すれば、これらはほとんどの人が理解できる。
英語を学ぶときに辞書が必要であるが、自然科学をベースに環境問題を理解するときの辞書は通常は高校までの教科書であろう。科学コミュニケータ、そして研究者は市民に説明する際にこの点も考慮しておかなければならないだろう。