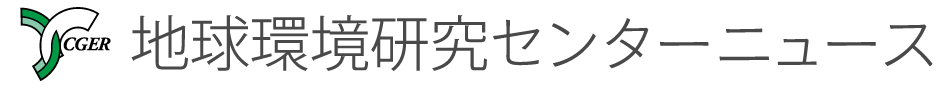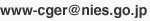2013年1月号 [Vol.23 No.10] 通巻第266号 201301_266001
2013年以降の対策・施策に関する報告書 2 「まっとう」になった温暖化防止シナリオ:福島原発事故からの再出発
1. 10年先延ばしになった温室効果ガス削減
福島原子力発電所事故は日本の温室効果ガス削減計画に大きな影響を与えた。実質的な影響は、脱原発依存社会路線によって、2012年9月14日内閣府でまとめた革新的エネルギー・環境戦略からは、今後数十年間の温室効果ガス排出が1990年比2020年5–9%、2030年23–25%削減の見通しが示されて、2010年に作られた従来計画2020年25%削減の目標に対して、温暖化政策は10年遅れることになった。世間の関心も原発問題に集中し、温暖化対策どころではないという雰囲気に埋没された状況にある。これらのことは当面、温暖化政策の大きな後退である。
しかし長期に見たときの評価も果たしてそうであろうか。例えば大災害を目の当たりにして、人間の力ではどうしようもない自然の大きな力に対する畏敬の念が国民の意識に深く刻みこまれたし、技術社会の中で生きることから起こるリスクとの共存について考え込んだ人も多い。取り戻しのできない状況を引き起こさないための予防的対応の重要性は、長期には気候変動への予防的対応とも共通する。福島原発事故の後に始まった論議を通じて、国民のエネルギー問題に関する知識(リテラシー)は向上し、エネルギーを供給側に任せていた姿勢から、自分たちの問題として考えるようになった。その結果、供給逼迫のおそれからやむをえず実施された節電要請に国民は積極的に対応し、懸念されたリバウンド(ゆり戻し効果)もなく、2年間続けての節電、節エネルギーに成功した。温室効果ガス削減計画策定の面から見ても、これらを奇貨として「まっとうな」計画づくりができやすい状況が整えられたのではなかろうか。
2. 原子力の呪縛から解放
それではこれまでの計画が「まっとう」でなかったのか、と問われると、計画づくりにさまざまな形で参画してきた身としては忸怩たるところがある。人のせいにはできないが、今になってみると、国の計画があまりにも全体整合性に固執し、行政の無瑕疵を標榜するがゆえに、もしできなかったらどうするのかのリスク概念をいっさい排除した、硬直的なものになってしまうこと、政治的な立場からの短期的視野に対応するあまり、長期のことが後送りにされる傾向におちいりやすいことが、今回明らかになったといえる。いま、硬直性の重要要因の一つであった原子力路線の縛りがなくなってみると、温暖化政策が如何にひ弱な基盤や前提に立っているのかが明らかになった。そういう意味で、革新的エネルギー・環境戦略を形作る温室効果ガス削減シナリオ案は素っ裸の赤子の状態であるが、呪縛が解かれた今からは温暖化防止についてフリーハンドで「まっとうな」案を練ることが可能になった。
3. 温室効果ガス削減政策形成への原子力リスクの認識
第一に、これによって、足元をきっちり固めた計画が可能となった。早い話、原子力ができなかったらどうするかという不安からの開放である。多分2020年5–9%削減は、やれるし、また必ずやらねばならない最低の数字として発射台が設定されたといってよい。後はどれだけこれに上乗せするか努力をどうするのかを考えることになる。これまではエネルギー計画側から示された、どちらかというと原子力に過大に頼った計画で、不安を抱えながらの計画であった。
前世紀から何回もつくられた長期原子力発電所増設計画をその後の実績と比較するとかなりの乖離がある。長期エネルギー需給見通しなどにおける原子力発電量の見通しで示された2010年の数字は、1990年代見通しでは700万kW超、2001年見通しでは約600万kWとされてきた。しかしその間立地困難性が増し、1990年末から増設のペースが落ちて、2010年における設備容量実績は約500万kWに過ぎない。2010年のエネルギー基本計画ではまだこの楽観的増設計画づくりを引きずり、2020年までに9基、2030年までに14基の計画策定となっていた。福島原発事故前に中央環境審議会でなされた「温暖化防止ロードマップ小委員会報告」は、国の政策の整合性の観点からエネルギー基本計画から与えられたこの原子力増設計画を丸呑みしたものであった。その結果、2020年の排出量は、政策を強めれば25%の削減もありうるという結果を示していた。
しかしこのときにも、温暖化対策計画自体のリスク分析という観点から、原子力発電所増設可能性の不確実さによる二酸化炭素排出政策への影響分析が行われており、もし予定がくるって原発一基がたたないとしたら、1990年二酸化炭素排出量比で0.5%の排出増となるという分析がなされていた。現在はすでにもう50基に近い原発が停止しているのであるから、概略的に見て50 × 0.5% = 25%の排出増になっているという計算になる。
4. 解き放たれた太陽のめぐみ
第二に、原子力以外のエネルギーにアプローチする自由を得たことである。
原子力に依存する計画であるがゆえに、再生可能エネルギーはこれまで疎外されていたという傾向は否定しがたい。今、長期的・世界的観点から見て、あらゆるエネルギー資源に対しての可能性を追求すべきときにある。再生可能エネルギーは日本ではなりたたないという見解もいまだちらほらいわれているが、世界で論議している科学者の示すところでは、自然エネルギーを総動員すれば産業革命以前からの温度上昇を2度以下に抑えることは十分に可能であって、できないのは、あれはダメこれはダメと最初から決め付けて、やらない理由を百も並びたてる声への過度の配慮が世界的にもあるためらしい。今回、政策として再生可能エネルギー等の普及に総動員するということになったが、ともかくやってみなければならないことがなおざりにされていたことから、脱却できるというのが一つの前進である。
5. 需要あっての供給:節エネルギーが主役へ
第三に、需要あっての供給という当たり前のことが、日本のエネルギーの世界にも入り込んできたことである。これまでは温暖化対策も供給側での解決にかなり多くを頼っていた。今回、電力コストの再計算や電力融通の硬直性解明などを通じて、エネルギーシステムに関連した国民の知識が高まった。その結果、そうなんだ、節エネすれば原子力に依存しなくともやっていけるのだという需要側の意識が強まり、夏の節電の成功で自信も強まった。ここであえて「節エネ」といっているのは、これまでの「省エネ」が機器や自動車のエネルギー効率を言っていることが多く、エネルギー需要の絶対値削減とは違う意味で使われていることから、あえて絶対値での削減について「節エネ」と言葉を変えている。
固定価格買取制度(FIT)が発足し、これまでの需要側が再生可能エネルギーを用いて供給側になったりして、需給一体になった節エネルギー活動への兆しも見え始めた。節エネルギーはエネルギーの安定供給の面からいっても最大の力になりうるし、当然温暖化防止にも役立つ。先進国は一斉に節エネ戦略を打ち出しており、筆者が事務局長をつとめる低炭素社会研究国際ネットワークの年次会合でも、2012年の中心課題となった。電力を売れば売るほど儲かる今の電力料金システムでは、供給側に節電意識が働かない可能性があるが、エネルギーを安価に且つ安定にそしてできる限り少なくて済むように供給を考えるという「用役 = Utility」会社に立ち戻ってもらい、需要あっての供給という基本に戻ったエネルギー計画にしたい。
6. 変革が生むグリーン経済
第四に、さまざまの矛盾の解決が、新たな経済の原動力になってきた。
今回特にエネルギー回りに多くの解決すべき問題が生じてきて、その変革への投資が新しい経済の原動力になる可能性が示された。2012年環境基本計画で設定された2050年までに温室効果ガス80%の削減に向けては、その削減の40%は節エネルギーによってであり、残りの40%が供給側の技術導入である。節エネルギーは単に家電製品の省エネ効率をあげることだけではなく、エネルギーが少なくても健康に暮らせる快適な高断熱住宅、高齢者が安心して買い物を楽しめるコンパクトな街づくりなど、社会システムの変更までを考えねばならない、とすればこれはインフラを含む大きな新たな社会基盤づくりの開始である。
「原子力ひとすじ」での供給側での温室効果ガス削減ではなく、需要側である社会基盤の変革を新たな国づくりの目標にしたグリーン経済への道が今回開けたのではなかろうか。
2012年6月に一旦まとめられた中央環境審議会「2013年以降の対策・施策に関する報告書」のなかでは、経済成長率や素材生産量を固定したワンセットのマクロフレームを前提としたシナリオだけではなく、2050年の産業構造を研究開発型から分かち合い型社会にまでさまざまに変えたときの削減可能性にも言及している。これからは国民の議論に耐えうる幅広な議論の材料を提供するという、専門家の使命を再認識するときである。