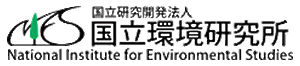観測現場発 季節のたより[33] 「フィリピンTCCONプロジェクト」ドキュメンタリーがYouTubeでご覧頂けます!
衛星観測で取得したデータを科学研究や政策決定への知見として利用するためには、衛星観測データを他の手法で取得したより高精度なデータと比較してバイアスやバラツキを評価(検証といいます)する必要があります。日本の温室効果ガス観測技術衛星GOSATシリーズや欧米等の温室効果ガス観測衛星の検証では、大気中の温室効果ガスの吸収を受けた太陽直達光を観測する、地上設置の高分解能フーリエ変換分光計で取得した温室効果ガス気柱量データが、検証標準となっています。この地上に設置された高分解能フーリエ変換分光計による観測は、現在全球で28ヵ所運用が行われており、全量炭素カラム観測ネットワーク(TCCON)という全球観測網を形成しています。TCCONについては、「長期観測を支える主人公—測器と観測法の紹介— [9] 空を見上げて温室効果ガス濃度を測る組織—TCCON—」地球環境研究センターニュース2015年3月号を参照ください。
国立環境研究所では、茨城県つくば市の当所地球温暖化研究棟「大気微量成分スペクトル観測室」、北海道足寄郡陸別町の陸別宇宙地球科学館(銀河の森天文台)内の「NIES陸別成層圏総合観測室」、フィリピン共和国ルソン島北部のBurgosの3カ所において、TCCONとしての観測を行っています。
そしてこの度、「フィリピンTCCONプロジェクト」ドキュメンタリーが作成されました。BurgosにおけるTCCON観測地点の選定、観測機器の設置、組み立てと調整、観測開始までの様子が、地球温暖化による気候変動の顕在化、温室効果ガスの衛星と地上による観測の重要性についてのメッセージとともに映し出されています。このドキュメンタリーはいくつかの映画祭への応募を経て、現在YouTubeで公開されています。
温室効果ガスの観測や研究に取り組む過程や現場の様子などがよくわかる動画となっております。ぜひご覧ください。
Web address: https://www.youtube.com/watch?v=SktFEEwrt7A
タイトル:TCCON Philippines: A Small Nation Rises Up To The Challenge of Climate Change | Full Documentary (TCCONフィリピン: 小さな国が気候変動に立ち向かう|ドキュメンタリー完全版・全編英語)
時間:59分38秒