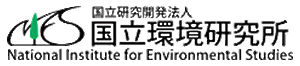最新の研究成果 将来の気候変動を決める炭素循環:複雑なモデルと簡易なモデルの予測の違い
人間活動による温室効果ガスの排出などによって、産業革命前と比べて地球全体で1℃程度の気温上昇が生じています。このまま温室効果ガスの排出が続けば、今後もさらに気温上昇が続くと予想されます。将来の気候変動を左右する重要な過程が「炭素循環」です。人間が排出した二酸化炭素は、陸域や海洋で吸収され、残りが大気に蓄積するように「循環」することで、気候変動の大きさが決まるためです。
地球の炭素循環を調べるために、様々なモデルが利用されます。最も複雑なモデルが、最先端の「地球システムモデル」です。地球システムモデルでは、陸域と海洋での生態系による二酸化炭素の正味吸収量(植物による光合成や海洋への二酸化炭素の溶解)と、大気中の温室効果ガス濃度の変化によって生じる気候の変化を、地球全体で3次元的に詳細に計算します。地球システムモデルによる計算には、スーパーコンピュータなど大規模な計算資源が必要です。
一方、「簡易気候モデル」は、生態系による二酸化炭素の正味吸収量や、それによって生じる気候の変化を簡易な方法(複雑な過程を簡単な式で置き換え、地球の広い領域を平均的に表現する)で計算するモデルです。簡易気候モデルは「気候エミュレーター」とも呼ばれ、大規模な計算資源を必要としないため、より幅広く様々なケースを想定した分析に向いています。しかし、簡易気候モデルを利用するためには、複雑な地球システムモデルとの整合性を保つことが重要となります。そこで本研究では、過去から将来にわたる気候変動のもとで、地球システムモデルと簡易気候モデルによって推定された炭素循環の詳細な比較を行い、今後のモデル開発のための提言を行いました。
図1に、地球システムモデルと簡易気候モデルによって計算された地表気温の変化と海洋・陸域における炭素の正味吸収量の積算値(過去からその時点までの総和)を示します。ここでは共通社会経済経路(Shared Socio-economic Pathways: SSP)と呼ばれる将来のシナリオのうち、代表的な3つの経路のもとでの結果を示しています。図1から、過去と将来の気候変動において、地球システムモデルに比べて簡易気候モデルは 1) 気温上昇が小さく、2) 海洋による炭素吸収が大きく、3) 陸域での炭素吸収量も大きいことが分かりました。
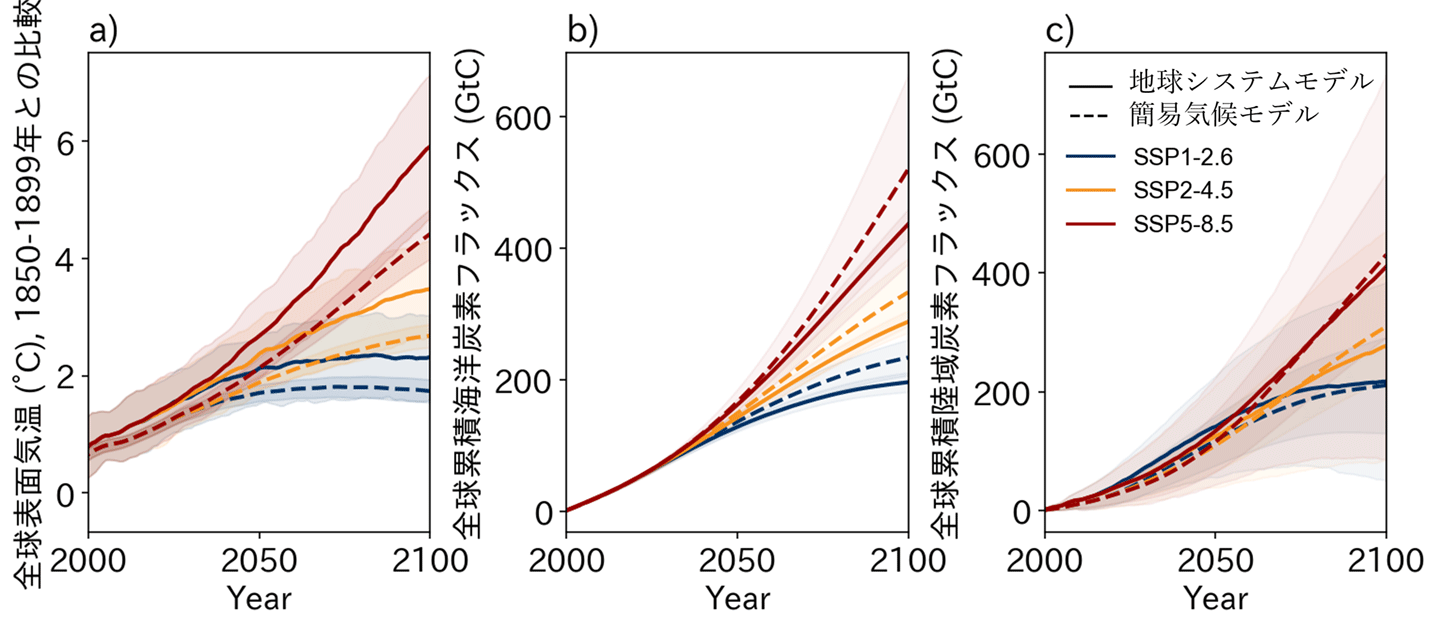
図2は、陸域と海洋の正味炭素吸収量を、将来の二酸化炭素濃度変化と気温変化に対して示しています。これにより、二酸化炭素濃度や気温の変化に対する生態系の振る舞いを理解することができます。図1および図2の結果から、地球システムモデルと簡易気候モデルの挙動が異なる原因として、次のような結論を得ることができました。
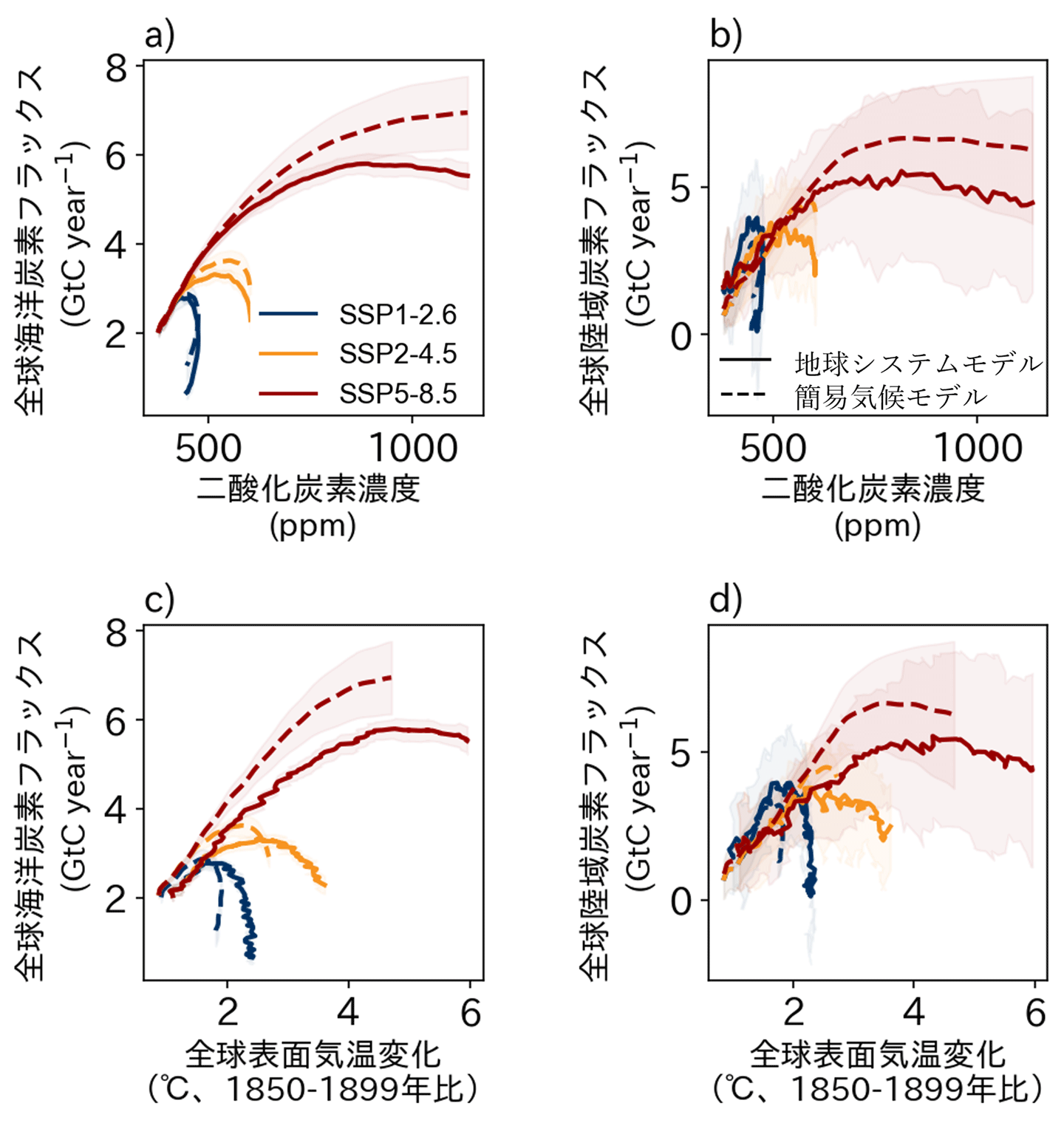
一般に簡易気候モデルは、過去の観測結果と一致するようにモデル定数などが調整されていますが、二酸化炭素排出量が多いシナリオや、二酸化炭素排出量が増加した後に減少するような複雑なシナリオでは、簡易気候モデルの挙動が現実から離れる可能性があります。例えば図2に示すように、特に二酸化炭素濃度が高いシナリオにおいて、地球システムモデルよりも簡易気候モデルは二酸化炭素吸収量が大きくなる傾向があります。これは、簡易気候モデルでは、二酸化炭素濃度が高いときに栄養塩が制限され、高温によって植物が炭素を取り込む能力が低下することを考慮していないためと考えられています。同様に図2に示すように、地球システムモデルに比べて簡易気候モデルでは、二酸化炭素が海洋表層から深海へ移動するスピードが速すぎることにより、海洋における炭素吸収量が大きくなっています。このことは、二酸化炭素濃度が21世紀の後半に減少する「持続可能シナリオ(SSP1-2.6)」において、二酸化炭素濃度減少に対する海洋炭素フラックスの反応が遅いことからもわかります。
このような分析から、簡易気候モデルを開発する際に次のような点が重要であることを私たちは主張しています。第一に、二酸化炭素排出量が多いシナリオなど、より幅広いシナリオにおける地球システムモデルの結果を用いて、簡易気候モデルの調整を行うことが重要です。また、簡易気候モデルにおいて、海洋表層から深層への二酸化炭素の移動を現実的に表現するために、地球システムモデルの結果を参照することが重要です。そして最後に、地球システムモデルと簡易気候モデルによって過去の炭素循環を精度良く再現することが、将来予測の信頼性を向上させることにつながります。