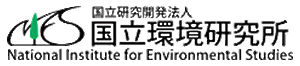地球環境研究センター30周年企画 時の証言者たちに聴く(1):京都議定書が拓いた地球温暖化対策への世界的な取り組み
地球環境研究センターは2020年10月で設立30周年を迎えます。このインタビューや対談では、地球環境研究センターが誕生した1990年から現在に至るまでの地球環境研究の国内外の動向やさまざまな研究活動を振り返り、それらに直接深くかかわられた方々からご経験や考えをうかがい、今後の30年を展望していくことを目的にしています。
初回は、浜中裕徳氏(地球環境戦略研究機関(IGES)特別研究顧問、元環境省地球環境審議官)に、地球サミット、気候変動枠組条約、京都議定書をめぐる国際交渉など、1990年代を中心に、地球環境研究センター長の三枝信子がお話を聞きました。
公害問題を担当して得たもの
三枝:浜中さんは1969年厚生省に入省され、公害問題に着手されました。そのご経験についてお話ししていただけますか。
浜中:まず、地球環境研究センターが設立30周年という節目の年を迎えたことをお祝い申し上げます。
1967年に公害対策基本法が制定され、私が厚生省に入省した1969年はその実施段階に入った頃でした。私が最初に担当したのは、イタイイタイ病と同じ原因であるカドミウムの環境汚染による地域住民の健康調査でした。仕事はデスクワーク中心でしたが、実際に公害問題の現場に調査に行かせていただき、得難い経験をしました。たとえば、大阪市西淀川区など大気汚染が進行していた地域の調査、工業開発計画があった仙台市近郊地域で大気汚染予防のための気象条件の調査などです。
1971年に設立された環境庁(当時)に異動してからは、大気汚染の環境基準の設定を行いました。
窒素酸化物については、当時科学的知見が限られていた中で動物実験データを重視し、予防的観点から厳しい基準を作成したところ、産業界から基準の科学的根拠に対し批判があり、基準の達成に必要な対策はなかなか進みませんでした。
その後、新たな科学的知見が得られ、それ程安全を見込まなくても健康を保護する上で支障がないことが明らかになったことから、故橋本道夫先生(厚生省初代公害課長や環境庁大気保全局長を務めるなど、ミスター公害と呼ばれた)が基準値を見直し新しい基準を作られました。そして、専門家の検討結果に基づき、技術の進歩に見合った規制の強化を進めるなど、対策は軌道に乗っていきました。
このような経験から、予防重視で厳しめの基準を作るだけでは問題は解決しない、対策を前に進めるなら、いろいろな問題を総合的に考えて対策を講じ、関係者にその実施を「覚悟」していただく必要があるということを学びました。公害問題に取り組んだ経験で得たこのような教訓は、京都議定書(以下、議定書)交渉にとても役立ちました。

国内調整と多国間交渉を同時並行で進めた京都会議
三枝:浜中さんは環境庁(当時)に異動後、1995年に企画調整局地球環境部長に就任され、気候変動枠組条約締約国会議(COP)などの国際交渉をリードされました。1997年の京都でのCOP3までの国内外の動向や、COP3での国際交渉についてお聞かせください。
浜中:1990年にできた地球環境部の初代の企画課長に就任し、私は初めて地球環境問題に取り組みました。1992年、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された環境と開発に関する国際連合会議(地球サミット)では、持続可能な開発という考え方が共有されました。同時に途上国は、地球環境問題は悪化の責任の大半を占める先進国から取り組むべきで、途上国は貧困の克服が最大の課題だと主張しました。
そして、持続可能な開発を実現するためには「共通だが差異ある責任」という原則と、先進国から途上国への資金的・技術的・人的能力向上に関する支援が必要だという認識が共有されました。気候変動枠組条約においても同様の考え方が広まり、「共通だが差異ある責任」「先進国の途上国支援」は地球環境問題の国際協議の場で繰り返し議論されるテーマとなりました。
その後私は、水質保全対策を担当する部局に異動していましたが、1995年のCOP1でベルリンマンデートが採択され、COP3までに先進国の約束を強化する議定書を作ることになりました。そして、COP1が終わった数か月後、私は地球環境部長に就任しました。1996年のCOP2でCOP3の日本開催(京都)が正式決定され、交渉が本格的になってきました。基本は多国間の交渉ですが、国内のステークホルダーとの調整と同時並行で進めなればいけないという難しさがありました。
ベルリンマンデートで合意された先進国の約束の強化について、COP2でアメリカとEUは数値目標を作ることを提案していました。数値目標については、だんだんと世界的な相場観が変わってきました。最初は「抑制または削減」と言っていたのが「削減」だけになりました。しかも、1%や2%ではなく「相当の削減」ということに変わっていったのです。さらに1990年からの削減が相場になってきました。
国内では、通産省(当時)が、どんなに頑張っても日本の排出量は1990年と同じレベルまで減らすのが精一杯で、それ以上の削減はとてもできないという見解を強く打ち出していました。私たちは、国立環境研究所の研究者と一緒に取り組んで分析した結果、5%くらいの削減は可能と主張しましたが、通産省とは平行線でまとまりませんでした。COP3の議長国となる日本が京都会議をまとめるためには、まず日本国内の調整をしなければならないということで、当時やや珍しい形でしたが、首相官邸が乗り出して調整しました。
三枝:国内調整が大変だったのですね。

浜中:調整の結果、議長国提案として、1990年から5%削減を「基準削減率」とし、各国の削減率はそれぞれの事情を考慮し差異化するという案をまとめました。1980年代の第2次オイルショックを経て企業の省エネ投資が進んでいた日本は、1990年の段階でエネルギー効率が他の先進国よりも相当高かったので、基準削減率を5%の半分の2.5%とするという提案を出しました。
しかし、国際交渉ではある国の言い分が100%通るということはまずありません。最終的に50%くらい満たせればまずまずということができます。国内で困難な調整をした日本の削減案ですが、京都会議の本番ではそのまま通らないという難しさを経験しました。
先進国の約束を強化するためには、日本、アメリカ、EUの間で意見がまとまることが議定書合意に不可欠となります。ところが、交渉の優先事項は各国それぞれ異なります。日本は国別削減率の差異化を、EUは15の加盟国(当時)全体で15%削減の厳しい目標を達成するから、アメリカも日本も同じ目標にすべきだと主張しました。これに対しEUのなかでは国ごとに違い(例えば南ヨーロッパは緩く、他方イギリスやドイツは厳しい目標など)を認めながら、他の国には一律削減を求めるEUの言い分はおかしいと指摘しました。
アメリカは最初、1990年水準からの削減は不可能と言っていましたが、本心は森林の二酸化炭素(CO2)吸収量 を、温室効果ガス排出量削減とみなして算入できる仕組みや排出権取引などを導入し、それらのルールを適切に定めれば、削減できるということでした。
合意成立の可能性が見えてきたことで、数日間徹夜で交渉しました。日本は、当初森林の吸収量をそれ程正確には測れないという理由で、議定書で考慮することに慎重でした。しかし、官邸は合意の成立と議定書の採択が最優先でしたから、交渉方針を転換し吸収量も考慮することにしました。そして、ご存知のように日本は6%、アメリカは7%、EUは8%削減となりました。
三枝:その結果、国内外でどんな動きがあったのでしょうか。
浜中:6%の削減実施に向けてさらに努力していく必要があるということが、国民的なコンセンサスになったと思います。ただ、通産省と産業界との間ではなかなか簡単にはいきませんで、森林吸収量の算入や排出権取引が認められたことで結果として国内の実質的な削減レベルは変わらないことを説明したのですが、2.5%が6%になってしまい、その違いが将来追加の削減を求められる結果になるのではという不安を残してしまいました。
京都会議の後も議定書をどう実施するかに関するルールの交渉が必要となり、その最中にアメリカは政権が変わり、2001年3月に議定書を離脱しました。日本は2001年7月のボンにおけるCOP6再開会合に向けて、議定書実施のルール作りの国際交渉とアメリカの参加を働きかけるという二兎を追わなければなりませんでした。COP6再開会合では、アメリカ抜きの議定書発効を目指すEUが、日本が必要としていた森林の吸収量を認め、議定書実施のルールに関する基本合意ができました。
その数か月後、モロッコのマラケシュで開催されたCOP7で議定書の運用ルール(マラケシュ合意)が採択されました。そして議定書は2005年に発効しました。
京都議定書の意味と残された課題
三枝:議定書は地球温暖化対策に関する考え方のコンセンサスを変えた転機だったと思います。議定書の意味と残された課題は何でしょうか。
浜中:議定書の評価と課題は対になっています。国際的な取り組み制度の関係と各国の国内での温暖化対策という二つの側面から見たいと思います。
まず、国際制度の関係です。京都議定書の後、紆余曲折を経ながらも、2015年のCOP21で気候変動に関する国際的枠組みであるパリ協定が採択され、国際制度は進展したといえるでしょう。
ここで私の問題意識は、京都議定書が採択されていなかったらパリ協定はあったのだろうかということです。私はかなり厳しかったのではないかと思っています。どうしてかというと、議定書は2005年に発効し、全面実施に移りました。そのことは、途上国に対しても大きなメッセージになったと思います。地球温暖化問題については先進国が先導すべきというスタンスだった途上国も、実際に先進国が削減を約束し、その実施に乗り出したことを見て、もはやそのようなスタンスに固執するする理由が乏しいと感じたのではないでしょうか。
議定書には、将来的に排出量が多くなっていくことが予想される中国やインドに削減義務がなく、世界第一のCO2排出国(当時)であるアメリカは離脱したという大きな課題が残りましたが、その後2007年にインドネシアのバリで開催されたCOP13で、先進国も途上国も対策を強化しなければならないということを基本的な考え方とする「バリ行動計画」が作られました。それから新たな国際枠組みの検討が進められ、最終的にすべての条約締約国に適用されるパリ協定の採択につながりました。
もう一点の国内対策については、日本もEUも、省エネ、再生可能エネルギー拡大、温暖化対策の法制度、カーボンプライシング、つまり炭素税とか排出権取引といった取り組みが進みました。日本では、京都会議の翌年、省エネ法を改正したトップランナー方式(省エネルギー基準を、現在製品化されている最も効率のよい製品以上の水準に決める方式)に基づき、自動車や家電製品の厳しい省エネ基準を設定して、省エネが大いに進みました。
しかし、せっかく議定書が採択されたのに、それに見合うような効果的で強力な政策措置の導入実施は十分ではなかったと思います。とくに不十分だったと思われるのが、カーボンプライシングです。温暖化対策税が導入されましたが、これは税率が非常に低い財源調達型のもので、本格的な炭素税や排出権取引制度は産業界の強い反対で導入できませんでした。

脱炭素社会に向けたモデルづくりに若い人もアプローチを
三枝:脱炭素社会をめざすなど、地球環境の改善に向けて、若い人たちがこれから地球環境問題に取り組もうとしているとき、大切にしてほしいことなどございましたら是非お話いただければと思います。
浜中:パリ協定のことを少しお話しします。パリ協定は議定書の次の大きな一歩として非常に重要なステップだと思います。途上国を含むすべての条約締約国が参加できる枠組みだからです。また、21世紀後半を視野に人為的な排出量と人為的な吸収量をバランスさせるという長期のゴールを明確に設定しました。そして各国は自国の貢献を提出し、パリ協定が決めた長期ゴールに向けて定期的に見直し、アップデートをするという、トップダウンとボトムアップをミックスさせた仕組みになっています。
参加の幅を広げる観点から各国が自国の削減の内容を定め、提出するというボトムアップの側面を重視しましたが、それは課題として残る点でもあります。パリ協定の実施による実際の削減効果がどのくらいで、それは協定の長期ゴールに向けて十分なのかということを今後、しっかり検証しなければなりません。もし不十分なら、パリ協定を見直すことも必要かもしれません。
もう一つ、パリ協定は気候変動問題への取り組みにおける国家以外の主体の役割を初めて明確に認めています。この問題における、産業界、金融機関・投資家、自治体、NGO、そして科学者が果たす役割は非常に大きいので、そういった主体の役割をより一層強化できるように、そして国家主体との協働が実現できるようにしていくことが重要です。そういう非国家主体の役割や各主体間の協働の実態を検証し、その課題や取り組みの方向を検討していく必要があるでしょう。
これから脱炭素化という目標に向けて関係者が認識を共有していくうえで、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の役割はますます重要になるでしょう。IPCCがこれまで公表した報告書は大きな役割を果たしてきました。第5次評価報告書(2013〜2014年公表)ではカーボンバジェット、脱炭素化などのコンセプトを示し、1.5°C特別報告書(2018年公表)では2050年までに脱炭素を実現する必要があり、そのために広範な社会・経済システムの転換と人々の行動変容が重要だと指摘しました。
今後、脱炭素化に向けて、自治体や企業、市民のライフスタイルの面でも、一つのモデル的なものを日本のなかで先導的に作り、いろいろな主体が経験を共有し、お互いに学びあうことが大事でしょう。
若い人には是非、脱炭素モデルの先導的な形成なども視野に入れて自分の得意な分野からアプローチしていただければ、これからの人類社会の取り組みの大きな力になると思います。また、実際の問題に携わりながら、さまざまな関係者と一緒に取り組んでいくことが重要です。お互いに立場は違っても学びあいながら知識や認識を深めていけば、行動をさらに進められますので、若い方々のご活躍を心から期待したいと思います。
少し話題が飛びますが、最後に少し付け加えさせてください。昨今のコロナ禍のなかで、私たちはテレワークなどオンライン通信を利用したコミュニケーションが拡がるといった新しい経験をしています。私たちの日常の暮らし方や働き方、ビジネスモデルなどを変える必要があるかもしれない、ということを考えさせられる時期のような気がしています。
コロナ危機対応と気候危機対応はレジリエントで持続可能な社会づくりといった点で共通するところがあるかもしれません。そういったことも一つのきっかけになりますので、若いみなさんには是非新しい課題にチャレンジしていただけたらと思います。
三枝:深いご経験に基づく示唆や今後に向けたエールをいただきました。本日は貴重なお時間をいたたき、ありがとうございました。