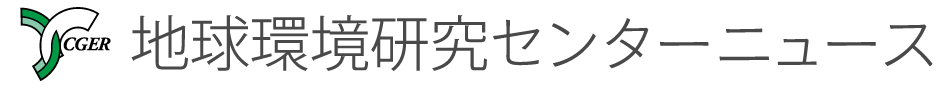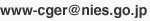2013年8月号 [Vol.24 No.5] 通巻第273号 201308_273004
人間活動と水環境問題の新時代に向けて 〜「人新世の水」会議参加報告〜
2013年5月21日から24日にかけて、ドイツのボンでGlobal Water System Project(GWSP)が主催する国際会議Water in the Anthropocene(人新世の水)が開催された。地球環境研究センターから中山・眞崎・花崎の3人が参加したので、この会議の様子を紹介する。
GWSPはIGBP、IHDP、WCRP、DIVERSITAS[1]の四つの国際的な地球環境変化研究プログラムによる共同プロジェクトで、その名の通り、水という系を通して、地球圏・生物圏、人間、気候変動、生物多様性を横断的に分析する研究を支援している。GWSPの共同議長は、水のガバナンスの研究で著名なClaudia Pahl-Wostl教授(ドイツ・オスナブリュック大学)と全球水循環モデルの研究で著名なCharles Vörösmarty教授(アメリカ・ニューヨーク市立大学)の2人である。
Anthropocene(人新世)とは、人間活動の形跡と範囲が地球規模に現れるようになった時代を示す。この言葉は約1万年前から現在までを指す地質時代区分Holocene(完新世)を捩ったもので、Eugene F. Stoermer博士とPaul Crutzen博士によって提唱された[2]。Anthropoceneを象徴するのが地球温暖化問題である。化石燃料の燃焼に伴って排出される二酸化炭素などの温室効果ガスが地球の大気組成を変え、地球の気候を変化させつつある。ここで、水循環や河川に目を向けても、やはりダム・堰の建造による流れの分断や取水・導水による流量の改変など、人間活動の影響は世界各地に顕著に現れている。こうした背景から、Anthropoceneにおける水をテーマにして、会議が開かれることになったようである。


写真(上)会場のMaritimホテル(下)全体会合の様子。学界や行政、実業で活躍する幹部クラスの参加者も多く、含蓄に富んだ質疑応答が行われた
会議は全体会合と分科会合の二つに分かれ、それぞれ1回約2時間で6回ずつ行われた。全体会合は基調講演とパネルディスカッションからなる。基調講演において、James Syvitski教授(コロラド大学)はインダス川や黄河の歴史的な開発などを題材にして、地球工学的(Geo-engineering)に世界の主要な河川が改変されていることを指摘した。Pavel Kabat教授(国際応用システム分析研究所)は、食料と水、エネルギーと温暖化、公平性と貧困の三つを軸にして、特にアジアとアフリカに着目して、水問題の分析と解決を目指すべきだと主張した。Joseph Alcamo教授(国際連合環境計画)は水循環におけるFuture Earth[3]のため、持続可能性を満たしつつ越境水問題(国境をまたぐ水系における諸問題)にも今まで以上に取り組む必要性を強調した。
最終日にはパネルディスカッションが行われた。パネリストは弁護士や企業社長などいわゆる水の専門家ではない人たちで、水に関する研究と実社会をどう結び付けるかなどについて意見が交換された。たとえば、水問題を水利権売買などの市場の活用によって解決する方法は論文において活発に議論されているものの実社会では成功事例に乏しいのはなぜか、4年程度で政権が変わる国が多い中、長期的な視点から水問題にどう取り組むべきか、などについて議論が交わされた。また地球の水資源に関する科学・ガバナンス・水管理・意思決定に携わる機関と個人への提言をまとめた「ボン水宣言」[4]が採択された。
分科会は10のテーマが並行開催された(期間全体で60テーマ)。テーマは自然の水循環から社会の水利用制度・統治まで、スケールは地球から小河川まで、幅広く研究報告がされた。地球水循環と地球温暖化に関する発表は充実していた。たとえば、全球水循環モデルを拡張することで河川水温を推定することに成功したという事例、降水量や河川流量などの水のフローではなく、ダム・ため池・帯水層・湿地など水のストックに着目して地球水資源の評価を実施するプロジェクト、世界の灌漑農地の歴史的変化を地図化するプロジェクトなどの報告が特に印象に残った。花崎と眞崎は、貯水池操作や灌漑取水など主要な人間活動を扱うことのできる全球水資源モデルH08(http://h08.nies.go.jp/h08/index_j.html)を利用して実施した、地球温暖化の影響評価の最新の結果を報告した。
水循環に加えて水質や水温という観点からの発表が増えていることも印象に残った。中山は、洪水および渇水といった極値現象に伴う水・物質循環変化が生態系機能に及ぼす影響について統合型水文生態系モデルNICEを用いて評価した研究、および、これまで地球スケールではほとんど無視されてきた陸の水域の炭素循環における重要性について発表を行った。Planetary Boundaries(地球の境界[5])の概念で有名なJohan Rockström教授(ストックホルム大学)は水循環変化に伴うTipping Point(臨界点[6])の解明の必要性を強調していたが、トップダウン—ボトムアップ間の関連性解明のためにも水循環のみならず物質循環、特に炭素・窒素循環のホットスポット特定も今後ますます重要になると予想された。
以上のように、「人新世の水」には大きな関心が寄せられ、国際的にも多くの研究が実施されている。地球環境研究センターでも引き続きこのテーマの研究を進めていく予定である。
脚注
- IGBP(International Geosphere-Biosphere Programme):地球圏—生物圏国際協同研究計画、IHDP(International Human Dimension Programme on Global Environmental Change):地球環境変化の人間的側面研究計画、WCRP(World Climate Research Programme):世界気候研究計画、DIVERSITAS:生物多様性科学国際共同研究計画。
- http://www.igbp.net/5.d8b4c3c12bf3be638a8000578.html
- 三枝信子, 江守正多「Planet Under Pressure会議報告—地球環境研究の新しい枠組みFuture Earthに向けて—」地球環境研究センターニュース2012年6月号
- http://www.gwsp.org/products/archive/bonn-water-declaration.html
- Rockström J., et al. (2009) Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity. Ecol. Soc., 14(2), 32.
- Schellnhuber H.J. (2009) Tipping elements in the Earth System. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 106 (49), 20561-20563.