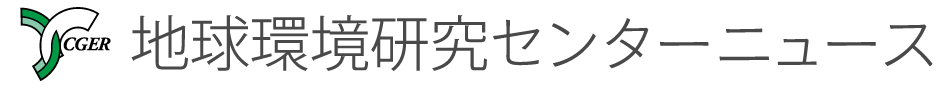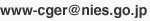2015年10月号 [Vol.26 No.7] 通巻第299号 201510_299008
インタビュー「地球温暖化の事典」に書けなかったこと 6 温暖化研究の発展を握る生態系への影響評価—生態系の変化は予測できるか—
- 三枝信子さん
地球環境研究センター 副センター長 - インタビュア:高橋善幸さん(地球環境研究センター 陸域モニタリング推進室 主任研究員)
国立環境研究所地球環境研究センター編著の「地球温暖化の事典」が平成26年3月に丸善出版から発行されました。その執筆者に、発行後新たに加わった知見や今後の展望について、さらに、自らの取り組んでいる、あるいは取り組もうとしている研究が今後どう活かされるのかなどを、地球環境研究センターニュース編集局または地球温暖化研究プログラム・地球環境研究センターの研究者がインタビューします。
第6回は、三枝信子さんに、地球温暖化に関する観測研究と温暖化による生態系への影響についてお聞きしました。

- 「地球温暖化の事典」担当した章
- 6.1 生態系 / 6.3 光合成
- 次回「地球温暖化の事典」に書きたいこと
- 温暖化影響に関する新しい観測研究
観測ネットワークの構築とデータ共有
- 高橋
-
地球温暖化にかかわる観測研究は、今でこそ大きな研究テーマになっていますが、その歴史は比較的新しいものだと思います。古くからある体系化された気象学や生態学などと地球科学分野の “境界領域” にできた新しい研究分野といってもいいかもしれません。いわゆる分野横断的な研究の最前線で、チャレンジングな要素も多かったと思います。三枝さんが大気-陸域生態系の間の物質交換という研究分野に携わってきたこの十数年は、この分野が急速に成長してきた時期に重なります。この間の研究をとりまく環境や研究コミュニティの変遷はどんなものだったのでしょうか。
- 三枝
-
陸域の炭素循環、陸域生態系の観測研究そのものは昔からあったのですが、多くの人たちが協力して観測点のネットワークを作りデータを共有するということは、私が研究を始めた1990年代前半は非常に少なかったです。それが今と大きく違うところだと思います。たとえば森林や農耕地の上で二酸化炭素のフラックス(単位面積・単位時間あたりの輸送量)を測って生態系による吸収量を算出する取り組みも、当時すでにいろいろな大学や研究所が行っていて、個別の共同研究もあったのですが、日本で30か所以上、世界で数百か所以上の観測サイトをまとめた大きなネットワークができたのは最近で、十数年前以降のことになります。
- 高橋
-
1996年にヨーロッパでEUROFLUX(後のCarboEurope)が、1997年にはアメリカでAmeriFluxが、1999年にはアジア地域のフラックス観測ネットワークAsiaFluxが活動を開始しました(地球環境豆知識 [7] FLUXNET参照)。
- 三枝
-
陸域のフラックス観測については必須観測と推奨観測の項目を決め、完全とはいえないまでも観測方法を標準化し、それを多くの観測地点に展開していきました。ただし、陸域のフラックス観測は航空機や船舶による温室効果ガス観測とは違い、一つの研究機関が世界中の多地点で観測することは難しいので、フラックス観測のネットワークや生態系観測のネットワークが作られたのです。

富士山の北麓に広がる森林。ここに国立環境研究所富士北麓フラックス観測サイトがあり、森林と大気の間で交換されている温室効果気体などの量を長期連続観測しています。

森林の中に、高さ30メートルを超えるタワーを建て、気象要素、温室効果ガスの濃度、森林による二酸化炭素の吸収速度などを観測しています。

森林の中にはさまざまな機器が設置されていて、定期的なメンテナンスなどを行っています。
生態系は予測しにくいもの
- 高橋
-
温暖化による生態系への影響は、物理化学的な影響よりもさらに予測しにくい面があると思います。それをどのように克服するのでしょうか。その方法と成果について教えてください。とくに、生態系が温暖化によってどのような影響を受けるか、できるだけ具体例を挙げて説明してください。
- 三枝
-
生態系の将来の変化については、今の私たちの知識では完全な予測はできず、本質的に私たちの理解を超えるものがあると考えるのがよいと思っています。流体力学で予測する大気の流れや、物理化学的な側面から推定する海洋と大気の二酸化炭素交換などと比べて、生物は人間の予測しがたいメカニズムによって、生物自身が変化したり移動するという性質をもっているからです。たとえば、1万年といった長い時間スケールでは新しい種ができることがありますし、動植物の適応能力についても現在の私たちの理解を超える変化がありますので、完全に予測することはできません。それが生物の適応能力をも含む生態系の一番の特徴だと思います。ですから、気候変化に対する生態系の応答を理解するうえで必要なのは、まず、現状を把握して知識を蓄積する、つまりモニタリングすることです。過去のデータから、近未来に起こることを私たちの理解、想像の範囲内で予想することはできます。
- 高橋
-
予測できないから現実に起きていることを把握・理解することが重要ということですね。
- 三枝
-
生態系応答の事例や知識について、将来の人たちに役立つようなデータを系統的に残さなければならないという使命を感じます。

- 高橋
-
生物圏が温暖化の影響を受けている具体例として、ロッキー山脈では温暖化により越冬できるようになった虫が森林を枯らせてしまったということが起きています。
- 三枝
-
生態系への温暖化影響は重要です。国立環境研究所は2011年に日本の高山帯や沿岸のサンゴに対する温暖化影響のモニタリングを開始しました。気候変化が起こると、高山帯の植物は標高の高いところに移動していくことが予想されますが、そのスピードは物理化学的な原理では予測できません。もちろん生物(植物)の側も、移動するためのメカニズムはもっています。たとえば種子を周辺に散布した場合、それが散布先(移動先)で発芽できるかどうか、発芽した後で定着するかどうか、生長していくうえで必要な水や養分があるかどうか、そういう要素で植物が移動できるかどうかが決まります。このとき、気候変化のスピードに生物の移動速度がついていけるかどうかが非常に重要ですが、この点が難しいところです。とくに垂直移動は水平移動より予測が難しいといわれています。水平移動の場合、種子散布の実験や発芽実験などによるいろいろな知見と、50年、100年で気温が何度上がるかといった物理的なシミュレーションからある程度の推定ができます。最近の研究例では、水平方向については、生物の移動が気候の変化に追いついているケースがあるとの報告があります。一方、垂直方向の移動については、追いついていないという報告があります。高山では、岩など土壌がないところがあり、気温の上昇とともに標高の高いところに生物が移動しようとしても、崖や尾根や山頂があってそれより高いところへ行けないなどの理由で生息地を拡大できないことがあります。私たちができるベストなことは、なるべく早く重要な生態系でモニタリングを始めて、変化を正確に記録し知見を蓄積することです。
- 高橋
-
生物の分布の変化などは、物理化学的というより確率的なことに支配されることが多く、簡単に関数にして予測できるものではないということですね。
- 三枝
-
物理化学的なプロセスですと、ある程度、理論と経験式の積み重ねで予測が可能ですが、生物については、枯死率、生存率、発芽率など確率的にしか記載できないことが多く含まれますので、変化を推定する手法も異なりますし、それを検証する方法も違ってきます。さらに、そのための観測データのとり方も違ってきます。
温暖化影響の指標となる動物に注目
- 高橋
-
地球温暖化の影響というと植物が主です。動物への影響はあまりないのでしょうか。
- 三枝
-
あります。温暖化の影響を受けるとされる典型的な動物や、昆虫を含む動物と植物の関係がどうなっているかということを見る必要があります。温暖化の影響で海氷面積が減少すると、ホッキョクグマは氷上で狩りができなくなって、健康状態が悪化したり数が減少するという報告があります。また、特定の昆虫に受粉されなければ生存できない植物もあるため、昆虫と植物の分布域にずれが生じると、双方の生息が危ぶまれるということが起こります。植物と動物の相互作用がなければ生態系が維持できないという地域において、一つの種が絶滅すると、その生態系全体のバランスが大きく崩れる場合があるときに、特定の種を指標のように扱って、その個体数や変化に注目することもあります。ところで、私たちの目にはあまり見えていませんが、地球の炭素循環に圧倒的な影響を与えているのは微生物です。土壌のなかに私たちがまだ知らないたくさんの種類の微生物がいます。私たちが観測している富士北麓などの森林の観測サイトにおいても、植物が吸収した二酸化炭素の半分以上を土壌微生物が大気に戻していますから、微生物の役割は重大です。
物理学と生物学との価値観の違い
- 高橋
-
三枝さんは気象学に近い分野の出身で、大学では生態学に近い分野で教官を務めていた時期もありますね。そういうご経験についてお話ください。
- 三枝
-
もともと東北大学では地球物理の気象学を専攻していました。筑波大学の生物科学系に職を得たのは偶然でしたが、生物学の分野で働き始めて、双方の研究分野で考え方が180度くらい違うということにすぐに気づきました。物理学では、世界を一本の式で表せるような統一的・基本的な原理を見つけることに高い価値をおく一方、生物学では新種発見をはじめ私たちの理論や知識を軽々と超えていく生物の多様さを見出すことに価値をおくようでした。最初はとまどいましたが、異なる価値観をもつ二つの分野で研究する経験をしたことにより、得るものは大きかったと思います。たとえば物理学の分野で確立した観測手法を応用して生態系の観測を行い、予測しにくい生態系の応答を謙虚に検出しようという考え方につながったと思います。
- 高橋
-
生態系のガス交換に関する研究はどちらかというと理論先行で、観測技術は少し遅れてついてきた印象がある分野ですね。
- 三枝
-
はい。二酸化炭素や水収支の観測技術は、最近10年から20年で向上し、世界各地で無人観測ができるまでに発展しました。こうした技術を気象学からもらい、生態系の応答について何を明らかにすべきかという問題意識と、これまでに蓄積されたたくさんの知識を生態学からもらいました。

さまざまな分野の新しい研究成果を加えたい
- 高橋
-
次回、『地球温暖化の事典』を執筆するとしたら、書きたい内容はありますか。
- 三枝
-
全体構成として、温室効果ガス、エアロゾル、地球システムなど、温暖化に関する基本的な物理化学的なシステムについてはよく網羅されているのですが、生物圏や湖沼をはじめ、温暖化に対して脆弱な地球表層への影響については、章はあるものの、事典発行後の研究の発展が大きいので、強化した方がいいかなと思っています。とくに海面上昇、海洋酸性化、高山帯や沿岸の生態系、雪氷や極域、植物と動物の相互作用を含む生物多様性についてです。私がとくに強化したいと思うのは、気候と生態系の間のフィードバック効果についてです。地球が温暖化すると極域で永久凍土が溶けて、地中に蓄えられた大量の炭素が二酸化炭素やメタンなどとして大気中に放出されます。その放出がかなり大きいと、放出された温室効果ガスがさらに温暖化を加速するので、私たちの予想を超えたスピードで温暖化が進行するかもしれません。これが正のフィードバックです。逆に負のフィードバックもあります。温暖化して高緯度の気温が上がり、降水などの水条件がよければ、亜寒帯域やツンドラ地帯でも森林が定着したりバイオマスが増える可能性があります。森林は大気中の二酸化炭素を固定しますので、負のフィードバックがかかり、温暖化のスピードを緩める効果があるかもしれません。このような気候変化と生態系プロセスによるフィードバックメカニズムとその実証に関する章が一つほしいですね。
- 高橋
-
今のお話で、三枝さんがカバーしている範囲は広いという感じがします。
- 三枝
-
私自身がすべてをカバーはできませんが、幸い、地上観測、衛星観測、近接リモートセンシングなどいろいろな手法を使った生物・生態系の新しい研究手法も発展しています。ただ、やはり私たち陸域分野の研究者は、自分が調査している事象や生態系については非常に詳しいのですが、世界の生態系の中で何が起こっているかを全体として明らかにしましょうといった研究の総合化があまり得意ではないので、それを乗り越えていかなければなりませんね。
*このインタビューは2015年9月1日に行われました。