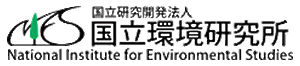令和6年度スーパーコンピュータ利用研究報告会を開催しました
国立環境研究所(以下、国環研)地球システム領域 地球環境研究センター(以下、センター)は、2024年12月19日(木)に令和6(2024)年度スーパーコンピュータ利用研究報告会(以下、報告会)を開催しました。開催方式は参加者が対面とオンラインのどちらかを選択できるハイフレックスを採用し、今年度はのべ34名(対面17名、オンライン17名)にご参加いただきました。現地の様子を写真1に示します。

国環研は、将来の気候変動予測や陸域・海域モデル等の研究開発、温室効果ガスやエアロゾルの逆解析・データ同化、その他基礎研究を支援する目的で、長年にわたりスーパーコンピュータ(以下、スパコン)を整備・運用し、所内外の研究者に計算資源を提供してきました。スパコンの利用・運用方針等は、国環研に設置した「スーパーコンピュータ研究利用専門委員会」(以下、専門委員会)において審議を行っています。
令和6年度は7つの所内課題、2つの所外課題が採択され、報告会では幅広い分野からの最新の研究成果が報告されました。その中から2つを紹介します。
「高度な大気汚染予測のためのデータ同化手法の開発」(課題代表者:五藤大輔)では、全球大気汚染物質輸送モデルのNICAM-Chemを用いて、エアロゾル観測の中で最も利用可能なデータが多いエアロゾル光学的厚さ(AOT)を対象とした2次元変分法(2DVar)によるデータ同化シミュレーションの結果(Goto et al., 2024, doi:10.1029/2023MS004046)が報告されました。エアロゾルの鉛直積算量であるAOT同化によって、エアロゾル地表PM2.5 濃度の再現性が改善し、既存のエアロゾル再解析データセット(MERRA-2やCAMS)とも遜色ない結果が得られることも示されました(図1)。
![図1 (a)札幌付近、(b) 東京・埼玉付近、(c)大阪・京都付近、(d)福岡付近における各種推定による地表PM2.5質量濃度 [µg m-3] の時間変化。 2021年3月23日から4月4日までの期間である。この推定には、地上測定 (Observation: 環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君))、NICAM/2DVar+G(地上観測のみをデータ同化に利用)、NICAM/2DVar(衛星観測のみをデータ同化に利用)、NICAM(同化なし)、および3つのモデル参照結果(MERRA-2、CAMS、WRF-CMAQ)。この元データはGoto et al. (2024)からの引用である。(課題代表者、図の提供:国立環境研究所五藤大輔主幹研究員)](/assets/images/cgernews/202502/411003-fig01.gif)
所外課題の「NICAMによる雲降水システムの研究」(課題代表者: 佐藤正樹)からは、NICAMを活用したシミュレーションと2024年5月に打ち上げられたEarthCARE衛星のデータの相互比較についての報告がありました。図2は、NICAMを利用して870mおよび3.5kmの水平解像度でシミュレーションした南半球における対流現象(前線)の断面を示しています(衛星観測データは一般公開前のため図示していません)。レーダー反射強度(a,b)では、高度2 km付近に融解層が確認できますが、そこにあるのが雨か雪かは不明確です。一方で、ドップラー速度の解析結果(c,d)は、雨(青色)と雪(黄色)の区別が明確に可能であることを示しています。また、より高解像度のシミュレーション結果(a,c)では、低い雲の割合が減少し、大気の鉛直速度がより詳細に表現されていることが確認できます。人工衛星に搭載されている雲レーダーはモデルの雲物理過程および対流現象を検証し、理解を深めるために大変有用です。EarthCARE衛星データは、2025年1月から順次一般公開される予定です。
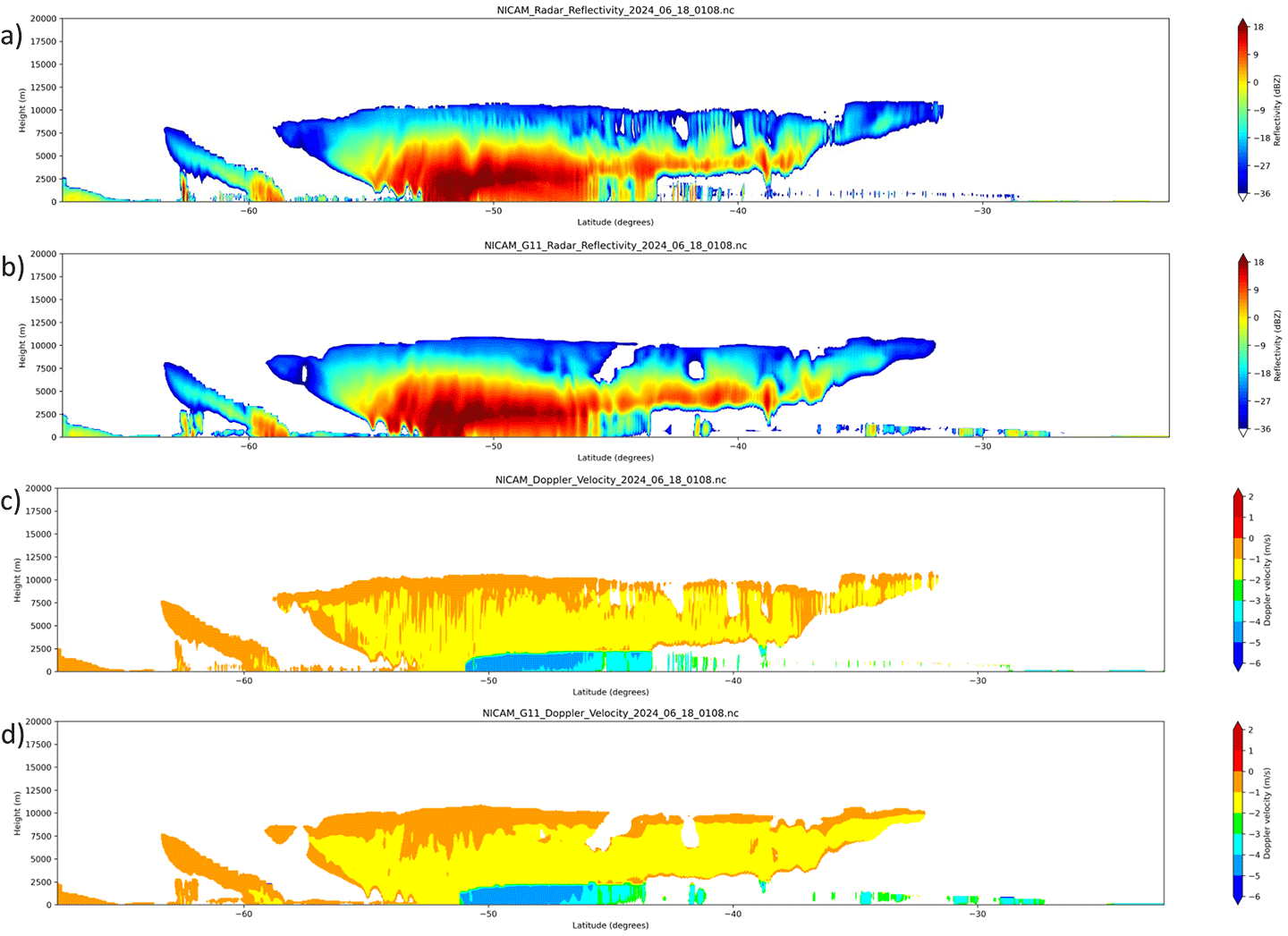
専門委員会には所外の3名の外部委員に参画頂いており、今回も多くの貴重なご意見をうかがうことができました。また、スパコン事務局から利用者に向けて、令和6年10月までの過去1年間のスパコンの運用状況についての報告も行われました。今年度は落雷による停電が2回ありましたが、それを除けばベクトル型スパコンNEC SX-Aurora TSUBASAは大きなトラブルもなく順調に動いており、昨年度10月から1年間の利用率は平均で約80%(高い月では95%)の占有率でご利用頂いていることが報告されました。来年度には令和2年3月の稼働開始からの運用年限(6年)を迎える予定で、次期計算基盤についての検討も佳境に入っております。多くの利用者の皆様に有意義に利用して頂けるよう、引き続きスパコン事務局も尽力して参ります。
年の瀬のお忙しい時期にもかかわらず、課題代表者をはじめとするスパコン利用者の皆様、所外の研究利用専門委員、所内各担当委員の皆様にご参加頂き、活発な研究議論を行うことができました。心より御礼申し上げます。
当日報告された内容の詳細については、センターのウェブサイト(https://www.cger.nies.go.jp/ja/supercomputer/)をご参照ください。サイトには、スパコンの紹介や、過去の報告会での発表内容に関する情報も掲載されています(文中敬称略)。
※地球環境研究センターニュースに掲載されたこれまでのスパコン利用研究報告会の記事はアーカイブ(https://www.cger.nies.go.jp/cgernews/archive/supercomputer.html)からご覧頂けます。