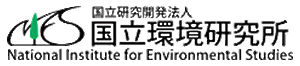気候変動リスクをめぐって ガバナンスとコミュニケーションの観点から
気候変動リスクでのガバナンス(合意を作り守っていく体制)とコミュニケーションについて、最近の僕の考えを説明したいと思います。一部、社会環境システム研究センター(現:社会システム領域)の朝山慎一郎主任研究員に相談にのってもらいました。
※この記事は低炭素研究プログラム・地球環境研究センター合同セミナー(2021年3月4日開催)における発表をまとめたものです。
1. 気候変動とそのリスク
異常気象の増加:気候変動を背景として気象災害が増えており、被害額も増加しています。国土交通省によると、2019年10月の台風19号による被害総額は、津波を除く水害としては、1961年の統計開始以来で最も大きい額になりました(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001359046.pdf)。これは、2019年の世界最大の被害額でもあります(図1)。
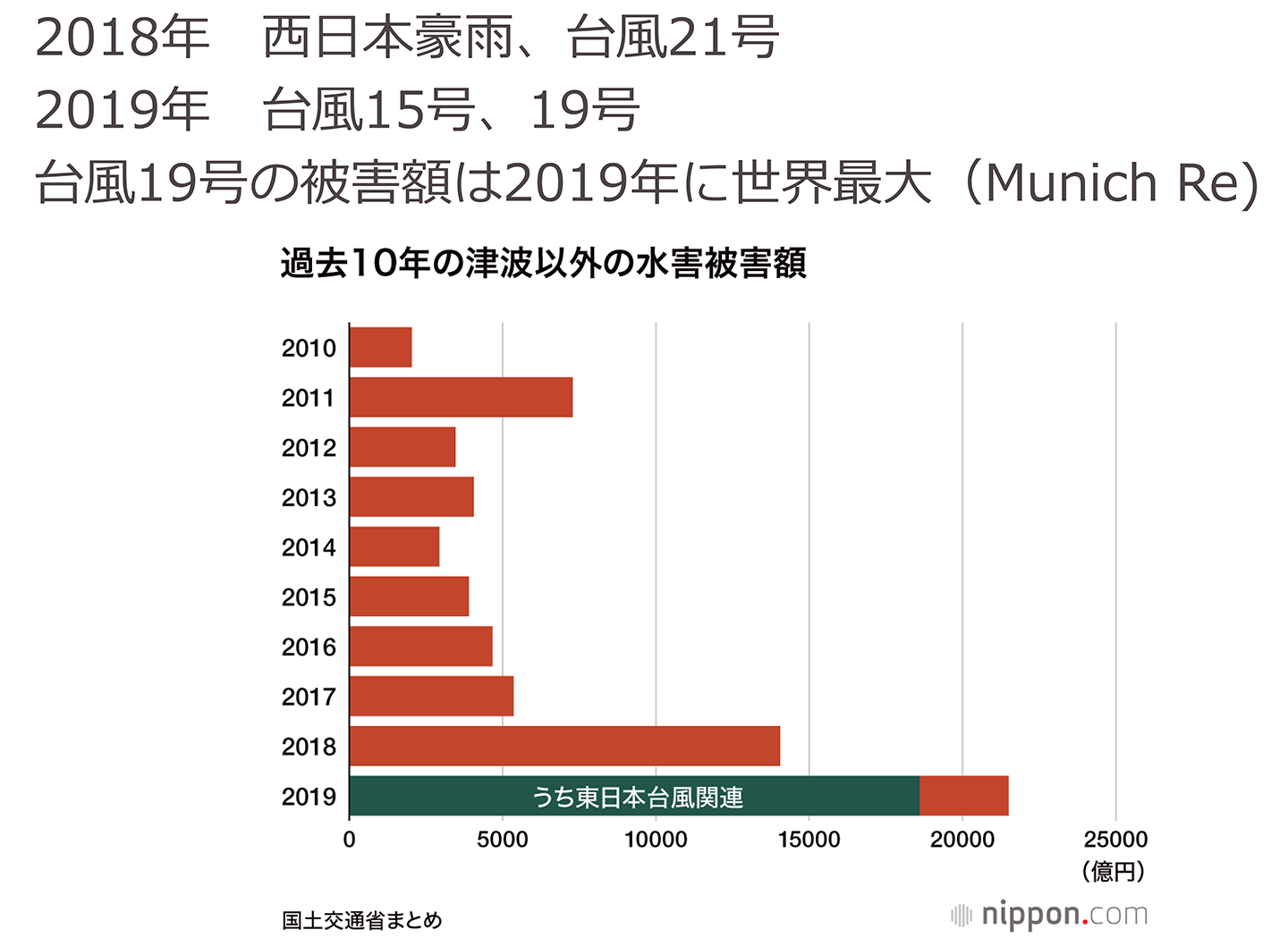
ティッピングエレメント:かつて、温暖化はあるところまで進むと決して止められなくなるのではないかということが話題になり始めた時、そんなに簡単に暴走しないという解説を書いていました(江守正多「温暖化は暴走する?」ココが知りたい地球温暖化(http://cger.nies.go.jp/ja/library/qa/20/20-2/qa_20-2-j.html)参照)。しかし、温暖化の進行によりさまざまなティッピング(臨界点)現象がドミノ倒しのように連鎖して起こり、温暖化が+4℃くらいまで止められなくなる危険性が指摘されました。この現象はHothouse Earthと呼ばれ、現在注目されています(https://www.pnas.org/content/115/33/8252)。
気候正義:発展途上国や将来世代の人たちは、産業革命から今まで先進国に生きてきた人たちに比べてほとんど二酸化炭素(CO2)を出してないのに深刻な被害を受けます。この構造を是正すべきという「気候正義」(詳細は、広兼克憲「地球環境豆知識34 気候正義(climate justice)」地球環境研究センターニュース2018年4月号を参照)の認識はいくら強調してもしすぎることはないと思っています。先日、委員として出席したある審議会で、ヒアリングに呼ばれたFridays for Future Japanの若者が気候正義を熱く語ってくれたのですが、委員の反応は薄く、大人が彼らの声に答えられていないことが僕自身としては非常に気になっているところです。
2. ガバナンス
パリ協定:パリ協定には「世界的な気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求する」という長期目標があり、そのためには「今世紀後半に人為的な温室効果ガスの排出と吸収源による除去の均衡を達成する」必要があります(図2)。しかし、各国が国連に提出した「国が決定する貢献(NDC)」との間にはまだギャップがありますから、これからNDCを何倍にも引き上げていかなければなりません。日本でも目標を見直している最中です。
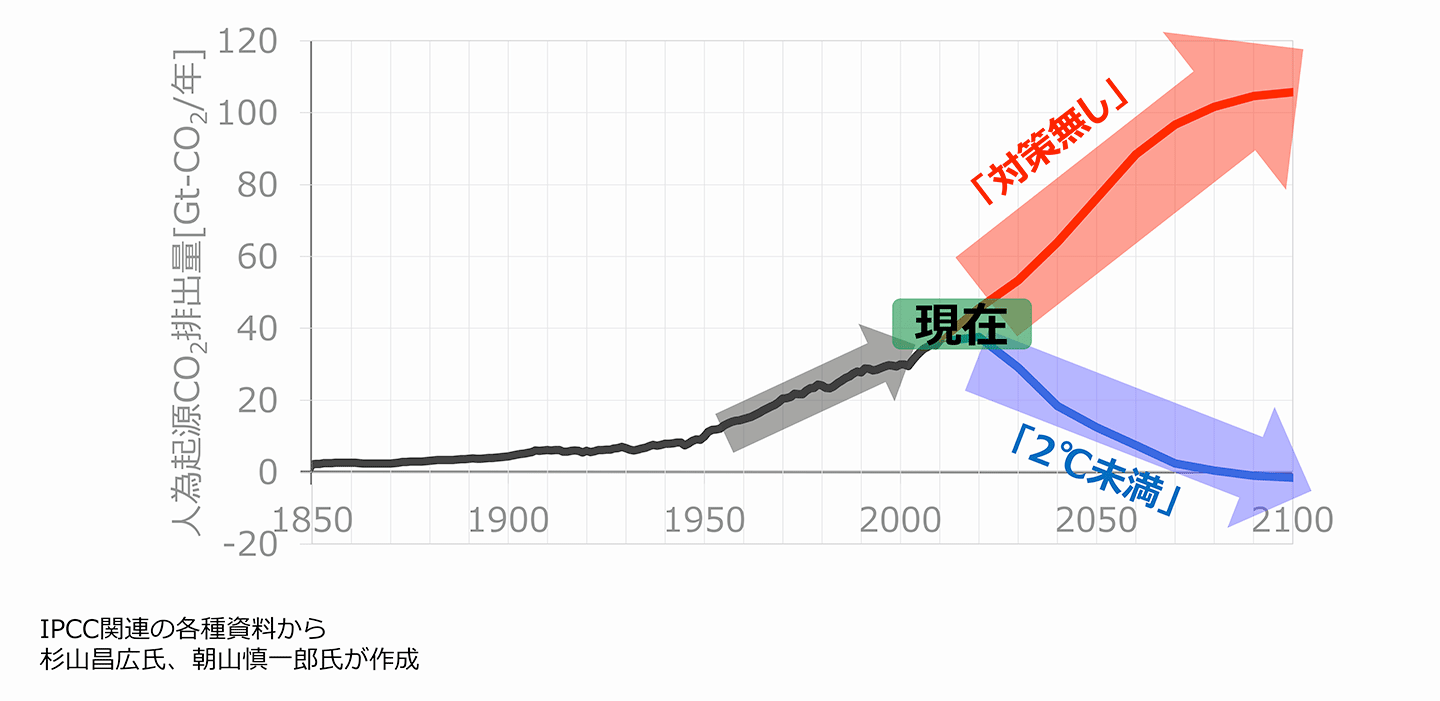
トランスフォーメーション:トランスフォーメーションとは、一言でいうと、常識が変わってしまうような社会の変化というのが僕のイメージです。たとえば、今はエネルギーを使うとCO2を排出するのは仕方がないという常識で頑張って排出削減しようとしていますが、やがてCO2が出ないのが当たり前の社会になる。そんなトランスフォーメーションの原動力となるものとして、Market(グリーン投資、再生可能エネルギー(以下、再エネ)の価格低下)、Technology(イノベーションなど、特にデジタル化との組み合わせ)、Policy(規制、炭素の価格付け)、Norms(気候正義)の4つが挙げられると思います。
世界のエネルギー源の推移:再エネは加速度的に増えていますが、世界の一次エネルギー全体に占める割合はまだわずかです。再エネを増やして、あと30年で化石燃料分を賄うことができるでしょうか。これを考えるとき参考になるのが、諸技術の普及率の推移です。技術の普及は当初ゆっくりなのですが、あるところを過ぎると一気に進みます。こうしたことにもティッピングみたいな臨界点があるのでしょう。そういうパターンで再エネが普及していくことがあるかもしれません。
パラダイムシフト:京都議定書のころは排出量重視で、国家間の駆け引きは負担の押し付け合いでした。パリ協定の現在は技術の進展という要素が新たに重要になりました。京都議定書のときには現実的ではなかった安価な再エネが今はあります。
こうした技術の転換で排出削減できるなら、世界のエネルギーインフラを入れ替えるという巨大マーケットが発生して、ビジネスチャンスの奪い合いになるといわれています。「負担の押し付け合い」から「ビジネスチャンスの奪い合い」へとパラダイム(物の見方や捉え方)がシフトしているのです。 2017年にこのことを論文*1で読んだときには、こういうことが始まってもおかしくないと思いましたが、世界脱炭素時代に入った今、まさにこのとおりのことが起きているように見えます。
市民議会:無作為抽出により、実際の人口と年齢構成や男女比、学歴などの比率を合わせて市民を集め、専門家からの情報提供を受けながら対話的に議論し、そこで形成された意見を政府に提案するやり方があります。これが市民議会(Citizens' Assembly)で、イギリスやフランスでは国家規模で100人以上を集めて何カ月もかけて行われました。最近、日本(札幌)でも小規模ですが、僕も入っている研究グループがこれを試行しました(https://citizensassembly.jp/project/ca_kaken)。
3. コミュニケーション
懸念の理由:リスクの深刻さ(懸念)は見方によって違うという認識が重要です。また、人によって見方は異なり、その人の価値観に依存します。たとえば、産業化前と比較して世界平均気温が約1℃上昇している現在、世界経済に影響が出ているとはいえなくても、サンゴの白化や死滅など固有の生態系や文化にはすでに大きな影響が出ています(図3)。
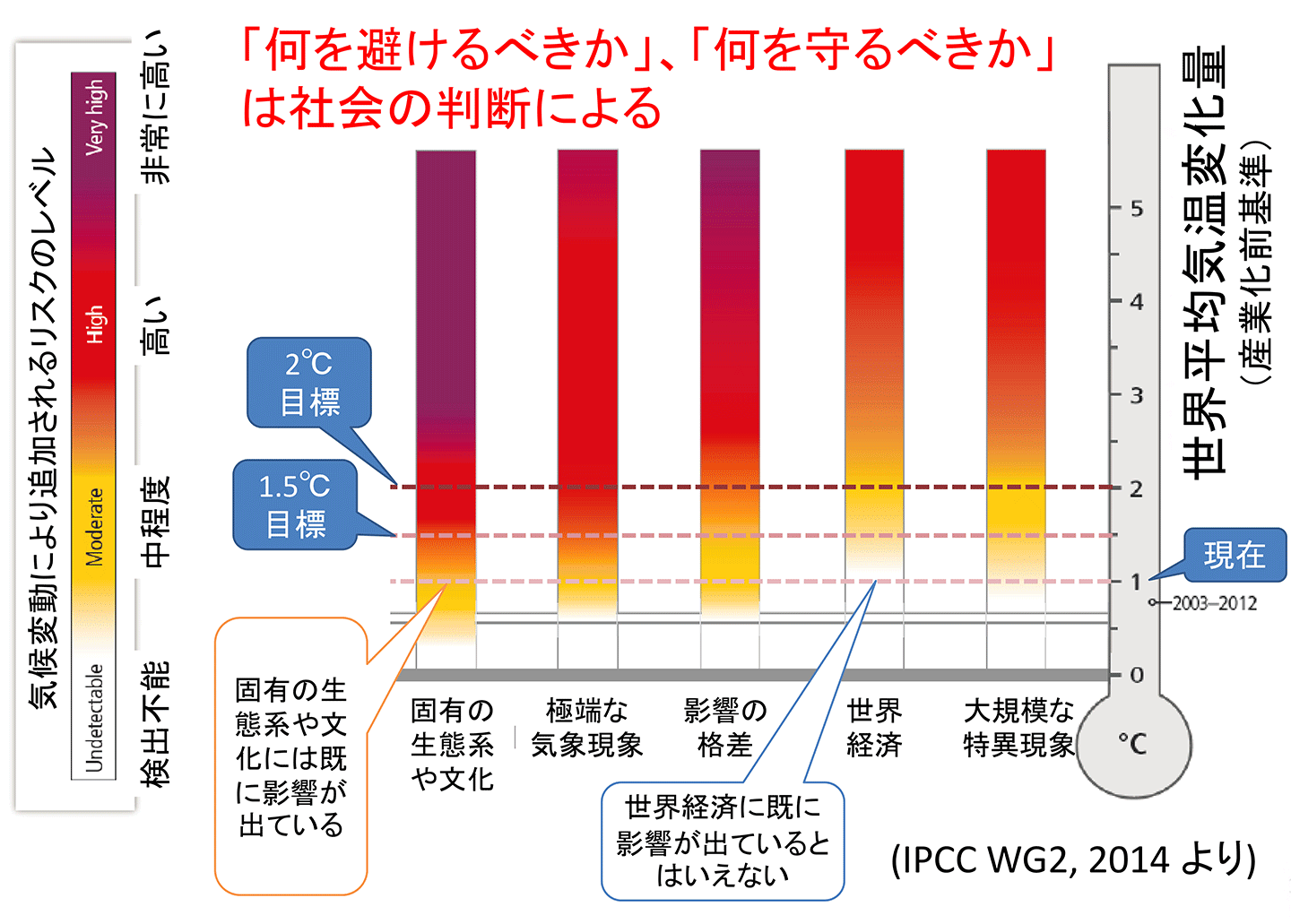
どの見方が大事かというのは、人の考え方によって違ってきます。アメリカでの研究によれば、個人主義対共同体主義、階級主義対平等主義、という分け方をした場合、リベラルな人たち(平等主義的共同体主義者)は科学的知識が増すほど、気候変動は重要な問題だと思っています。
一方で逆の考え方の人たち(階級主義的個人主義者)は、科学的知識が増すほど、気候変動は大きな問題ではないと、リスクの認知が低くなっていく傾向があります。気候変動の知識がないから深刻さがわかってないとよくいうのですが、科学的知識が増すほど、文化的グループによる認知の差が大きくなることがあります(https://www.nature.com/articles/nclimate1547)。
「欠乏」のコミュニケーション:2050年までに脱炭素を実現しようとすると、残された許容の排出量はこれだけしかないという表現で危機感を共有することになりがちです。また、2050年までに脱炭素を実現しようとすると、あと30年も時間があると思う人もいるので、2030年までに、2025年までにと締切を手前に設定して、それまでに達成できないと大変なことが起こるというコミュニケーションも多くなってきています。
2018年に公表されたIPCCの1.5℃特別報告書では、早ければ2030年には1.5℃上昇に到達してしまう、また、2030年に世界のCO2排出量を半減する必要があると書かれています。2018年に2030年のことがクローズアップされ、イギリスの新聞The Guardianが、"We have 12 years to limit climate change catastrophe, warns UN"(あと12年しかない)という見出しの記事を掲載しました。それを読んだ若者などがかなり反応したようです。あと12年で世界が終わるわけではないと専門家が解説しましたが、締切を煽りすぎるのも功罪があるのではないかという議論が出ています(https://www.nature.com/articles/s41558-019-0543-4)。
希望のナラティブvs危機のナラティブ:危機感を共有しないと気候変動問題は解決しないので、メディアにもっと危機を伝えてほしいという人たちがいます。しかし危機だけを強調すると人々は認知的不協和になり、考えることを止めたり麻痺してしまうと心理学的に解説されています。ですから、同時に解決策や希望を示すことが大事だということをよく聞きます。
たとえばマイケル・ブルームバーグ氏(世界的な企業・金融情報会社であるブルームバーグの創業者で元ニューヨーク市長)が『HOPE』という本を書いて、気候変動問題を解決に導く希望があると言っています。しかし、そういうことを言っていたらグレタ・トゥーンベリ氏(スウェーデンの環境活動家)が出てきて、「希望はあると人々は言ってきたけど、排出はまったく減っていないではないか。hopeより大事なのはactionだ」と言ってのけました。希望があると言い続けていていいのかと、わからなくなってきたというのが最近の僕の心境です。
4. 日本の場合
産業政策としての脱炭素:日本も脱炭素社会を目指す段階に突入しましたが、大部分は産業政策として動いているように見えます。経済界などでは気候変動の影響でダメージを受けるので深刻だという認識もありますが、国内で脱炭素の必要性の理由が深く議論されている感じがしません。ヨーロッパやアメリカ民主党などは、気候正義のような倫理的な認識があって脱炭素の必要性を議論していると思います。そこからの外圧により、日本もよくわからないけど脱炭素することになったという感じが強いです。
経済産業省×環境省:経産省が専門家主導でエネルギー政策を進め、環境省は限定された役割の中で国民のライフスタイルなど「普及啓発」を推進しています。ガバナンスの断絶があるのではないかと危惧します。
日本人の負担意識:「あなたにとって、気候変動対策はどのようなものですか?」と聞くと、世界平均では生活がよくなるという人が70%近くいるのに対して、日本では生活を脅かすと答える人が60%くらいいて、日本人は対策を我慢とか負担だと思っているようです(図4)。こういう状態ですと、社会の大部分がこの問題に興味をもつということは起こりそうもない気がします。外圧で動くということと、強い関心をもっている一部の人たちが声を挙げて加速していくという戦略をとることになるでしょう。
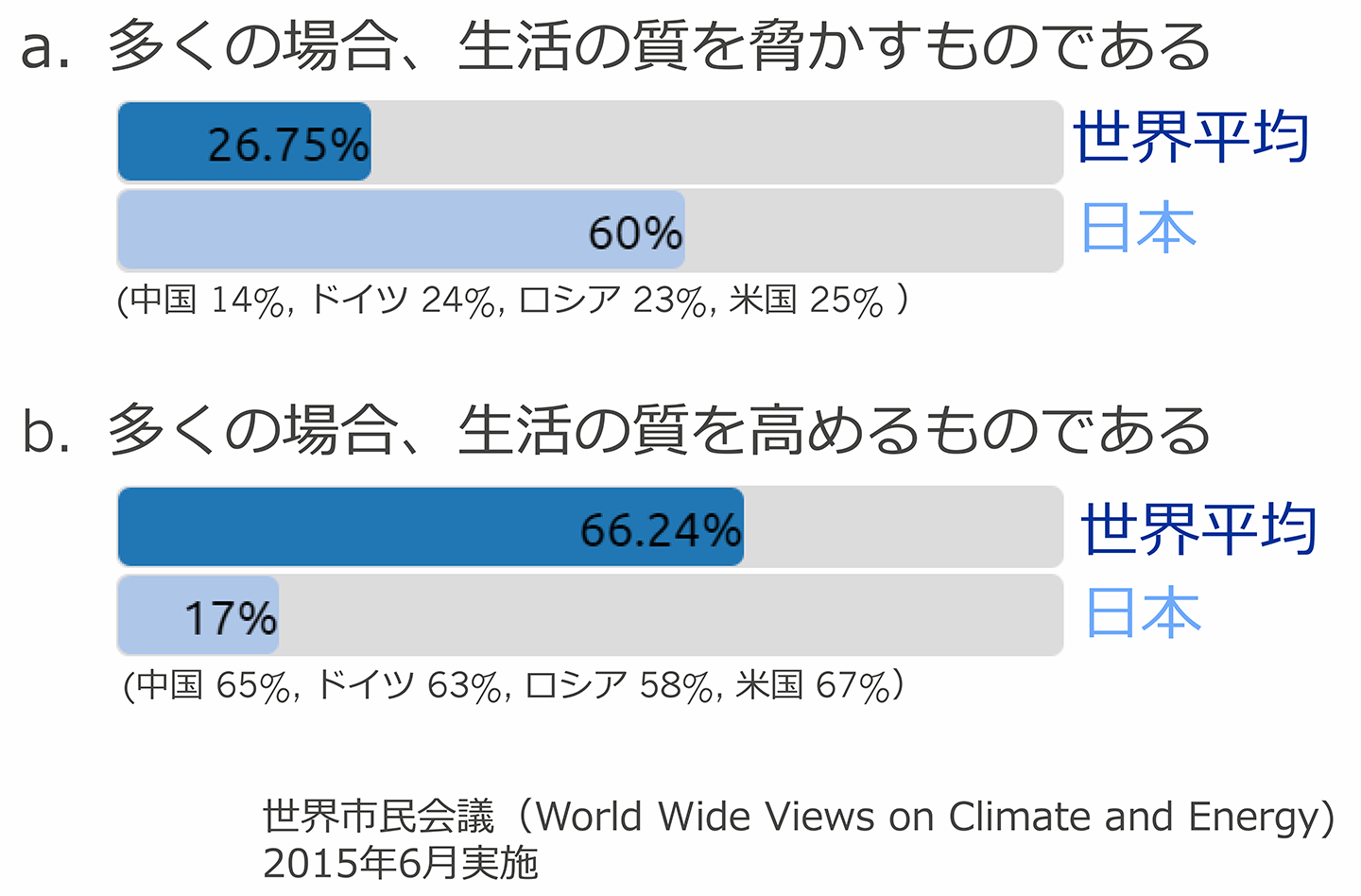
社会像の対立軸のシフト:これまで、従来の経済成長派(化石燃料による成長を擁護)とグリーン成長派(再エネなどにより経済成長と環境問題のデカップリングを志向)の間で綱引きが行われてきました。綱引きはグリーン成長派が勝利を収めつつあるように見えます。しかし、グリーン成長では経済格差や労働問題、パンデミックは解決できなさそうということで、今度はポスト成長やポスト資本主義が注目されています*2。グリーン成長対ポスト成長の、新しい綱引きが始まっているように見えます。