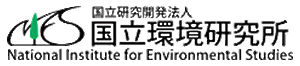Ocean Sciences Meeting 2020参加報告 学会にもIT化の波:ポスター発表も紙からタッチパネルへ
1. はじめに
2020年2月16日から21日、米国サンディエゴにおいてOcean Sciences Meeting 2020が開催された。本大会は米国地球物理学連合(American Geophysical Union: AGU)、陸水海洋学会(Association for the Sciences of Limnology and Oceanography: ASLO)、海洋学協会(The Oceanography Society: TOS)の共同開催であり、1982年に第1回が開催されて以来、2年毎に開催されている。

本大会が開催された2月は、今なお世界で猛威を奮っている新型コロナウイルスが武漢を中心とする中国各所で大流行していた時期であり、日本でも武漢からの帰国者やダイヤモンド・プリンセス号のケアに追われていた頃であった。開催地の米国では、中国滞在歴のある人に対する入国禁止措置が取られた直後ということもあり、海洋学・陸水学の分野でも多くの研究者を輩出している中国からの参加者がほとんどいないという異例の会議となった。それでも閉会時のアナウンスによれば、66ヶ国から6300人を超える参加者があったようだ。
筆者は大気-海洋相互作用をテーマとするセッションで南極海(南大洋)の二酸化炭素(CO2)収支に対する生物影響に関する研究発表を行った。研究の詳細については、本号の「南極海の二酸化炭素吸収:微細藻類の量だけでなく種類が鍵となる?優占群集の違いが夏期の炭素収支を左右していた?」を参照されたし。本報告では、新しく導入された発表形式と同セッションを中心とした会議の様子について紹介する。
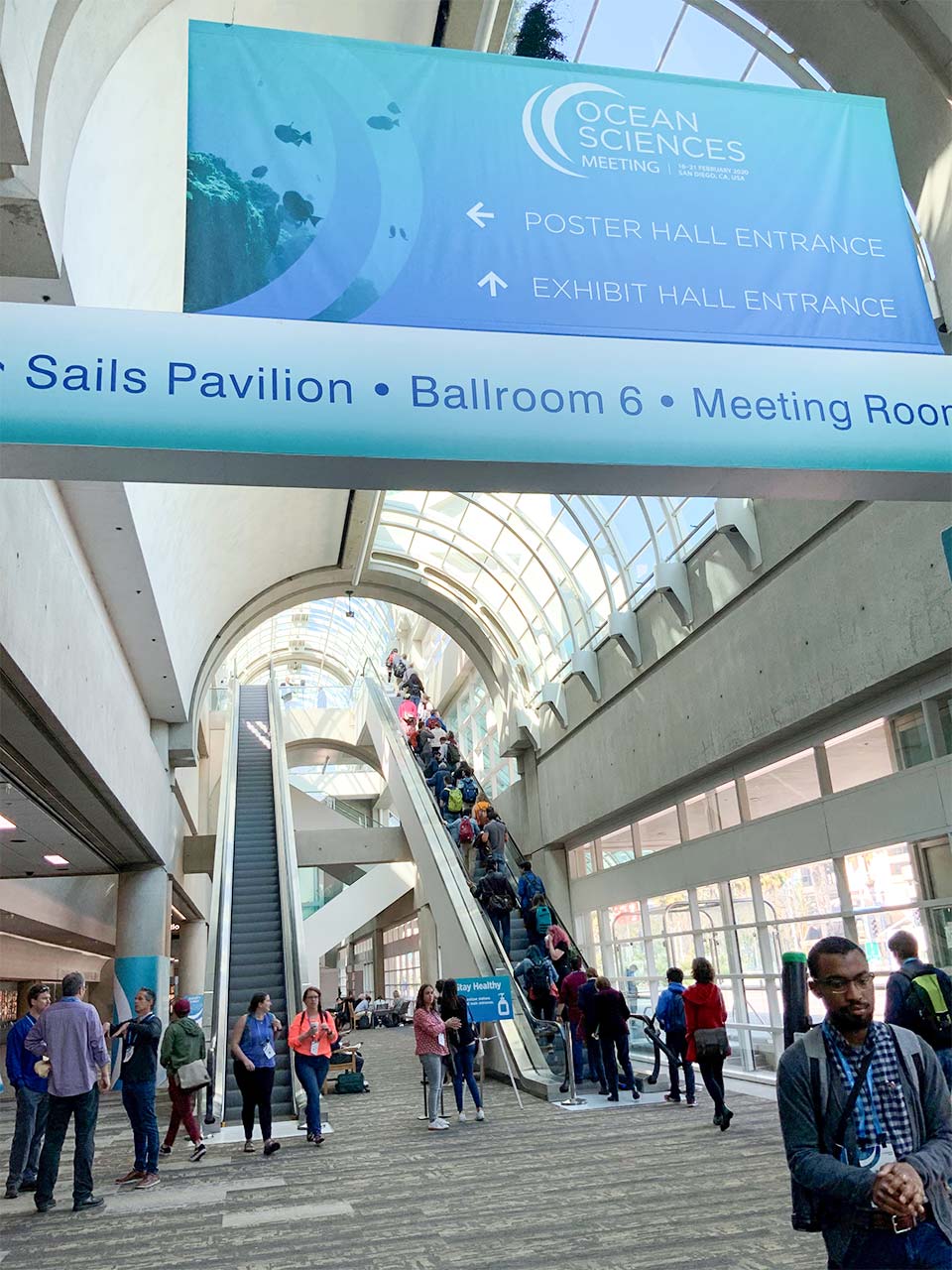
2. 新しい発表形式eLightning
Ocean Sciences Meetingでは、従来の口頭発表、ポスター発表に加え、今回初めてeLightning発表が採用された。eLightningは口頭発表とポスター発表を組み合わせたような形式であり、まず発表者全員(10名程度)がポスター会場に設けられた大型ディスプレイを使って自身の研究成果について3?5分程度の口頭説明を順に行う(写真3上)。全員の説明が終わった後に10分程度の質問や議論の時間が設けられており、聴衆はその場で発表者へ質問することができる。それが終わると、各発表者は用意されたタッチパネル式ディスプレイの前に移動して、従来のポスター発表のように聴衆と個別に議論を交わすという流れだ(写真3下)。この発表形式はこれまでの紙のポスターと違い、映像や音を流せることに加えて、その場でweb情報にもアクセスできる利点もある。従来の学会発表でもポスター内容を1分程度で説明する試みはあったが、eLightningは音楽やアニメーションも活用することができ、より口頭発表に近い印象を受けた。筆者もこのeLightning形式で発表を行ったが、研究室でパソコンを前にして同僚とアイディアを出し合い、webからも情報を得ながら議論を交わしているような、そんな感覚の学会発表であった。


3. 大気-海洋相互作用セッション
会議5日目と6日目に行われた大気-海洋相互作用のセッション「Processes Affecting Air?Sea Exchange and the Biogeochemistry of the Upper Ocean」で筆者は発表を行った。本セッションは、細菌や植物プランクトンのような小さな生物から台風などの大規模な大気海洋現象まで、大気と海洋間の熱や物質のやり取りに関与する事象を幅広く扱っており、2日間で口頭発表16件、ポスター発表18件、eLightning発表12件が行われた。本セッションを通じて感じたことはドローンを活用した研究がかなり浸透してきた点である。CO2を始めとする温室効果ガス測定に関しては、米国ノース・カロライナ州にあるエリザベス・シティ州立大学のJ. Yuan教授からドローンに搭載したセンサーで海洋直上から300 m付近までのCO2濃度の鉛直プロファイルを観測する取り組みが紹介された。ドローンへの積載重量やバッテリーの持ち時間など制約はまだ多いが、ネットで購入した商品を運んでくるドローンが同時に温室効果ガスも測定してくれる、そんな未来もそう遠くないのかもしれないと感じた。
また、NOAA(アメリカ海洋大気庁)のA. Sutton博士からは風力・太陽光発電で自動航行可能な無人船(Saildrone)を活用した研究成果が報告された。Sutton博士らの研究グループは約7 mのSaildroneで南大洋を周回しながら大気と海洋のCO2濃度の連続測定を試み、200日近くかけて南大洋1周観測に成功したそうだ。人工衛星、船舶、ブイといった従来の観測手法に加えて、今後Saildroneを活用した観測空白域の集中観測が実現すれば、大気-海洋間の炭素収支の定量化やその変動要因の解明が更に進むと考えられる。
4. さいごに
次回のOcean Sciences Meeting 2022はハワイでの開催が予定されている。新型コロナの影響で先が見えない情勢だが、この難局を乗り越えて世界中の研究者が笑顔で再会できることを切に願う。