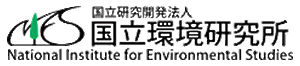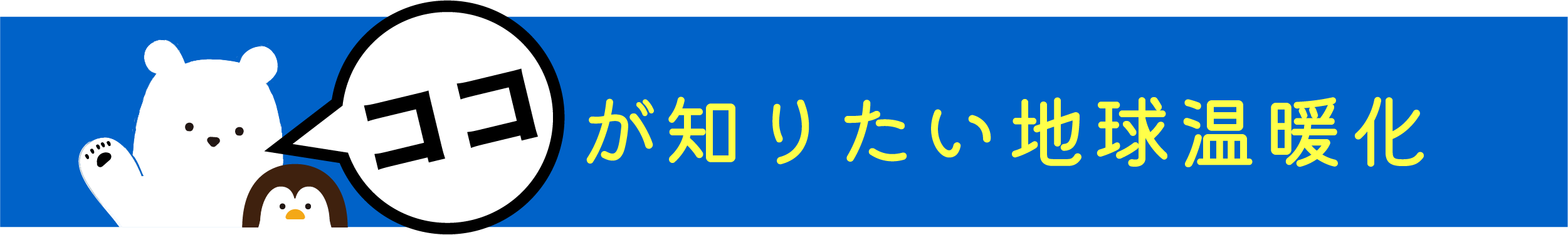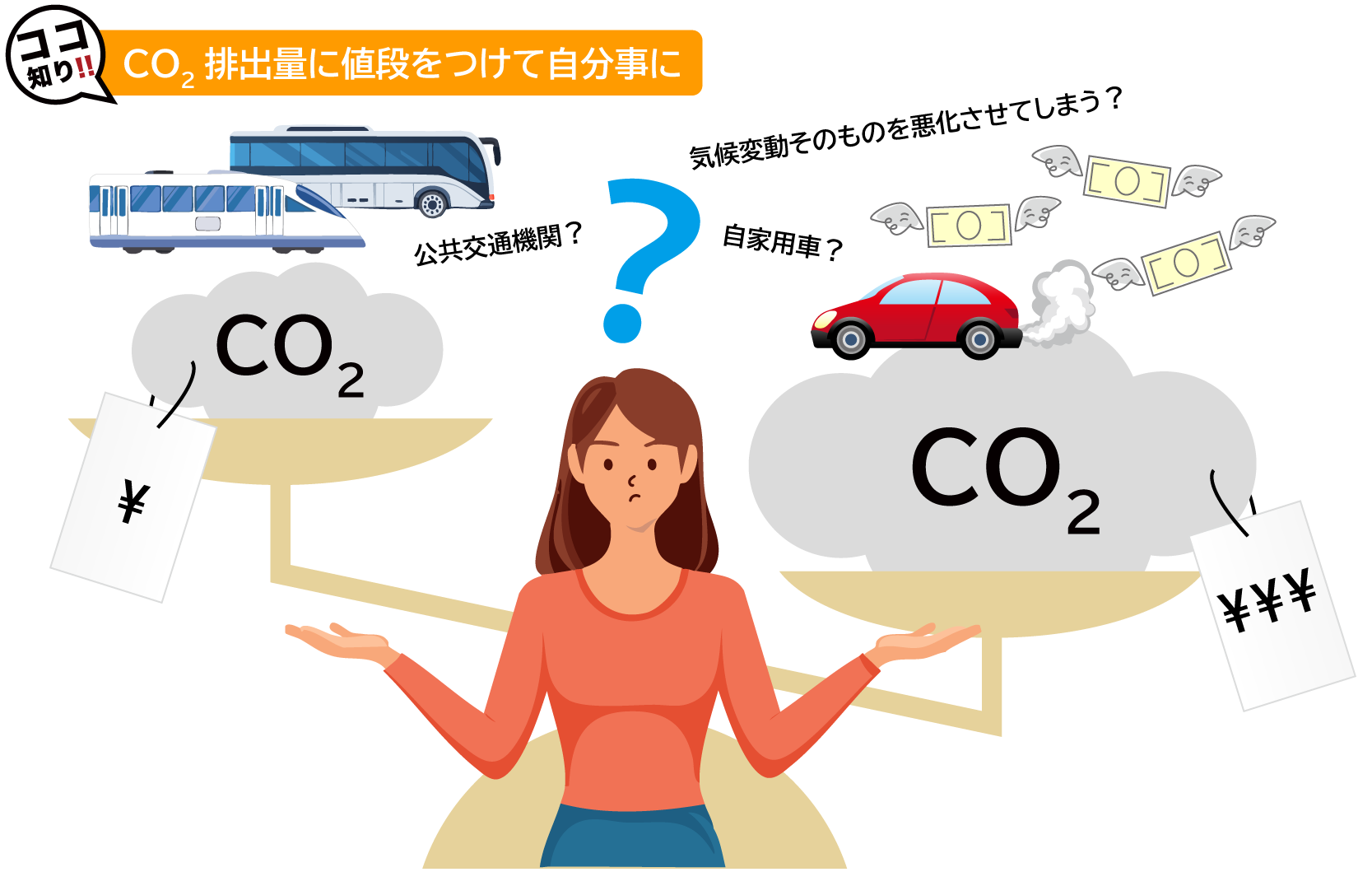Q9カーボンプライシング
!本稿に記載の内容は2025年07月時点での情報です
カーボンプライシングとは何ですか?カーボンプライシングを導入するとどうしてCO2排出量が削減されるのですか?

岡川 梓
(国立環境研究所)
カーボンプライシングとは、二酸化炭素(CO2)排出に価格をつけることであり、CO2排出の少ない行動を選んだ場合の金銭的なメリットを作り出すことを目的としています。カーボンプライシングを導入すると、CO2排出の少ない行動が選ばれやすくなり、人々が行動を選ぶときに、その都度気候変動を意識しなくてもCO2排出が削減されます。多くの人にとってCO2排出削減を自分事にするカーボンプライシングは、厳しい削減目標の達成に社会全体で長期的に取り組むために不可欠な仕組みです。
1カーボンプライシングとは?
カーボンプライシングとは、CO2の排出に値段(価格)をつけることです。CO2をたくさん発生させる行動にたくさん費用がかかるようにして、CO2排出の少ない行動を選ぶメリットを作り出すことを目的としています。
化石燃料由来のエネルギーに頼っている現代社会では、私たちのほぼ全ての行動にCO2排出を伴います。現在問題となっている気候変動は、主にCO2を始めとする温室効果ガス排出によって引き起こされ、地球全体、人間社会全体に直接、間接に被害を与えます。
しかし、私たち自身がいま排出したCO2が、すぐに目に見える被害となって跳ね返ってくるわけではありません。実感できるほどの被害が出てくるには長い時間がかかります。しかも被害を受けるのは地球全体、社会全体であり、排出の多かった人ほど大きな被害を直接的に受けるとは限りません。
このように、自分の行動選択の結果が自分の受ける被害に直結していないと(または直結していると認識していないと)、CO2排出削減が自分事ではなく他人事になります。他人事のままでは、環境配慮の意識を強く持っている一部の人しか排出削減をしないでしょう。
気候変動問題の難しさは、大部分の人にとってCO2排出削減が自分事になりにくいことに原因があります。私たちは2050年カーボンニュートラル実現に向けて大幅な排出削減に長期的に取り組む必要がありますが、多くの人が強い環境配慮の意識を持ち続け、毎日ずっと排出削減の努力をし続けることはほぼ不可能です。
これを解決し、多くの人がCO2排出削減を自分事として考えるようにするのが、カーボンプライシングです。カーボンプライシングが導入されてCO2排出に価格がつくと、一つ一つの行動がどれだけ気候変動そのものを悪化させるかが金銭的な負担(費用)として明らかになり、それを支払うことを求められます。支払う費用の大きさはCO2排出量に比例しますので、気候変動を悪化させる選択肢ほど、それを選んだ時の負担が大きくなります。
気候変動を悪化させてしまうかを常に意識して削減努力を続けられる人は限られていますが、金銭的な負担を小さくしようとする人はたくさんいますから、カーボンプライシングはCO2排出と気候変動を自分事にします。排出削減を自分事にするカーボンプライシングは、社会全体で長期的に厳しい排出削減を続けるために不可欠なものです。
2カーボンプライシングを導入する方法:炭素税と排出量取引
カーボンプライシングを導入する方法として代表的なのは、炭素税と排出量取引です。炭素税も排出量取引もCO2を排出する人に金銭的な負担を求めますので、本質的には同じものです。
炭素税とは、ガソリンや電気の使用に対して課税する制度です。例えば、自動車はガソリンを燃やして走らせます。ガソリンの中には炭素が含まれており、燃やすとCO2が排出されます。ガソリンを購入するときに、含まれている炭素の量に比例した税を徴収すると、ガソリン代にCO2排出の費用が上乗せされます。このような税を炭素税といい、CO21トンあたりの炭素税(炭素税率)がCO2排出の価格となります。日本では、2012年から地球温暖化対策税という炭素税が導入されました。税率はCO21トンあたり289円とされており、これがCO2排出の価格です。ガソリン1Lあたりにすると0.76円です。
排出量取引は、主に企業を対象とする制度です。政府がある業種全体の排出量を削減するために排出量取引を導入するとすれば、以下のような制度となります。
① 削減対象となる業種(企業)全体のCO2排出総量の上限(目標)を政府が決め、その分の排出許可証を発行する。
② 発行した排出許可証は、CO2を排出する企業に配る。
③ 排出許可証は、企業同士で売買(取引)可能とする。
企業は、持っている排出許可証の分だけCO2を排出することができます。③からわかるように、CO2の排出削減を進めて排出許可証が余った企業は、排出許可証が足りない企業に売ることができ、売買の時の取引価格がCO2排出の価格となります。炭素税の場合と違って、排出量取引の下でのCO2排出の価格は変動します。制度の対象となる企業の排出量の合計に比べて排出目標量が少ないと、排出許可証を余らせる企業よりも足りない企業の方が多くなるため、排出許可証への需要が高まって高い価格で取引されます。詳しく知りたい人は「排出権取引とは 活用方法・メリット・注意点を徹底解説(自然電力の脱炭素支援サービスWebサイト)」を読んでください。
排出量取引は、EUで初めて導入されました。日本では、東京都や埼玉県で導入されています。国全体では、2026年度から排出量取引制度が導入されます。
3カーボンプライシングによってCO2排出削減が起こる仕組み
カーボンプライシングによってCO2排出費用の支払いが生じると、気候変動が自分事となり、排出削減が起こります。たとえば炭素税が導入されると、その税率の分だけガソリン代が高くなります。ガソリンをたくさん使用する人は、炭素税もたくさん支払わなければなりません。すると、「ガソリン代が高いから節約しよう」と考える人が増えます。炭素税率が高くなるほど1Lあたりのガソリン代が高くなりますので、節約したいと考える人はさらに多くなり、よりいっそう排出削減が進みます。これが炭素税によるCO2排出削減の仕組みです。
炭素税も排出量取引もCO2の排出に価格をつける制度であるため、排出削減が起こる仕組みは同じです。炭素税であれば、エネルギーを節約してCO2の排出量を減らせば税金を支払わなくて済みますし、排出量取引であれば、排出許可証を購入しなくて済みます。ここからは、消費者としての私たちの行動に関わりが深い炭素税について具体例を用いて説明をします。
4カーボンプライシングで人々の選択を変える:相対価格を変化させる
CO2の排出が気候変動の大きな要因になっていることは、広く知られるようになりました。いま自分がエアコンのスイッチを入れること、いま自分が自動車で移動しようとしていること、いま自分がどんな冷蔵庫を購入しようとしているかということ。こういったエネルギーの使用に関係する行動の選択が何十年後かの地球の平均気温に影響を与えることを、ほとんどの人が知っています。
だからといって、多くの人がすぐに環境に良い選択をすることは難しいことです。なぜなら、CO2排出とそれによってどれだけ気候変動を悪化させるかが自分事ではなく、しかも気候変動以外にも考えなくてはならないことがたくさんあるからです。今日は体調が良くないからエアコンを使いたいとか、雨が降る中でたくさん荷物をかかえての子どもの送迎は大変だから車を使いたいとか、共働きだから冷凍室の大きな冷蔵庫がほしいとか、優先順位は人それぞれです。
カーボンプライシングは、「気候変動以外にも考えなくてはならないこと」と「気候変動のこと」のメリット・デメリットのバランスを変えます。カーボンプライシングによってCO2排出の多い行動を選んだ場合にかかる費用を増やすと、CO2排出の少ない行動が選ばれやすくなります。
例えば、自宅から図書館に行くときの交通手段として、自家用車か路線バスを選べるとしましょう。
自家用車で行くとガソリン代はかかりますが、バス停ごとの停車がないので早く到着します。また、図書館のすぐそばに自家用車を駐車できると歩く距離が短く、雨の場合や、たくさん本を借りた場合の負担が小さくなります。ただし、自家用車では一人が1km移動するために127gのCO2を排出します(注1)。
バスで行く場合、一人の人を乗せて1km移動させるために排出されるCO2は63gですから、気候変動のことを考えればバスで行くべきです(注1)。しかし、バス停まで歩かなければなりませんし、バス停で停車するたびに時間がかかります。また多くの場合、自家用車のガソリン代より高い運賃がかかるでしょう。自分で運転しなくて良いという利点はありますが、おおむね不便である上に費用も多くかかるのでは、バスより自家用車を使いたくなるというものです。
ここで、炭素税率が上がって、ガソリン代の方がバス運賃より高くなったとしましょう(注2)。自家用車とバスのそれぞれの利便性は変わりませんが、費用面ではバスが有利になります。すると、「ガソリン代が高いから、不便でもバスで行こう」と考える人がこれまでよりも増えると考えられます。つまり、炭素税率を上げることで自家用車を利用するための金銭的な負担が増えるので、気候変動を意識しなくてもバスを選ぶ人を増やせると考えられます。
このように、カーボンプライシングには、気候変動のことを考えている人も、他に優先すべきことがある人も「お金がかからない方を選んだら気候変動を防ぐ選択をしていた」という機会が増えて、CO2排出量を減らす効果があるのです。
カーボンプライシングは、「規制」でも「罰金」でもないという点が重要です。一律に禁止する「規制」とは違い、カーボンプライシングが採用されている世界では、その分の費用を支払えばガソリンを使って車で出かけることができます。つまり、思いつきでアイスクリームを車で買いに行く人は減るでしょうが、急病のために車で病院にかけつけることまでやめなくてよいのです。どうしてもアイスクリームが食べたい人も費用(炭素税)さえ支払えばあきらめる必要はなく、責められるものでもないので「罰金」でもありません。必要性が低いと自分が判断すれば使用を控え、必要性が高いと自分が判断すれば使用できるという状態を実現するのが、カーボンプライシングの特長です。
5カーボンプライシングの効果の持続性は?
よくある疑問として、カーボンプライシングが導入されたとしても、CO2排出削減の効果があるのは最初だけで、そのうちにみんな慣れてしまって元に戻るのではないか?というものがあります。
カーボンプライシングの役割は、人々が意識しなくても気候変動を自分事とし、気候変動を防ぐ行動を選びやすくすることでした。炭素税が導入されて間もない頃は「ガソリン代には炭素税が入っているのだから、必要以上に車を使わないようにしよう」と意識していた人たちも、やがて炭素税込みのガソリン代がすっかり当たり前になると、気候変動のこともガソリン代が高くなったことも意識せず車で移動するようになるでしょう。
しかし、依然として炭素税は課されていますので、いまから車を使うかどうかという選択は、「ガソリン代の一部として炭素税を負担しながら車を使う」あるいは、「車を使わない=CO2を出さないから税を負担しなくて済む」の選択になっています。
このように、車を使うか使わないか=炭素税を負担するかしないかが自由に選べる状態が維持されている限り、人々が意識していようといまいと、課税していない状態と比べてCO2排出は削減されています。意識的か否かに関わらず、排出量に応じて税=排出の費用を負担する状態を保つことは、排出削減された状態を維持するために必要です。
さらに、カーボンプライシングを続けることには、CO2排出の少ない製品の開発や普及を促すという将来にわたる効果も期待できます。これから先ずっと炭素税がなくならないのであれば、自家用車を買い替える際にCO2排出の少ない車両を選びたくなる人が増えます。CO2排出の少ない車両はそうでない車両に比べて価格が高いものです。しかし、炭素税込みのガソリン代を抑えられるのであれば、その価格の違いは気にならなくなります。自動車メーカーも、高い価格であっても売れる見込みが持てれば、CO2排出の少ない車両の開発を進めるようになります。すると、次に自家用車を買い替えるタイミングでは、価格も性能も魅力的でCO2排出の少ない車両がもっと増えているかもしれません。
将来にわたってカーボンプライシングが続くという見通しは、私たちの将来を見据えた選択に影響をもたらしますし、将来CO2排出の少ない選択肢を増やすことにもつながっていきます。
6カーボンプライシングで社会を変える
ここまでは、カーボンプライシングと消費者としての人々の選択の変化について説明してきましたが、カーボンプライシングは企業―生産者の行動も変化させます。消費者のエネルギー節約志向を受け、生産者が省エネルギー型の製品の開発や生産に力を入れるようになることは前節でも触れましたが、それだけではありません。カーボンプライシングにより、省エネのために生産プロセスが変わり、それに関わる周辺の生産者の行動や、お金の動きも変化します。
カーボンプライシングが導入されると、CO2をたくさん排出して作られる製品やサービスほど、生産にかかる費用が増えます。増えた生産費用は、最終的には消費者への販売価格に上乗せせざるをえません。消費者は、同じクオリティの製品やサービスであれば、より安い方を購入しようとしますので、生産者はCO2をあまり排出せずに作れるように工夫します。CO2排出を抑えられる生産設備を整えようとすれば、設備を作っている別の生産者にも新しい工夫が求められますし、そのための投資も進むこととなります。こうした産業構造の転換とともに、化石燃料から再生可能エネルギーなどのクリーンエネルギーへの転換にもつながっていくと考えられます。
最初に述べた通り、現代社会においては、人々が行動の選択をするとき、同時にエネルギー使用の選択を行っていることがほとんどです。エネルギーの多くはCO2排出の原因となる化石燃料ですから、カーボンプライシング導入の影響は消費者一人一人、個々の企業だけでなく、産業全体、経済全体に及びます。自家用車か路線バスかの選択の例のように、ある日突然高い炭素税をかけてしまうと、急激な変化に対応しきれずに倒産する企業や失業する人も出てくることでしょう。またエネルギーは必需品であり、暖房や調理に使用するエネルギーの価格が上がってしまうことで、とくに低所得世帯の生活に深刻な影響を与えることが懸念されます。
こうしたさまざまなマイナスの経済的影響を緩和するために、炭素税収を活用する等の工夫が考えられます。日本より高率の炭素税を導入しているヨーロッパの国々では、炭素税収を財源として、企業の社会保障費削減(人件費負担を減らして多くの人を雇用できるようにする)、法人税減税(企業の投資縮小を防ぐ)、低所得世帯の所得税減税(家庭への影響を緩和する)を実施しています。社会全体として大幅な排出削減目標に長期的に無理なく取り組んでいけるよう、バランスのとれた制度を設計する必要があります。
カーボンプライシングの導入は、環境にやさしい選択を無意識にできるようにするために有効な手段です。気候変動問題に危機感を持つこと、自分の行動とのつながりを意識することは重要ですが、そうでない人たちの行動も環境にやさしいものに自然となっているような社会が実現することを願っています。
- 注1
- 自家用車とバスの輸送量あたりのCO2の排出量は「運輸部門における二酸化炭素排出量(国土交通省)」より、2023年度の値を参照しています。 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html
- 注2
- 多くのバスの燃料である軽油はガソリンとほぼ同じくらいの炭素を含んでいますので、炭素税率が上がることによってバス運賃も値上がりすると考えられます。しかし、乗客を一人輸送する場合のCO2排出量は自家用車より少ないため、一人分のバス運賃の値上がり幅はガソリン代の増加よりも小さいと考えられます。
さらにくわしく知りたい人のために
- 第1版:2025-07-14
第1版 岡川 梓(社会システム領域 経済・政策研究室 主任研究員)