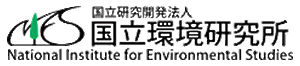目指せ!世界に「さきがけ」た海洋モニタリング観測 ~外部資金採択テーマの紹介①~
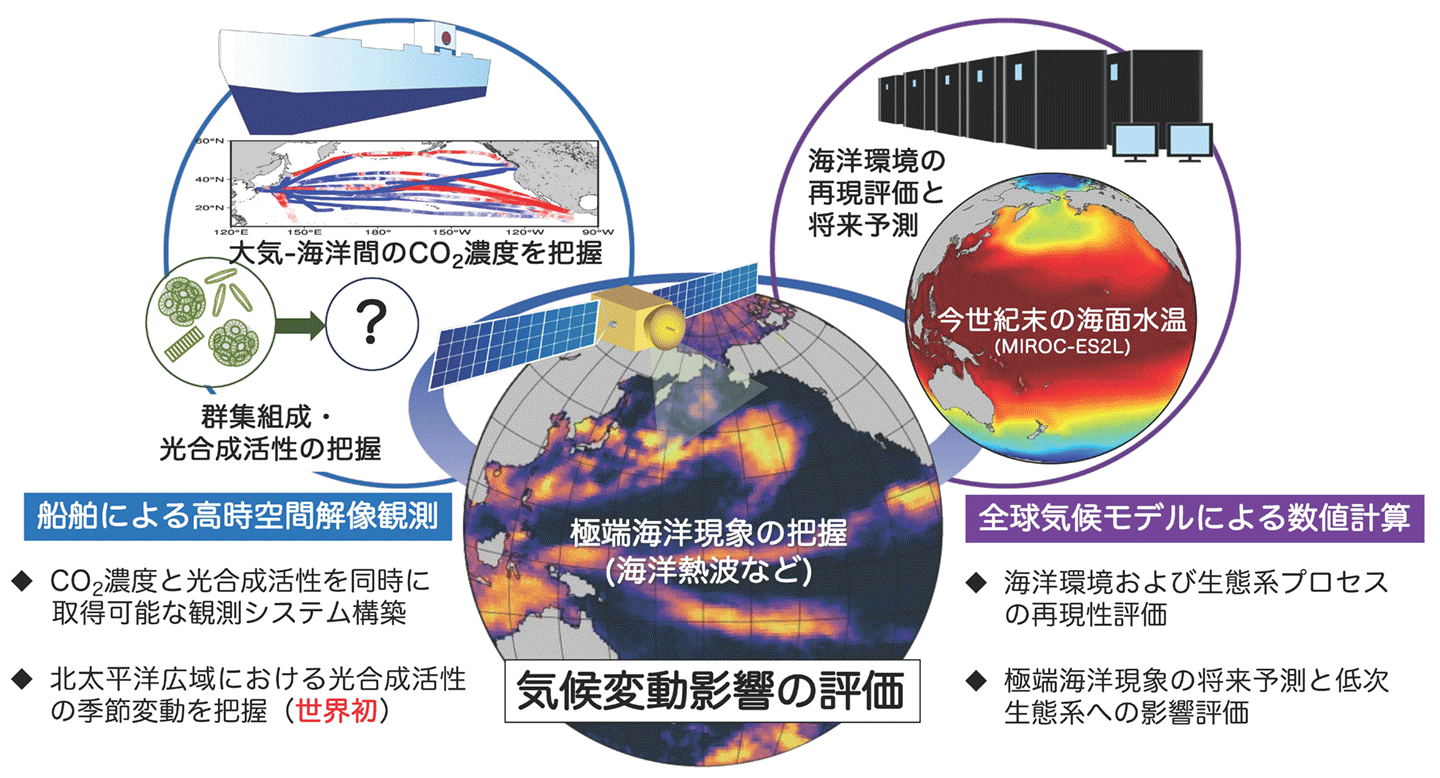
・研究課題名は何ですか。
「気候変動影響評価に資する光合成活性の高時空間観測システムの構築」です。光合成活性というのは、植物や微細藻類(植物プランクトン)の光合成活動を把握する上で重要な指標のひとつになります。
・どんな研究ですか。
国立環境研究所(以下、国環研)の日本-北米間を航行する船舶プラットフォーム(協力商船)による北太平洋の高頻度観測を活かし、近年頻発する海洋熱波をはじめとする極端海洋現象、大気-海洋間二酸化炭素(CO2)交換、植物プランクトンの光合成活性(生理状態)の相互作用の解明とそれらの海洋炭素循環への影響を評価するための高時空間観測システムの構築を目指しています。
・一緒に研究を行う(共同研究する)他の研究機関がありますか。
2024年4月から水産研究・教育機構や京都大学化学研究所と共同研究契約を結んでいます。本来、戦略的創造研究推進事業「さきがけ」は研究者が個人で研究を行う個人型研究ですが、今回採択された研究領域『海洋バイオスフィア・気候の相互作用解明と炭素循環操舵』では個人の提案課題の枠を超えた、さきがけ研究者間での交流や共同研究を支援する体制が非常に充実しています。今年6月の研究船観測では、上述の2機関に加えて長崎大学や東京大学大気海洋研究所の研究者と共に船上観測・実験を行なう予定です。
・準備で苦労したことはなんですか。
大学や他の研究機関で実施しているような外部資金獲得支援(研究提案書の添削、模擬面接等)の枠組みが国環研ではほとんど整備されていないため、応募に際しての情報取集を始め、提案書や面接資料に対する客観的な目線でのブラッシュアップに苦労しました。他の研究機関の方達から「URA*1から申請書の添削が返ってきた」とか「今日、模擬面接の日だ」といった声が聞こえてくる度に不安な気持ちにもなりました。一方、周りに助けていただき、苦労が減ったこともありました。私は絵心がないため、毎度ポンチ絵等の作成に非常に時間を取られます。しかし今回は地球システム領域地球環境研究センター研究推進係によるサイエンスイラストレーション作成支援で、効果的なポンチ絵の作成を手伝ってもらいました。結果として提案書作成に効率的に時間を割くことができ、その点が今回の採択に大きく役立ったと個人的には思っています(研究推進係の吉村さんに大感謝です!)
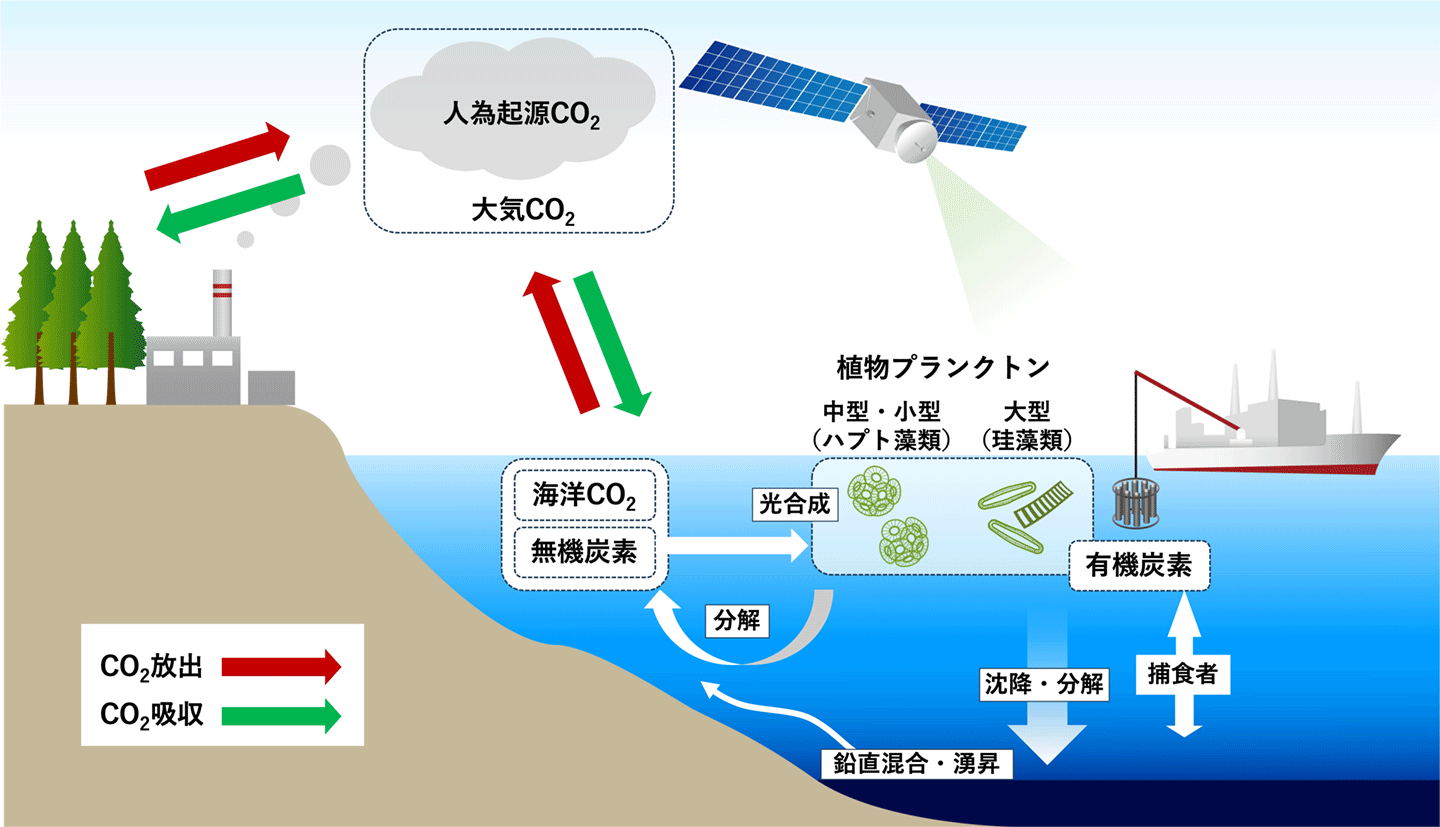
・どんな新しいことがわかりそうですか。
今回の研究では海の表層に生育する植物プランクトンの光合成活性に注目しているのですが、この情報を衛星観測で直接得ることは出来ません。そのため、光合成活性の詳細な季節変動性を広域で把握することはこれまで困難でした。本研究で構築する協力商船を活用した新しい観測システムを使うと、北太平洋における植物プランクトンの光合成活性の季節変動を、植物プランクトンの群集組成を表す情報とともに長期連続的に観測することができます。さらに、これらの情報を国環研が以前より取り組んできた大気-海洋間CO2交換量と同時に把握できるようになるため、広大な海洋におけるCO2吸収量が気候変動に脆弱とされる植物プランクトンの変化を介してどのように変動しているか、そしてそれが将来どのように変化する可能性があるかを理解できるようになることが期待されます。また、このような取り組みは世界初のため、まさに世界に「さきがけ」た試みになります。
・今後の抱負
海盆スケール*2で得られる季節的なCO2濃度変動と光合成活性データは、今年2月にNASAによって打ち上げられた地球観測衛星(PACE:Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem mission)の次世代海色センサ(OCI:Ocean Color Instrument)と組み合わせることで、新しい炭素固定量推定手法の提案にも貢献できると考えています。また、現場観測データとモデルを組み合わせた次世代気候モデルの発展を支える基礎データとしての活用も期待できます。このような連携研究の先にある確度の高い海洋物質循環の将来予測は、今後減少や枯渇が危惧されている漁業資源の維持・管理など社会的な影響を強く持つ分野へも貢献できると信じています。国環研の船舶プラットフォームを活用し、これまでのモニタリング体制を更に発展させていけるよう、精一杯課題に取り組みたいと思います。
・上司から一言
国環研の海洋モニタリングはこれまで海洋表層における無機的なCO2の交換に主眼を置いてきましたが、本研究によって有機的な光合成活性の理解を通した海洋全体の炭素循環の解明へと貢献の幅を広げることになります。世界でも数少ない協力商船による観測プラットフォームの「長期・高頻度」という特徴を最大限に活かした本研究が海洋物質循環研究の新たなページを開いてくれることに期待しています。