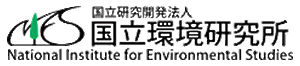国立環境研究所・琵琶湖分室-ガンバッてます-
1. はじめに
国立環境研究所・琵琶湖分室は、2017年4月、「政府関係機関移転基本方針」に基づき、滋賀県・琵琶湖環境科学研究センター内に設置された。「地方創生推進交付金」を活用した研究プロジェクトを、滋賀県・琵琶湖環境科学研究センターをはじめとする関係研究機関と共同で進め、国民的資産である琵琶湖の保全と再生のために、湖沼の水質・底質・生態系を見渡した学際的な研究を行っている。
さらに、研究成果の活用・実用化を図る地方創生プロジェクトに参画し、湖沼のもたらす恩恵を享受できる地域社会の実現に貢献することを目指している。本稿では琵琶湖分室の業務のうち、主に研究活動について紹介する。
2. 琵琶湖の現状とは
琵琶湖(北湖と南湖からなる)は我が国最大の湖であり、近畿圏の人々の暮らしと経済活動を支える貴重な水資源である(図1)。多くの固有種が生息する重要な生態系と豊かな水産資源に恵まれている。2003年以降、富栄養化は抑制されて、琵琶湖の水質は良くなっていると認識されている。
とは言いつつ、琵琶湖はいまだに多くの問題を抱えている。アオコの発生(局所的に発生)、カビ臭による利水障害、湖内部負荷による水質悪化(有機物[COD]濃度が低下しない)、外来魚の繁殖(2013年まで減少、2014年に増加、その後横ばい)、南湖での水草の異常繁茂(2007年以降)、侵略的外来水生生物(オオバナミズキンバイ等)の繁茂(2013年以降)、在来魚類の著しい減少(魚類は1992年頃から減少傾向、アユ不漁は2015年以降)等の異変が現れてきた。琵琶湖の水環境や生態系は、現在、必ずしも健全な状態にあるとは言えないだろう。
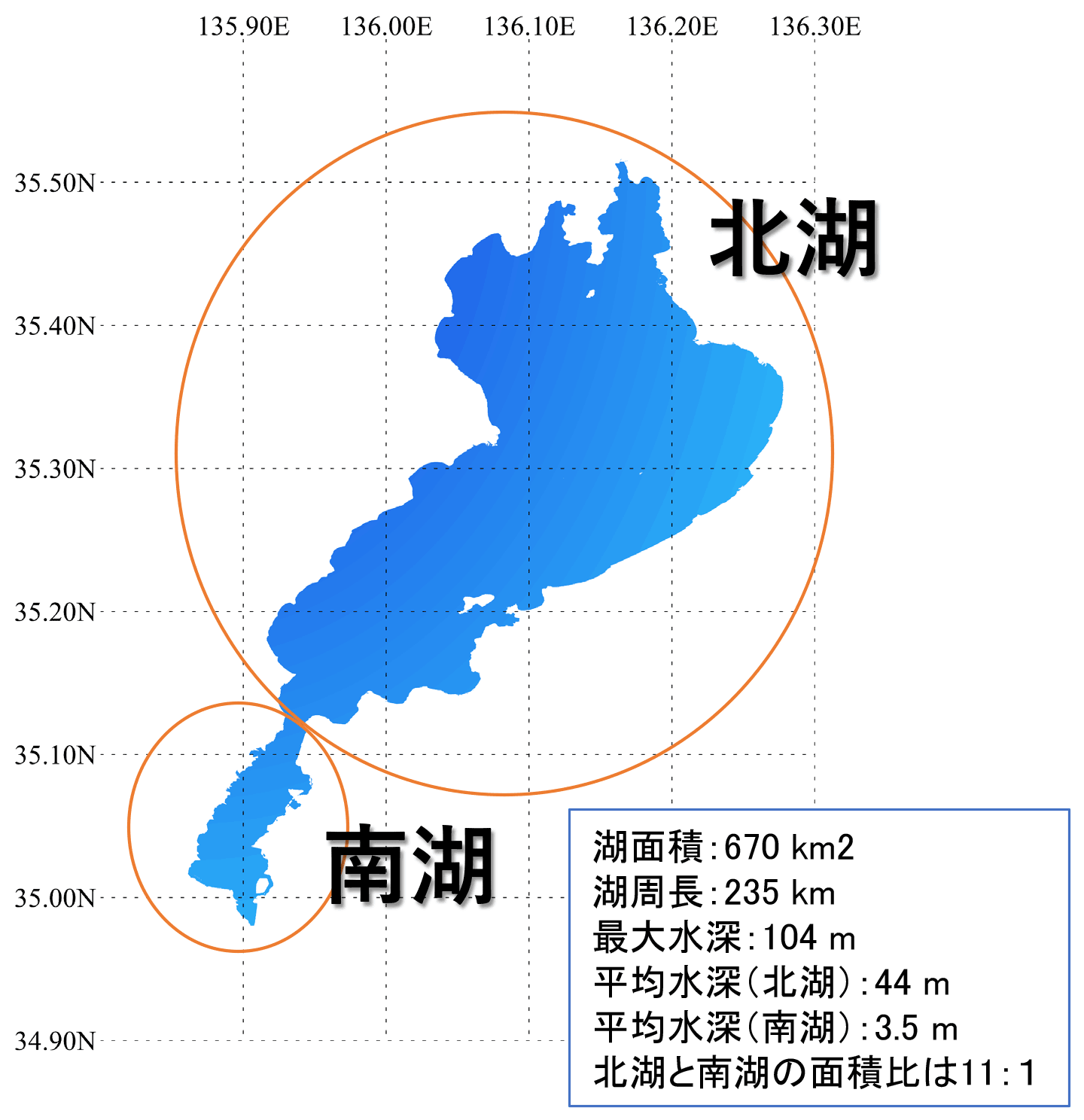
3. 琵琶湖分室の研究(地方創生推進研究)
琵琶湖分室では、健全な琵琶湖の水環境の保全・管理・再生を図るために、「水環境」と「生態系」の二つの観点から、滋賀県琵琶湖環境科学研究センター等と共同で二つのプロジェクト研究を実施している。新規性の高い測定・評価手法等と地道な調査・モニタリングを駆使するアプローチで、具体的な成果を得ることを目指している。
(1)健全な水環境保全のための水質・湖底環境に関する研究
琵琶湖における有機物収支の把握と底泥環境の評価について、以下の研究を実施している。①湖内での有機物の供給源である藻類生産や細菌生産の測定・評価、②有機物の特性に基づいた有機物収支の把握、③底泥の酸素消費量や栄養塩等の底泥溶出の測定法の開発と変動評価、④底泥環境変化の水質・生態系に及ぼす影響評価、⑤底泥環境の適切な改善手法の検討。
(2)湖沼生態系の評価と管理・再生に関する研究
水草繁茂や在来魚の生息分布の変化の要因解析を行っている。具体的には、①保全上重要な場所や対策優先度の高い場所の抽出、②在来魚回復のための対策の検討、③在来魚の資源回復を目標とする好適な産卵・生育場所が備える環境条件の解明、④卵から成魚の分布データと環境因子との関連性に基づく保全策立案、⑤環境DNA等による魚類等の分布データの効率的取得手法の開発と実測分布データとの比較検証、を進めている。
4. 研究成果
本セクションでは、トピック的に興味深い成果を二つ紹介する。
(1)細菌生産速度の30年にわたる変化 (Tsuchiya et al. 2020)
水圏生態系において、細菌は物質やエネルギー循環に対し重要な役割を果たしている。微生物食物連鎖と生食食物連鎖を介して物質循環を駆動させている。しかし、我が国では湖沼における細菌生産速度(BP)のデータは払底している。その理由は、BP測定法は一般的に放射性同位体を使用するが、我が国では放射性同位体の使用が厳しく制限されているためである。本研究では、琵琶湖北湖で過去に実測された直接比較可能な数少ないBPデータと最近取得したデータとを比較して、BPの30年間にわたる変化を明らかにすることを目指した。
具体的には、放射性同位体を使うチミジン法によるBPデータ(1986年4~10月)、比増殖速度データを活用したデータ(1997年6月~1998年6月)と放射性同位体を全く使用しないデオキシアデノシン法による実測BPデータ(2016~2017年、本研究)を比較した。
結果として、1986年のBP(水深0~10 m)は2016~2017年と比較して4.6倍高く,BPはこの30年間で1/5(22%)にまで低下したことが示唆された。一方、1997~1998年のBPも2016~2017年より顕著に高く、2016~2017年の2.1倍であった。つまり、この20年間で約半分に低下したと推察された。2016~2017年の値を1として、過去30年間におけるBPの相対生産速度をプロットした(図2)。BPは1986年から10年後の1997~1998年で40%、30年後の2016~2017年で22%まで低下していた。
琵琶湖北湖の細菌生産速度はほぼ指数的に減少している。細菌生産の大幅な低下を考えると、細菌は藻類由来の溶存有機物を栄養基質(餌)として利用するため(微生物ループ)、藻類生産も低下傾向にあると推測されるが、不思議なことにそのような傾向は観測されていない。さらなる研究の進展が望まれる。
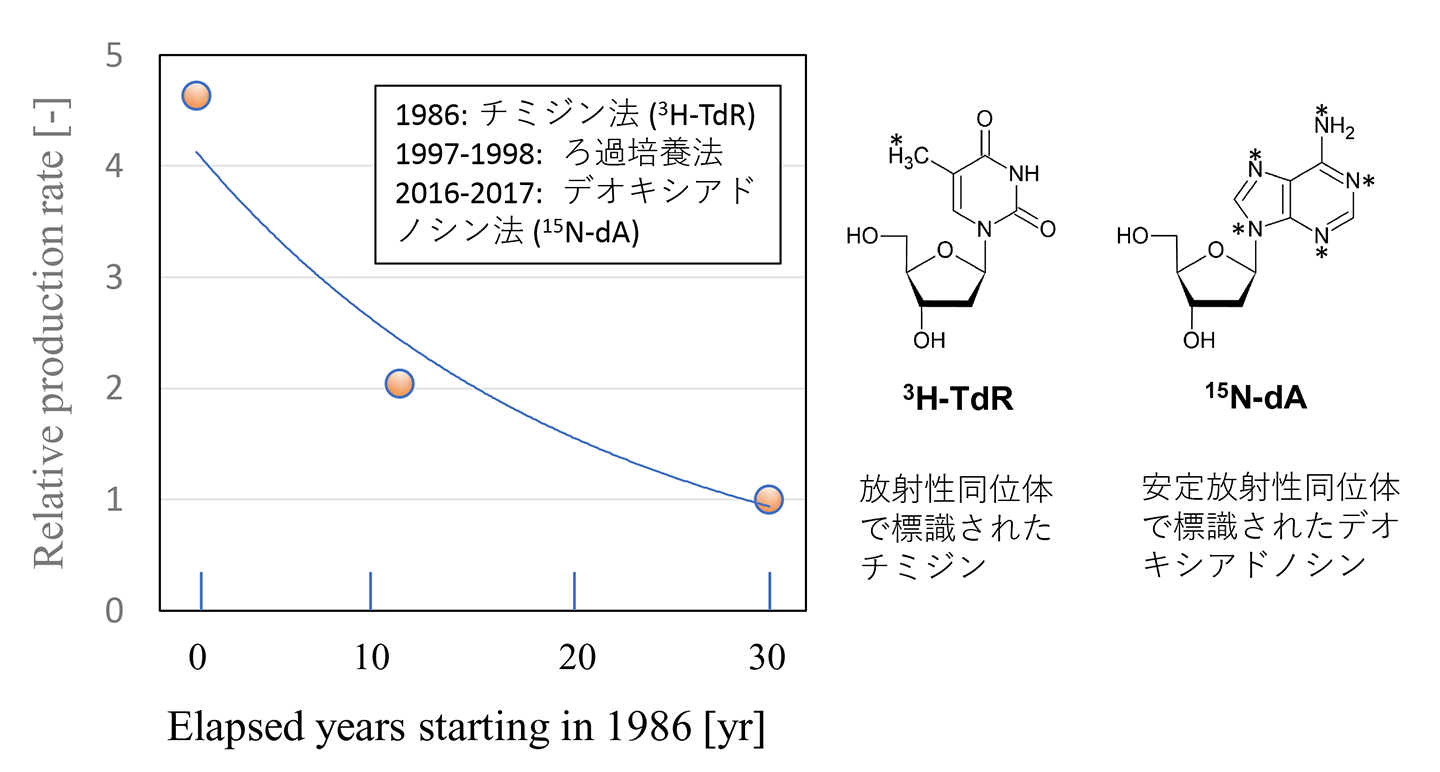
(2)琵琶湖湖岸の植生帯と流入河川・水路におけるコイ科魚類の産着卵調査(馬渕ら 2020)
ホンモロコ、ニゴロブナ、ゲンゴロウブナ、在来コイは、琵琶湖固有のあるいは琵琶湖にしか残存していない貴重な魚類であり、滋賀県の伝統的な食文化を支える食材である。しかし、これらの魚種の漁獲量は1980~1990年代以降激減している。
漁獲量激減の原因として、産卵のための回遊を阻害する土地改変や人為的水位調節が考えられている。これらの魚種は、春になると産卵のために沿岸や内湖に移動し、その場所にある植生に卵を産み付ける。1970年代開始の湖岸堤建設や圃場整備以降は、産卵適地が広範囲で消失している。産卵可能な場所は、現在、湖岸堤の本湖側の植物帯や造成ヨシ帯と、流入河川・水路等に限られている。
産卵場所を再生・保全していくには、湖岸植生帯や流入河川・水路が、各魚種によってどのように利用されているかの実態を明らかにすることが重要である。そこで我々は、湖岸や流入河川・水路等で、4~8月の産卵シーズンを通して産着卵を採集し、DNA種同定により、魚種ごとの産卵傾向の違いを明らかにすることを試みている。
南湖全体におけるホンモロコの産卵場所の地理的広がりについて紹介する。南湖にはかつて琵琶湖全体のホンモロコの65%が産卵していたという推計があるほど、本種の繁殖にとって南湖は重要な場所であった。しかし、1996年頃には南湖での産卵は全く観察されなくなった。本種は水際のヤナギ(湖畔ヤナギ)の根の、水面近くの部分に好んで産卵する。瀬田川洗堰の新たな水位操作(1992年以降)や湖岸堤建設による湖岸産卵地の破壊(1975~1991年)が観察されなくなった原因だと考えられる。
そこで我々は、2019年の4~5月の産卵盛期に、湖畔ヤナギの根に産み付けられた卵を採集してホンモロコ産卵の地理的な分布を調べた(図3)。結果として、南湖ほぼ全域でホンモロコ卵の存在が確認された。60年ぶりの観察結果である。

今回紹介したトピックの他にも興味深い成果を得ている。例えば、①これまで測定できなかった琵琶湖北湖のリン酸態リン濃度分布、②瞬時に藻類生産速度を測定できる高速フラッシュ蛍光光度法の開発、③小型ガラスバイアル(密閉容器)を用いる底泥酸素消費量測定法の開発、④琵琶湖水系に生息するイシガイ科二枚貝のDNA同定(貝を傷つけず糞を使う)、⑤ビワマス成熟雄に関する考察、⑥遠隔計測による水草繁茂監視手法(ドローンも利用)、⑦琵琶湖全層循環シミュレーション解析などがある。詳細は琵琶湖分室HPで(http://www.nies.go.jp/biwakobranch/)。コイの目線で琵琶湖の中が見える映像もあります(コイ目線のびわ湖映像アーカイブス https://www.nies.go.jp/biwakoi/index.html)。これは面白いので是非ご覧いただきたい。
5. 水環境ビジネスへの貢献
研究者にとって成果の活用・実用化はとても難しいことだが(関心の薄い人が多いというか)、琵琶湖分室では「しが水環境ビジネス推進フォーラム研究・技術分科会」等に積極的に参画して活用・実用化への貢献を図っている。このたび、分室が島津製作所と共同開発した全有機炭素検出サイズ排除クロマトグラフィー装置(SEC-TOC)の市販化が決定した(水に溶けている有機物の分子サイズを測定する装置。分子サイズと分解性に関係あり)。ガンバリました!