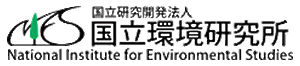地球環境研究センター30周年企画 時の証言者たちに聴く(2):地球環境研究の30年—モデル研究はどこから来て、どこへ行くのか
地球環境研究センターは、2020年10月で発足30年を迎えます。このインタビューや対談では、地球環境研究センターが誕生した1990年から現在に至るまでの地球環境研究の国内外の動向やさまざまな研究活動を振り返り、それらに直接深くかかわられた方々からご経験や考えをうかがい、今後の30年を展望していくことを目的にしています。
第2回は、甲斐沼美紀子氏(地球環境戦略研究機関(IGES)研究顧問、元国立環境研究所室長)と江守正多(地球環境研究センター副センター長)が、予測結果がIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書にも掲載されたスーパーコンピュータによる地球環境の将来予測の30年間の進展と今後の展望などについて対談しました。なお、両名は2007年にノーベル平和賞を受賞したIPCCに貢献しました。
進展の過程は
江守:地球環境研究センター(以下、CGER)は1990年10月1日に発足し、今年で30年になります。この機会に過去30年を振り返り、今後30年に向けて何をしたらよいか甲斐沼さんと考えたいと思います。
甲斐沼:1990年のCGER発足時、私は、総括研究管理官だった西岡秀三先生に10月1日の開所式で紹介するものを依頼され、サクラの開花予測を作成しました。当時は気候モデルを利用したわけではなく、気象庁のデータをもとに温暖化したときの開花を予測しました。西岡先生は、「サクラは出会いの歌によく使われているけど、そのうち別れの歌に入るようになるだろう」とおっしゃっていました。今は東京では3月に満開になる日もあるので、本当に別れの歌に使われるようになりました。
江守さんにはスーパーコンピュータ(以下、スパコン)による地球環境の将来予測の進展と今後の展望についてお聞きしたいと思います。江守さんは30年前から気候モデルに携わっていたのでしょうか。
江守:30年前は大学生ですから、まだ気候モデルは知りませんでした。卒業論文のときに地球温暖化問題の科学的な側面に興味をもち、国立環境研究所(以下、国環研またはNIES)の研究者に相談に来ました。卒業後、東京大学の教養学部の大学院に進学しましたが、温暖化に関する研究を行いたかったので、引き続き、半分アルバイト、半分居候の学生みたいな感じで、国環研にはよく来ていました。
気候モデルについて、後から聞いた話では、1992年に国環研にNECのSX-3というスパコンを入れることになったので、1991年に設立された東京大学気候システム研究センター(以下、CCSR。現在の東京大学大気海洋センター(AORI))では、国環研のスパコンを利用して気候モデルができる人を育てることになったそうです。東京大学から国環研に来た沼口敦さん(故人)と東京大学の山中康裕さん(現北海道大学教授)が、大気と海洋のモデルをそれぞれ開発して、それを結合して温暖化実験が始まりました。
甲斐沼:1988年に設立された気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の評価報告書にCCSR-NIESのモデル結果は掲載されましたか。
江守:CCSR-NIESモデルはIPCCの第3次評価報告書(TAR、2001年公表)のときに大気と海洋を結合して温暖化実験の結果を提出し、グラフに線を1本載せたのが精いっぱいでした。
その直後の2002年に海洋研究開発機構(JAMSTEC)に地球シミュレータができました。理化学研究所の「富岳」というスパコンが演算スピードを競う世界ランキング「TOP500」において世界一を久しぶりにとったというのがニュースになっていますが、地球シミュレータは2002年に世界一を獲得し、2004年までは抜かれなかったという当時としては画期的なスパコンでした。
2007年公表の第4次評価報告書(AR4)に向けては、世界最高速の地球シミュレータで最高分解能の結合モデル実験を行うチャンスに恵まれたので、それに向けてモデルを開発して、シミュレーションを行いました。その結果の解析により論文もかなり充実して、かつ海外との共同研究が増えました。
甲斐沼さんはCGER発足のころから統合評価モデルの研究をされていたのでしょうか。
甲斐沼:私は1990年に国環研に地球環境研究グループができて、地球温暖化問題にかかわり始め、温室効果ガス排出や温暖化対策のモデル開発を進めることになりました。また、排出量が伸びているアジア地域でも使えるモデルを開発しようということで、アジア太平洋統合評価モデル(AIM)の開発に携わりました。
1993年にウィーンの国際応用システム分析研究所(IIASA)で開催された温暖化の会議で知り合ったWeyant教授がIPCC第2次評価報告書の総括代表執筆者(CLA)をされていて、統合評価モデルをまとめておられました。そのモデル評価のなかにAIMも入れていただき、データ提供し、モデルグループと交流をもつようになりました。
IPCCは2000年に当時AIMのリーダーだった森田恒幸さん(故人)がかかわった排出シナリオに関する特別報告書(SRES)を出しました。その後2011年に代表的濃度経路(RCP)シナリオを発表し、第5次評価報告書(AR5)で使われました。

温暖化予測と社会経済シナリオの認識が変わった30年
江守:2001年のIPCC TARに載るように温暖化実験をやって提出したころ、気象学会のなかで、予測しても検証ができない100年後の温暖化実験は科学的な研究ではないと思われていた雰囲気があったのを覚えています。温暖化実験に携わっている人たち自身も、確かにそうかもしれないと思いながら、行政的に必要だから行っているという感じが強かったような気がします。
しかし、そのころすでにアメリカやイギリスの研究機関では、多くの研究者が直接検証できないものをいかに科学にするかというのを真剣に考えていました。今では日本でも、温暖化予測研究において、いかに不確実性を見積もるか、現実に近づけるかというのをみんなが重要な研究テーマであり科学的だと思うようになっているので、30年でものすごく変わったという感じがします。
甲斐沼:今のお話を聞いて、自然科学と社会科学の違いを感じました。物理化学で解明する明確な対象があり、それを探求するのが自然科学なのかなと思います。一方、われわれの社会科学は、わからないことをどう予測するかということが課題です。将来をいろいろ想定してシナリオ(甲斐沼美紀子「地球環境豆知識(30)シナリオ」地球環境研究センターニュース2014年7月号参照)を描いていくのですが、どれが実現できるかはわからないけれど、こういう社会にもっていきたい、それにはどうしたらいいかというのを考えます。
江守:温暖化の予測が科学なのかという議論が気象学会であったころ、失礼ながら、気象学の人たちは、社会経済シナリオの研究は科学なのか、研究なのかと、もっと思っていました。シナリオを何本も出されて、気候モデルをたくさん計算しなくてはいけなくて、データも多くて面倒なのに、それは何の意味があるのかと言いながらやっていました。僕の場合は、幸いなことに国環研に甲斐沼さんたちがいらして、そのお仕事を意識しながら温暖化予測の実験を行えたので、シナリオの意義を理解するのが早かった気がします。
甲斐沼:SRESには4つシナリオがあり、そのうちの一つのシナリオはさらに3つに分かれています。どれか1個にしてほしい、どれが本当に起きるのかとよく聞かれました。どれも同じように起きやすいということをなかなか理解してもらえませんでした。
江守:現在は一番起こりやすいことを研究すればいいわけではないと理解しています。これは本当に起こるかどうかわからないけれど、起きてしまったら大変だということを研究しなくてはいけないという発想は、最近よく聞くようになりました。
データ管理には専門家が必要な時代に
江守:IPCCにTGICAという組織があり、気候モデルと影響評価と統合評価の人が集まって、次のシナリオについて検討していました。2004年くらいからAR4に向けたTGICAの活動に参加した僕は、日本の気候研究者のなかではおそらく、気候モデルと影響評価と統合評価の連携のもっとも進んだ国際的な情報を得る機会があったと思います。その後TGICAはデータ提供を統括するTGDATAという組織になりました。
甲斐沼:データはとても大切です。1993年に統合評価モデルを始めたとき、いろいろなモデルの排出量データを調べてデータベースを作成し、報告書を出して、それをIPCCに提供しました。さらに新しいデータを積み重ねて、統合評価モデルの結果を入れて、AR4のときには国境研とIIASAの両方にそのデータを置きました。
その後残念なことに国環研は人手不足でフォローアップできず、IIASAにデータ専門の人がいて発展させてくれています。現在、統合評価モデルのグループが作ったデータは共通のフォーマットでIIASAに出すことになっており、そのデータを分析したり、新しいデータ入れたりして、将来の新しい技術を比較検討するのに役立っています。
江守:最初の頃、国環研でデータベースの作業を引き受けて国際的な信用を得ていったプロセスは、バイタリティがあってすごいと思いましたが、かつてのデータ量と、現在、IIASAの扱うデータベースとは桁が違うでしょう。気候モデルも同様です。グループの数が増え、計算が高解像度になるのでデータが膨大になります。また、実験の数が多くなり、気候モデルの場合はとくに、データのインフラはプロが扱わないと回らない状態です。
計算のプログラミングのテクニックも片手間では追いつかなくなっています。SX-3で大気モデルを開発していたころは、自分でベクトル化効率を上げるやり方を取得して喜んでいました。そのうち並列化計算が必要になり、たくさんのCPUで別々の領域を計算して、結果をやりとりするプログラミングが不可欠になってきました。地球シミュレータでとくに重要になったので、システムエンジニアに並列化計算のプログラミングを手伝ってもらうことになりました。
計算機科学と気候科学を共同で進めなければいけない時代がきたと感じたのが、地球シミュレータのころです。最近はますますそうなってきていると思いますし、データもデータの専門家が取り回しを考えて、ストレージの設計から行わないと気候業界のデータがきちんと研究者に流通しないという時代になっているという感じがします。

気候感度の幅はなかなか狭まらない
甲斐沼:江守さんは2021年公表予定のIPCC AR6にも執筆者として参加されています。私の興味としては気候感度*1がどのくらいになるかということです。今後、気候感度はどういうふうに見積もられていくのでしょうか。
江守:気候感度は、過去の気候やプロセスの再現性が一番現実に近くなるように気候モデルを改良して、結果的に感度を調べてみると何°Cだったというふうにわかるものです。どこのパラメータが変わると感度も変わるかが、ある程度わかってきましたが。現在、海外メディアでは、感度が高い新しいモデルが増えたことが話題になっています。いくつかの気候モデルの最新バージョンでは感度が5°Cくらいになっていて、現実の地球がそういう感度である可能性が高いということを意味しているのかが、大きな問題になっています。
そういう結論がAR6に出るのかどうかというのは守秘義務があるのでお話しできませんが、そうではないという論文も出てきています。感度が高いモデルは過去の再現性がよくないなど、モデルと観測データを組み合わせた評価が活発に行われています。30年前と比較して関連する研究は蓄積され理解が進んではいますが、必ずしも感度の幅は狭まっていかないですね*2。
30年後何ができるか
甲斐沼:最後に、地球環境の将来予測について、これからの30年はどんなふうに進んでいくと思いますか。
江守:気候モデルの研究については、コンピュータの役割がこれからも大きくなっていくでしょうから、解像度も上がって、100年の計算を何本も走らせたり、1000年の計算を走らせたりできるようになっていくでしょう。これまでの延長でのコンピュータの性能向上による予測の詳細化、高度化の過程は今後も続くと思います。
他方、膨大になる一方のデータ処理の問題にはみな頭を抱えています。かつて、地球シミュレータで計算したデータを大きなハードディスクに入れて、解析を担当する国環研に宅急便で送っていました。インターネットでデータを転送するのでは時間がかかったからです。インターネットで大容量のデータを転送するのは今後も大変なので、計算した場所にデータを置き、そこで解析もできるようにするという方向にだんだんいきつつあります。
また、予測がどんなに詳細化しても、不確実性をどういうふうに社会における意思決定に使うかという問題は残ります。特に適応策の検討が日本でも他の国でも本格化しているので、地域的な細かい気候予測を行い、防災インフラの設計や都市計画の考案に役立てようという動きがありますが、予測の不確実性はゼロにはなりませんし、別のモデルで計算すると違う結果になるということはまだしばらく起こると思います。それをどう社会の意思決定に使うかという課題は今後も続いていくだろうと思います。
甲斐沼:気候モデルから重要な情報をいただいて、このままでは大変なことになるから排出量を何%削減しましょう、対策をしましょうというところまできました。気候モデルは目標を出すまでは重要な役割を果たしたと思います。今後は、適応とも組み合わせていく方向になるのでしょうか。
江守:今お話ししたのは、単純に技術的にコンピュータが大きくなると気候モデルで何ができるかということで、それが必要かどうかというのはおっしゃるとおり別の問題です。30年後は2050年です。世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて1.5°C以内に抑えることを目指すなら、2050年に世界の正味の排出量がゼロになっていなければいけないわけです。それが実現していて、RCP8.5(地球温暖化対策をとらず、排出量が増加し続けた場合)にはぜったいにならないから、気候モデルでそんな計算はしなくていいというのが一番いいですね。
僕からも甲斐沼さんに統合評価モデル研究、シナリオ研究の30年後をうかがってみたいです。
甲斐沼:日本の100くらいの自治体が「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明(https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html)」をしています。そこで私たちは、実際に何をすればゼロエミッションを実現できるのか、具体的なシナリオを描くことができ、30年後にはそれが実現しているといいです。1990年代に研究を始めたころ、モデルを使って今こういう技術があるからここまで減らせるはずだというシナリオを描いていましたが、地域の担当者が使えるようなモデルができて、いろいろな対策が実行されるといいです。
自治体だけではなく、2100年にゼロエミッションにするロードマップを出した鉄鋼業界や、石油にとって代わるものを作るという石油化学工業の話が出ています。そういったことを進められるような社会はどうあるべきか、またどういう社会だったらそういうことが進むのか、そして、ゼロエミッションに向けて具体的に何ができるのかというシナリオを作っていけたらと思います。