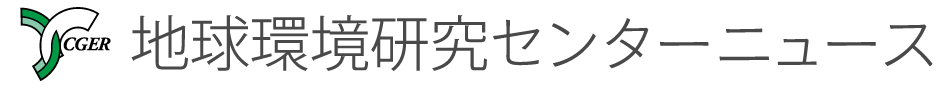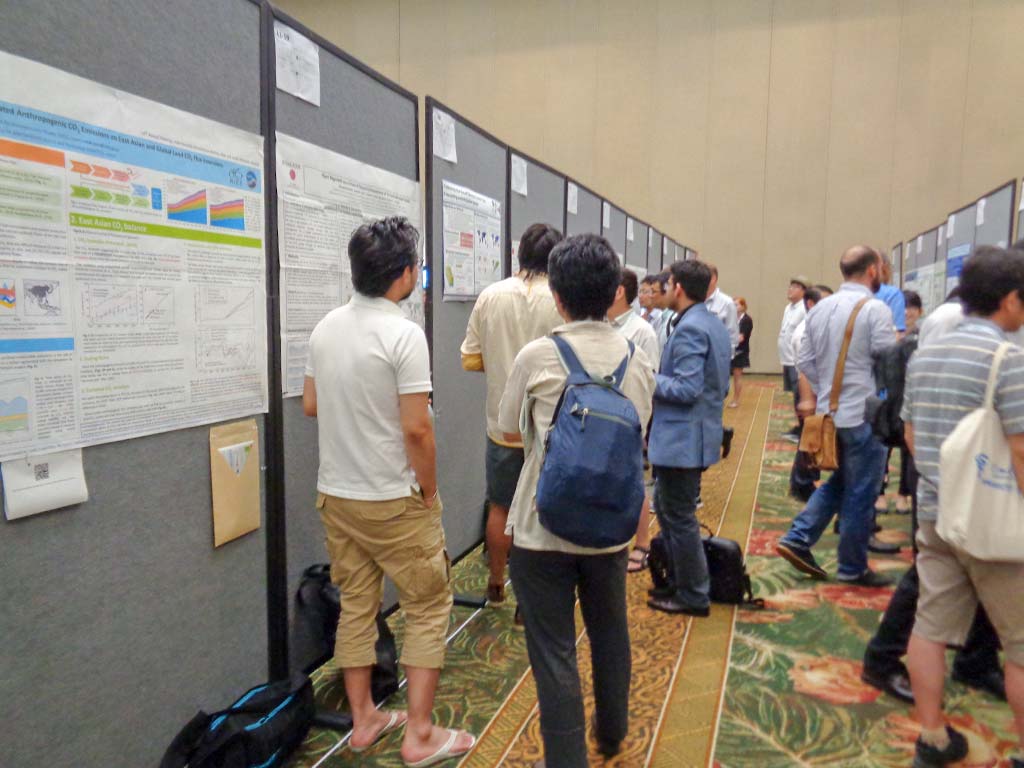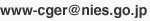2018年9月号 [Vol.29 No.6] 通巻第333号 201809_333001
アジア・オセアニアとアメリカにおける炭素循環研究の最近の動向 〜AOGS Annual Meeting参加報告〜
1. はじめに
2018年6月4〜8日の5日間、ハワイ・ホノルルにおいて開催されたアジア・オセアニア地球科学会(Asia Oceania Geosciences Society: AOGS)の年会に参加した。AOGSはその名の通り、アジア・オセアニア地域における地球科学を対象とした学会であり、アメリカ地球物理学連合(American Geophysical Union: AGU)や欧州地球科学連合(European Geosciences Union: EGU)などと並ぶ国際的な組織である。このAOGSの年会は事務局のあるシンガポールとそれ以外の場所で毎年交互に開催されており、前回の2017年はシンガポール、前々回の2016年は北京で開催された。今回のホノルルでの大会は例年に比べ参加者が大幅に増加し、特に国内ということでアメリカからの参加者が多く見られた。そのため、アジア・オセアニア域に限らない世界の研究動向を把握することが出来た。筆者は、物質循環系(Biogeosciences: BG)のKamide Lecture(若手研究者によるレクチャー)を行った。このレクチャーでは、自身が行ってきた研究について、特に航空機観測CONTRAILを用いた二酸化炭素(CO2)フラックスの逆推定に関する話題を中心に講演を行った。また、BGのアジアモンスーンセッションにおいて、環境研究総合推進費2-1701「温室効果ガスの吸排出量監視に向けた統合型観測解析システムの確立」のもと実施しているアジア・西太平洋上空におけるメタン濃度変動の解析についてポスター発表を行った。このように筆者は温室効果ガス、炭素循環を主な研究対象としているが、以下に、これらに関連する講演で印象に残ったものについて報告を行う。
2. ハワイの長期観測
大気のCO2を研究対象としている者にとってハワイは馴染み深い場所である。それは、故David Keeling博士が始めたハワイ島マウナロア山における大気CO2の観測によるもので、この観測は1950年代末から現在まで続けられており、CO2観測の世界最長レコードとなっている。大会のオープニングでは、この大気観測と並んで長い歴史をもつハワイの海洋観測ステーション、Station ALOHAについて、ハワイ大学のDavid M. Karl氏による基調講演が行われた。講演では、HOT(Hawaii Ocean Time-series)やC-MORE(Center for Microbial Oceanography: Research and Education)などのプログラムによって得られた観測研究の数々が紹介された。これらの研究は微生物から海洋酸性化まで対象が多岐にわたっており、Station ALOHAが重要な観測拠点として位置付けられていることを実感した。特に、大気CO2観測に携わっている筆者にとって1988年から続く海洋酸性化モニタリングは印象深く、長期観測がもつ説得力の高さを改めて感じることができた。
3. エルニーニョ現象とCO2フラックス変動
BGでは炭素循環に関するセッションとして「温室効果ガス観測からフラックスへ:炭素循環のトップダウン測定(From GHG Observations to Fluxes: Top-down Measurements of the Carbon Cycle)」や「陸域炭素収支の現状とプロセス理解(Current Status of Terrestrial Carbon Budget and Process Understanding)」が開かれた。前者の「トップダウン」とは、炭素循環研究におけるいわゆる業界用語で、大気の濃度観測データから地表面の炭素収支を推定するアプローチのことを指す。一方、後者はタイトルにはないものの “トップダウン” とは逆の “ボトムアップ”・アプローチに関するセッションであり、陸域生態系モデルなどを用いて炭素収支を推定する研究の発表が行われた。
両セッションにおいて共通の話題となっていたのは、2015/16年の大規模なエルニーニョ現象に伴う地表面CO2フラックスの変動である。エルニーニョが発生すると、陸域生態系や海洋において大気との間のCO2フラックス量が大きく変化することが知られており、高温や干ばつ、海洋の循環の変化が寄与していると考えられている。しかしながら、このような気候変動に伴うCO2フラックスの変動メカニズムには未解明な部分が多く、温暖化予測の不確実性要因の一つとなっている。そのため、2015/16年に起きた大規模なエルニーニョは、近年、重要な解析対象となっている。
トップダウン・アプローチのセッションでは、NASAゴダード宇宙飛行センターのAbhishek Chatterjee氏がアメリカのCO2観測衛星OCO-2のデータを用いて海洋のフラックス変動に着目した解析結果を紹介し、コロラド州立大学のDavid Baker氏は同じOCO-2のデータから逆解析を実施して得られたフラックス変動を示した。一方、ボトムアップ・アプローチのセッションでは、NASAジェット推進研究所のAnthony Bloom氏やカルフォルニア大学バークレー校のTrevor Keenan氏がエルニーニョ時の陸域生態系におけるフラックス変動の解析結果を示した。なお、この両氏は共に、植生の総一次生産(Gloss Primary Production: GPP)を推定できるとして近年注目を集めているパラメータ、太陽光励起クロロフィル蛍光(Solar-induced chlorophyll fluorescence: SIF)を使用しており、SIFの注目の高さを感じた。
4. 中国の勢い
上記のトップダウン・アプローチのセッションでもう一つ印象に残ったものに中国科学院のLin Qiu氏の講演がある。Qiu氏は中国の次期CO2観測衛星TanSat-2の構想について講演を行ったが、その内容に少し驚いた。TanSat-2では1号機から観測項目が増える(CO2のみからメタンや一酸化炭素も観測対象となる)ほかに、観測頻度を高めるために同時に複数の衛星を投入するとされていた。また、衛星のみならず、地上観測の展開、特に超高層ビルやバルーンなどをプラットフォームとした都市域における観測を充実させることも図られており、衛星だけに限らずに多角的に観測をしていこうという意欲が感じられた。大勢の研究者と潤沢な資金がバックグラウンドとしてあるのであろうこの構想は、実現すれば、炭素循環研究の分野に大きなインパクトをもたらすものと思われる。
5. おわりに
筆者は自身の講演後に中国の研究者から「どうして日本は民間航空機を使った観測(CONTRAILプロジェクトのこと)ができるのか?」と質問された。中国では、先述の通り衛星プロジェクトを中心としてあらゆる観測が展開される中、唯一、壁にぶつかっているものが民間航空機を使った観測で、非常にハードルが高く、手がかりすら掴めないとのことであった。筆者はこの質問により、改めて、自身が参画しているCONTRAILプロジェクトが長きに渡って蓄積された経験や実績の上に成り立っていることに気付かされた。日本では東北大学が1979年から、気象庁気象研究所が1993年から民間航空機を用いた観測を実施している(この観測がCONTRAILプロジェクトの第一フェーズである)。これら日本の航空機観測が世界の中で見ても非常に貴重なものであることを心に留めつつ、この優位性を存分に活かせるよう、今後の研究を発展させていきたいと思う。