柴田 清孝(気象研究所、国立環境研究所客員研究員)
出牛 真(気象研究所)
CGERリポート
CGER’S SUPERCOMPUTER MONOGRAPH REPORT Vol.13
本モノグラフは、化学-気候モデル(Chemistry-Climate Model, CCM)を使って、過去25年間(1980-2004)の成層圏のオゾンや気候を再現した結果を載せている。気象研究所の大気化学モデル(MRI-CCM)に観測に基づく種々の外力(海面水温、温室効果気体、フロン、太陽紫外線変動、火山エーロゾル)を与えて数値積分し、オゾン層の振る舞いとそれに関連する気候変動を調べている。MRI-CCMの分解能は水平が約300km、鉛直が成層圏で約500mであり、化学モジュールは51化学種と124種の化学反応(不均一反応を含む)を扱い、初期値が少しづつ異なる5メンバーを使ったアンサンブル実験である。重回帰解析の手法を用いてオゾン・気温等のトレンドやQBO(準二年周期振動)の成分、太陽活動、エルニーニョ、火山噴火への応答の成分を取り出し、それらの時空間の構造について論じている。この研究により、将来のオゾン層とそれに関連する気候変動の予測精度の向上が期待されている。
成果の一部を紹介すると、オゾン全量の経年変化(図1)から南極の春先に起るオゾンホール(オゾン全量が220ドブソンユニット以下の領域)は1980年あたりから始まり、その後、面積は増加し続けるが、1990年代の半ばあたりから毎年ほぼ同じような値をとり続けている。衛星は極夜のオゾンを観測できないので、はっきりとは見とれないが、モデルはこの傾向をほぼ忠実に再現している。また、北半球の冬~春のオゾンの年々変動が非常に大きいことも再現している。
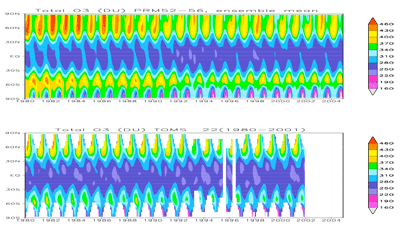
年平均、帯状平均気温のトレンド(図2)は成層圏界面(約1hPa高度)で温室効果気体の増加によって非常に強い冷却になっていることもモデルは再現している。さらに、オゾンでは2~5hPa付近に強い減少域があり、中高緯度でその値が最大値を示している。一方、熱帯では中部成層圏でオゾン減少の最小値を示している。
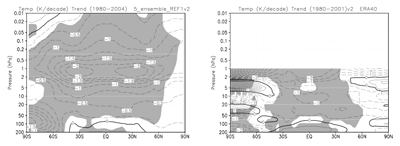
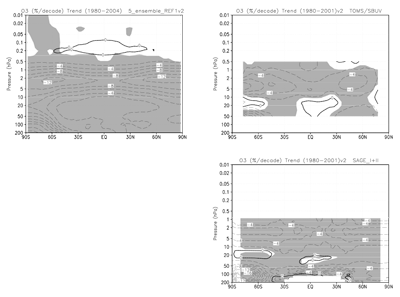

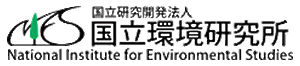
 PDF, 14.8 MB
PDF, 14.8 MB