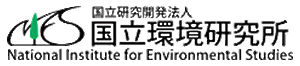国立環境研究所公開シンポジウム2019で地球環境研究センターの事業と広報活動を紹介しました
国立環境研究所では、毎年6月の環境月間に合わせて、研究で得られた最新の知見を広く一般の方に知っていただくために、講演とポスターセッションで構成する「公開シンポジウム」を開催しています。今年は6月14日に福岡県北九州市(北九州市立男女共同参画センタームーブ)で、21日には東京都港区(メルパルクホール)で「変わりゆく環境と私たちの健康」をテーマに開催しました。なお、本シンポジウムは、北九州市では初めての開催でした。地球環境研究センターからは、研究を紹介する6件のポスター発表を行いました。
講演開始前と終了後に設けられたポスターセッションでは、多くの方が研究者の説明を聞き、質問や議論をしてくださいました。

- あなたの家庭から排出されるCO2はどのくらい?—日本の家庭からのCO2排出量の時空間分布—(Richao Cong)
- 都市から排出されるCO2と熱の起源を大気モニタリングでとらえる(寺尾 有希夫)
- 大気汚染と気候変動の関係を探る—短寿命気候汚染物質の観測とモデリング—(谷本 浩志)
- 地球の息吹をとらえる—人工衛星「いぶき」のデータによる温室効果ガス吸収排出量の推定—(髙木 宏志)
- 海洋観測に基づく日本海における気候変動影響の検出(中岡 慎一郎)
- 地球環境を診察し、アドバイスする—地球環境研究センターの取り組み—(広兼 克憲)
地球環境研究センターの事業を紹介し制作物(パンフレット・動画等)を展示
ポスターセッション会場の一角で、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)が観測したデータに地上測定局のデータを合わせて地域別・時間別の吸収排出量を求め、そこから大気輸送モデルで推定した2009年6月から2015年10月までの世界の二酸化炭素濃度の推移(高度800 m付近の濃度の6時間ごとの動き)を動画で紹介しました。これをご覧になった来場者から「どうしてこんな動きをするのですか?」「この変化から何がわかるのですか?」「植生の光合成がこんなに吸収に影響するのですか?」「海と陸の違いは?」など、さまざまな質問をいただき、横田達也フェローが丁寧に説明しました。
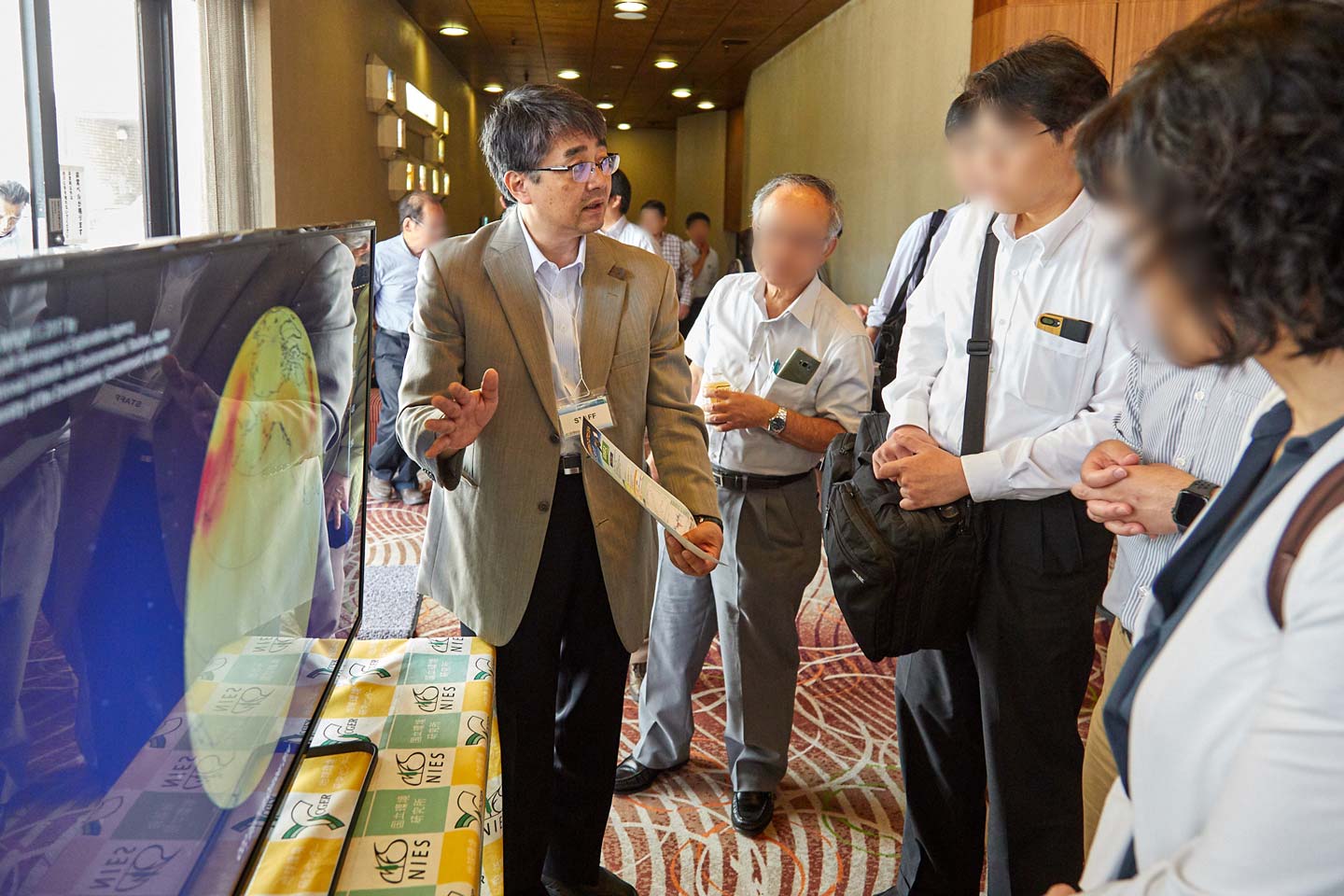
また、民間航空機による大気観測プロジェクト「CONTRAIL」で、航空機に搭載している二酸化炭素濃度連続測定装置の実物を展示し、どのような仕組みで世界各地での大気観測を実現しているのかをわかりやすく説明しました。「本物なのですね」と感心したり、「JALの飛行機全部に積んでいるのですか?」「データはどこに格納しているのですか?」ということに関心をもたれる方もいました。また、このような取り組みについて初めて知ったという方も多くいらっしゃいました。

1990年10月の地球環境研究センター設立当初から発行している「地球環境研究センターニュース」についても最近の内容とともに紹介しました。また、「ココが知りたい地球温暖化」のQ&Aのリーフレットも準備しました。このシリーズは地球環境研究センターのウェブサイト(ココが知りたい地球温暖化)でいまだに多くのアクセスを得ています。公開シンポジウムの参加者も興味のあるテーマのリーフレットを手に取っていました。
おわりに
ポスターセッションや休憩時には多くの方が展示コーナーを訪れてくれました。GOSATやCONTRAILプロジェクトについても説明員の解説を熱心に聞いてくれる来場者が多数いて、あらためて地球環境問題への関心の高さを知ることができました。
なお、公開シンポジウム2019の発表内容は、後日、国立環境研究所のビデオライブラリー(国立環境研究所公開シンポジウム)に掲載されます。